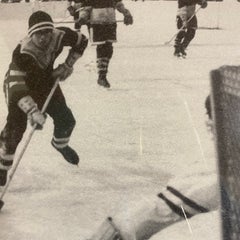一心寺、多くの人の納骨から立派な仏様をつくる
一心寺は大阪ではとても有名なお寺さんです。開創は文治元年(1185年)で、浄土宗の開祖法然上人によるものです。ここは納骨に訪れる人が多く、その遺骨を10年ごとに砕いて仏像に焼成し直すことで知られています。酒封じ祈願の本田出雲守忠朝の墓や8代目市川団十郎の墓などもありました。
↓山門(仁王門):平成9年に再建された前衛的な黒門で、仁王さま(阿吽像)が青銅で造られています。
↓大屋根の建物が大本堂です。↓左奥が納骨堂、右の大きい建物がお骨仏堂で、10年ごとに遺骨を集めて大きな仏像に仕上げています。
一心寺は大阪市天王寺区にある浄土宗の寺院で、宗派に関係なく参詣や納骨を受け入れるお寺として有名です。当寺院の発祥は1185年に法然上人がこの地に庵を設けたことと伝えられており、当時はこの地から西に海が見えたと言われています。
法然上人の没後、1596年に一千日の念仏修法を行い、寺を再興しました。当寺院は大阪冬の陣・夏の陣にて家康が本陣を敷いた場所としても知られ、戦場で討ち死にした武将の本多忠朝の墓があります。 本多は戦の前の晩に深酒をし、討ち死にする間際「戒むべきは酒なり」と言い残したと言われており、「酒封じの神」として知られるようになり、今では禁酒を誓う人も参拝するようになりました。 大阪市の無形民俗文化財にも指定されている当寺院で特徴的なのはモダンな山門と仁王像です。 山門は大阪城三の丸玉造門を移設したもので、「黒門」と呼ばれていましたが、1945年の空襲の際に消失してしまいました。現在の黒門は1997年に再建されたものです。
遺骨で仏様を造る
一心寺でこの前代未聞のしきたりが始まったのは明治20年です。安政3年(1856)、年中無休でおせがきの法要を営む常施餓鬼法要が始まりました。それにより、納骨に訪れる方も後を絶たず、納骨されたご遺骨をもっとも丁重にお祀りするためにお骨佛の造立が発願されたのです。
古来、霊場への納骨や納髪の風習があるように、故人の遺骨や遺髪をお寺に納め、永代にわたって供養するしきたりがありました。
また、仏教では仏像を造って礼拝することはこの上ない善根功徳とされています。多くの人々に礼拝される仏様を、遺族にとっては何より尊い故人のご遺骨でもって造立する。それにより、お骨佛を拝めば故人に供養するのと同時に、仏様を礼拝供養することになるのです。
まさに仏様への崇拝と先祖供養の精神が融合した、真に妙なる功徳の仏様、それが一心寺のお骨佛様なのです。
# 宝山寺(奈良県生駒市)広報から
もともとは役行者や空海が修験の場として開いたこの寺を、延宝6年(1678)に宝山湛海が中興し歓喜天を祀りました。般若窟と呼ばれる大岩壁を背景に本堂、聖天堂、多宝堂、絵馬堂などが立ち並びます。
色ガラスのはまった獅子閣(重要文化財)は明治17年(1884)に迎賓館として建てられた洋風建築で、訪れる人の目をひきます。
現世のあらゆる願いを叶えてくれるとされ、生駒の聖天さまと呼ばれ親しまれています。中でも商売繁盛の現世利益や禁酒といった断ちものを祈願する庶民信仰の寺として知られています。
生駒の聖天さんへの参道
大阪・キタの法清寺
「禁酒寺」のかしくさま
〝節酒〟祈願の多さに共感
山口瞳著『酒吞みの自己弁護』(ちくま文庫、新潮文庫)を読んでいて、面白いフレーズに思わず、膝を打った。

「酒をなぜ飲むかと言われれば、体にいいからとは答えない。 また、 体にわるいからとも言わないー-」
「曽根崎心中」で有名な大阪・キタのお初天神から歩いて5分 ″禁酒寺″と呼ばれる法清寺を訪ねた。
バー街の中にひっそりたたずんでいる。この地にいた遊女「かしく様」がご本尊である。
この女性はふだんおとなしいのに、酒が入ると人が変わり、ささいなことで兄を殺してしまった。
刑執行の直前に「油揚げ」を所望、その油で髪をとかし、次いで酒の害から世の人を守ろうと請願したという。
その後、歌舞伎や文楽で美化され、いつしか禁酒寺となった。
かしく様の前に置かれた「願かけ」をみると、「禁酒」より「節洒」の方が多いのがなんともおかしい。
当方も「缶ビール2本まで」という誓いをたててきたのだが……。
ところが、帰りに近くの「夕霧そば 瓢亭」(ここもお勧め)に入り、油揚げの入った「かしくそば」に舌鼓を打ちながら、生ビール大で乾杯。
適度に歩き回ったせいか心地良く酔い、「ほどほどの酒は体にいい」と自己納得した次第。
(法清寺〜日経夕刊1面コラム 掲載)