「オルタネーター (英: alternator) は発電機の一種で、エンジンなどから伝達される機械的運動エネルギーを交流 (英: alternating current) の電気エネルギーへと変換する装置である。自動車やオートバイ、小型航空機などに搭載されているものは、一般にはダイオードなどを使った整流器で直流へと整流されるので、整流器を含めてオルタネーターと呼ぶことが多い。」
ウィキペディアには、このように説明されています。
今日は、発電機の交換にチャレンジです。
上部の黒色の配線3か所には、マジックで「・」「・・」「・・・」と、それぞれ配線と差し込み口に目印をつけて、引っこ抜きます。
が、微妙にヘックス(トルクス)ボルトのような気がします。
いわゆる六角レンチと呼ばれるヘキサゴンレンチも、すっぽりはまります。
迷ったのですが、本の通り六角レンチで外してみました。
焼き付いているかもしれないので、プラスチックハンマーでこつんとやると、綺麗に外せます。
で、先ほどの本には、するりと外れるような記述があります。
時折拝見している、BMWR100RSモノサスの整備日記さんのHPにも、ぽろりんと取れるような感じで書かれています。
が、僕のBMWくんは、手前のカバーがぐらつくだけで、抜けてくれません。
えいやっ!と力を込めて引き抜くと、ろくなことはないだろうな、という感触です。
先ほどの、メンテナンスブックには、アルミ製のハウジングを引っ張らずに、奥の茶色の部分を引っ張れと書いてありますが、びくともしません。
プラスティックハンマーでこつんとやろうにも、奥まっているので、叩けません。
手前のアルミ製のカバーを、ごくごく軽く叩いてみたら、ぽろりとアルミ製ハウジングだけが外れました。
げげげ!
しかし、完全に外れたわけではなく、ハウジングの裏側で何かがつながっているままです。
僕のBMWくんには、何かスペシャルなものが乗っているのでしょうか?
期待が膨らみますが、写真を見比べても、どうやら普通です。
とりあえず、たばこを一本吸って、気を落ち着けて、真ん中のローターの部分のねじを外してみました。
左側は、ユーロモトエレクトリックさんで注文した、ローターを取り外すスペシャルツールです。
メンテナンスブックには、フォーシングスクリューという立派な名前で出ています。
これを取り外したねじ穴に、ぐりぐりと差し込むと、パコンという音とともにローターが外れるのだそうです。
ギアを二速に入れて、ねじ込んでみました。
不安になるほどねじ込んでいくと、バコン!と盛大な音がしてローターが外れた音がしました。
が、やはりハウジングは取れません。
もう一本タバコを吸ってから、奥の茶色の部分の隙間を探して、長めのマイナスドライバーでこじってみました。
すると、あっけなく外れて、 ごそっと部品が取れました。
もしや、壊してしまったのかと、ドキドキしていたので、写真はありません。
気が弱いくせに、こんなことをすると舞い上がってしまいます。
こんな時に、行ってしまえ!と突っ走ると、ろくなことはないような気がします。
そこで、作業は中止することにします。
またまた、ちまちまと部品を組み付け、カバーを取り付け、バイクをもとに仕舞います。
近所の人から見ると、ただの変わったオッサンなんでしょうねぇ。

にほんブログ村
ウィキペディアには、このように説明されています。
今日は、発電機の交換にチャレンジです。

ホームページで確認すると、このような作りになっています。

いつものように、ちまちまとねじを外して、ここまでたどり着きます。
近所のおっちゃんが出てきて、なかなか走らんな、と声をかけてきました。
大きなお世話です。
写真をあちこち取って、右側の赤色、緑色、グレーと黒の配線の位置を確認しておきます。
5月22日の日記に書いた、配線の練習で使ったコードがここに来ます。
上部の黒色の配線3か所には、マジックで「・」「・・」「・・・」と、それぞれ配線と差し込み口に目印をつけて、引っこ抜きます。
- BMWメンテナンスブック OHVボクサーツイン編 完全整備分解手帖 1969‐1996/著者不明
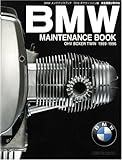
- ¥3,990
- Amazon.co.jp
が、微妙にヘックス(トルクス)ボルトのような気がします。
いわゆる六角レンチと呼ばれるヘキサゴンレンチも、すっぽりはまります。
迷ったのですが、本の通り六角レンチで外してみました。
焼き付いているかもしれないので、プラスチックハンマーでこつんとやると、綺麗に外せます。
で、先ほどの本には、するりと外れるような記述があります。
時折拝見している、BMWR100RSモノサスの整備日記さんのHPにも、ぽろりんと取れるような感じで書かれています。
が、僕のBMWくんは、手前のカバーがぐらつくだけで、抜けてくれません。
えいやっ!と力を込めて引き抜くと、ろくなことはないだろうな、という感触です。
先ほどの、メンテナンスブックには、アルミ製のハウジングを引っ張らずに、奥の茶色の部分を引っ張れと書いてありますが、びくともしません。
プラスティックハンマーでこつんとやろうにも、奥まっているので、叩けません。
手前のアルミ製のカバーを、ごくごく軽く叩いてみたら、ぽろりとアルミ製ハウジングだけが外れました。
げげげ!
しかし、完全に外れたわけではなく、ハウジングの裏側で何かがつながっているままです。
僕のBMWくんには、何かスペシャルなものが乗っているのでしょうか?
期待が膨らみますが、写真を見比べても、どうやら普通です。
とりあえず、たばこを一本吸って、気を落ち着けて、真ん中のローターの部分のねじを外してみました。
左側は、ユーロモトエレクトリックさんで注文した、ローターを取り外すスペシャルツールです。
メンテナンスブックには、フォーシングスクリューという立派な名前で出ています。
これを取り外したねじ穴に、ぐりぐりと差し込むと、パコンという音とともにローターが外れるのだそうです。
ギアを二速に入れて、ねじ込んでみました。
不安になるほどねじ込んでいくと、バコン!と盛大な音がしてローターが外れた音がしました。
が、やはりハウジングは取れません。
もう一本タバコを吸ってから、奥の茶色の部分の隙間を探して、長めのマイナスドライバーでこじってみました。
すると、あっけなく外れて、 ごそっと部品が取れました。
もしや、壊してしまったのかと、ドキドキしていたので、写真はありません。
気が弱いくせに、こんなことをすると舞い上がってしまいます。
こんな時に、行ってしまえ!と突っ走ると、ろくなことはないような気がします。
そこで、作業は中止することにします。
またまた、ちまちまと部品を組み付け、カバーを取り付け、バイクをもとに仕舞います。
近所の人から見ると、ただの変わったオッサンなんでしょうねぇ。
にほんブログ村


