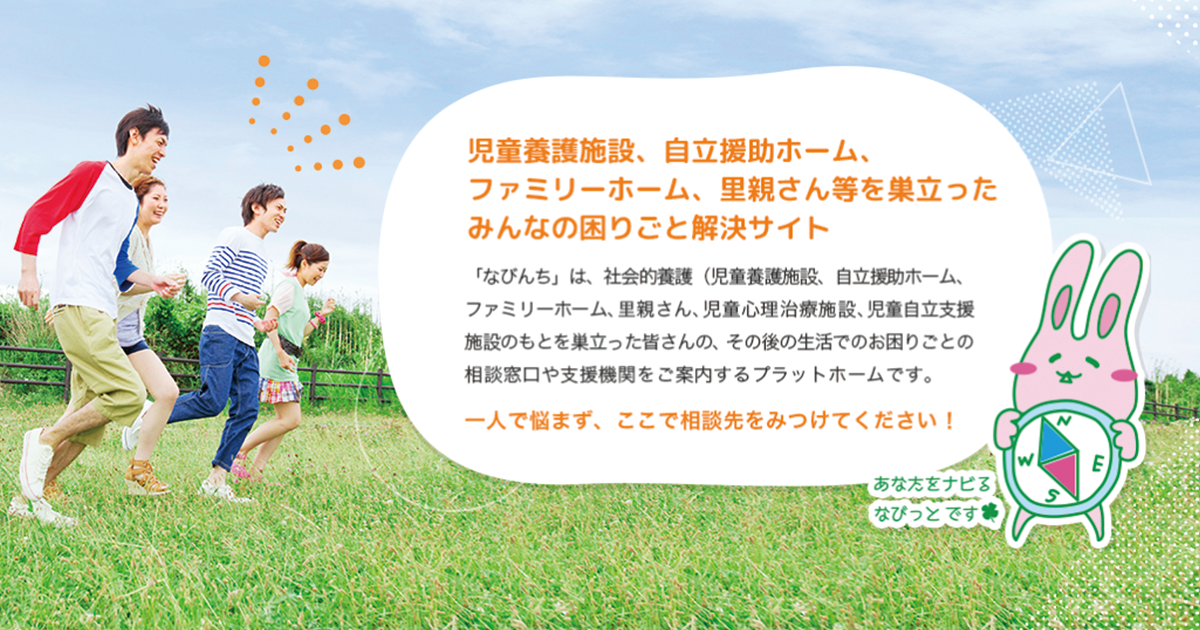
20年前と変わらない。。。
「必要とする若者に必要なタイミングで情報が届くように」児童養護施設や里親家庭などから自立する若者に向けに作成された〈ゆでたまごガイドブック〉
ガイドブックを更新し普及させようと活動をスタートし、去年はコロナ禍ということもありイベントは全てオンラインでしたが、ようやくリアルで開催できました![]()
児童養護施設出身の当事者、施設で働いていた経験のある方、里親の方、また社会的養護について知らないけれど何かしたいという方など30人近い人が参加してくれました。
ゲストは〈青少年の羅針盤〉と名付けられた一般社団法人「コンパスナビ」の高橋多佳子さん。埼玉県内の児童養護施設や里親等のもとを巣立つ若者の就労支援、自立支援、住居支援などのアフターケアを行っています。
実は高橋さんは〈ゆでたまごガイドブック〉を作成した自身も児童養護施設出身の阿部華奈絵さんを高校時代から知っていたそうで、本人も初めて聴いてびっくりしていました
親を頼れない子供を社会で支える〈社会的養護〉の対象となる子供は現在約4万2000人。7割が虐待を受けていて障害がある子供も40%いると高橋さん。
華奈絵さんもそうでしたが進学したいと思っていても経済的な理由から諦めざるを得ず60%が就職しているという現実。そして就職先も本人の希望ではなく、とりあえず〈寮ありき〉で決まることがほとんど。
18歳という年齢でいきなり自立しなければならない彼らは、対人関係も上手くいかなかったりして、誰にも頼れないまま2年以内に離職してしまう人が7割を超えているとのこと。
そんな現状を改善するために高橋さんはこれまで採用協力企業を開拓し続けてきました。コンパスナビで紹介している70ほどの企業のうち約50社から応援を取り付けたそう。社会人研修や職業体験ももちろん実施しています。
「施設で暮らす子供達に夢はないのでしょうか」と質問してくれた方がいました。夢は持っていても親を頼れない彼らは〈今〉を生き抜くのに精一杯なのが現実なのです。
「20年前と全く変わっていない」実は自分も児童養護施設出身だったと語ってくれた当事者の方の言葉です。ケアの情報量が少なく本人に届いていないとも指摘していました。
この方もやはり住めること働けるだけで十分と寮がある会社に就職したそう。5年前に自分で会社を立ち上げたそうで〈納税者〉の役割を果たせてますと胸を張って話してくれました。
また大学卒業後に児童養護施設で働き、児童相談所にも勤めた経験もあるという男性からは、施設の職員が本当に子供達と向き合っているのかという問いかけがありました。
この方自身も施設で働き始めた当時はまだ若く、体調を崩したこともあったと正直に話してくれました。子供達の心を育てることや生きていく上で必要な〈人間らしさ〉を教えていくことが大切だとも。
「子供達のためになっているのか」という視点で今も子供のケアに関する勉強会を開催したり関係者の連携をはかる活動を続けているとのことで私達の会でもまたお話を伺いたいと思います
先日のTBSラジオを聴いて参加してくれたという施設職員や里親と〈社会的養護〉にずっと関わっている男性。ゆでたまごガイドブックに記載されていることは、本来は施設にいる時に身に付けるべきことだという意見はまさにその通り。
華奈絵さんがゆでたまごガイドブックを作ろうと思ったきっかけは、施設以外の大人との繋がりもなく必要な情報を得られなかったという経験をしたから。
現場の職員さんが目の前のことでいっぱいいっぱいならば、社会的養護で足りていない部分を、地域の人などと共同で役割分担をする必要があるとの考えはまさに私達と同じ。
すでに活動している支援団体、行政、地域と連携を強めて、様々な事情を抱えているひとりひとりに向き合って、夢を描き未来を自分の手で選択できるように、幅広い支援をこれからもしていきたいと高橋さん。
自立は1人で何でも頑張ってやることではなく〈必要な時に人を頼れること〉が本当の自立です。コンパスナビのサイト「なびんち」には困った時に頼れる奨学金、就職、アフターケアなど多岐にわたる情報が掲載されています☞
次回のゆでたまご勉強会のゲストは子供の虐待防止と家族の笑顔を増やすため「たたかない子育て」講座の講師として活動する、NPO法人児童虐待防止全国ネットワークの高祖常子さんです。
https://www.tokiko-koso.com/policy
「たたかない子育て」は親と子供の両方の生きる力に繋がると話す高祖さん。みんなで子供を支える社会を目指すために何が出来るのか一緒に考えてみませんか 詳細はまたお知らせします
詳細はまたお知らせします![]()











