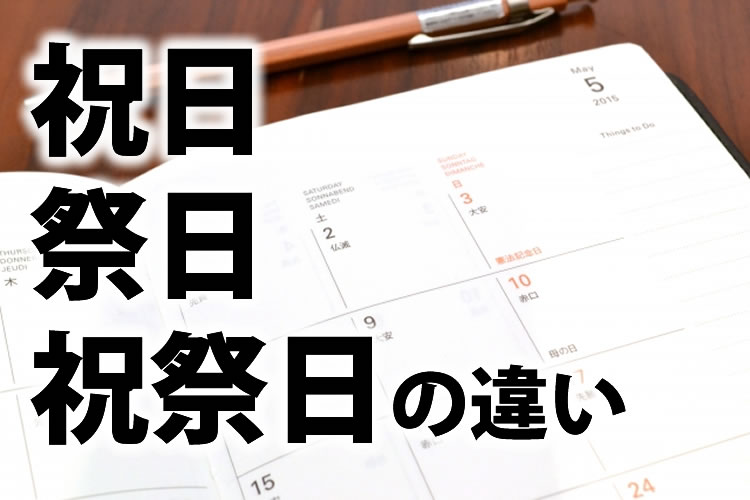もうすぐゴールデンウイークですね!
祝日は季節の変わり目である節句や天皇の誕生日など、基本的にはその名の通り
何かを祝う日とされ、特別な休日となります。
ところで、「祝日」と「祭日」と「祝祭日」の違いは何なのでしょうか?
社会人の教科書のHPに解説が記載されていました。
祝日は、「国民の祝日」というのがその正式な呼び方で、法律で定められた日曜日を除く
休日を言います。
この法律とは、具体的には「国民の祝日に関する法律(祝日法)」第2条を指しており、
昭和23年に施行されました。
祝日は、1月1日の元日に始まり、12月23日の天皇誕生日(2018年まで)に至るまで、
1年間で合わせて16日が制定されています。
これらの祝日が日曜日と同日になる場合は、その後に来る最初の平日が、
休日として振り返られます(振替休日)。
また、前後を祝日に挟まれた平日は、休日扱いとされることになっています(国民の休日)。
祭日とは、本来宗教において重要となる、祭祀(儀礼・儀式)を行う日を言います。
祭日はさまざまな宗教に存在しますが、日本の神道においても、多くの日が祭日として
定められています。
具体的には、2月11日の紀元節や、4月3日の神武天皇祭、10月7日の神嘗祭などです。
これらは明治41年に皇室祭祀令として定められ、その大半が、明治政府によって
国家の休日に指定されました。
現在、「祭日=休日」のイメージがあるのはこのためですが、前述のように、
実際は両者には明らかな違いがあります。
祝日は祭日と違い、宗教的な意味合いはありません。
なお、昭和22年に皇室祭祀令が廃止されたことにより、現在は法律で定められた
祭日は存在しません。
しかし、宮中祭祀では今なお行われており、現行の祝日にも、その一部が名前を
変えて引き継がれています。
祝祭日とは、文字通り祝日と祭日を掛け合わせた言葉です。
祝祭日という言葉が使われていたのは、主に明治の中頃から、戦後まもなくにかけての期間です。
この時期には、上記のように神道の祭祀(大祭)を基本として、それに国家の記念日(祝日)を
合わせたものを、休日として定めていました。
このことから、休日は「祝日大祭日」と呼ばれており、縮めて「祝祭日」というようになった
という経緯があります。
このように、祝日とは、日本の祝日法で定められた休日を言います。
つまり現在の日本には祭日は一切存在しませんが、俗称としてその言葉が残っているのです。
以上、長い休みを取ると社会復帰できなくなるのではと心配になる営業マンの日記でした(;^_^A