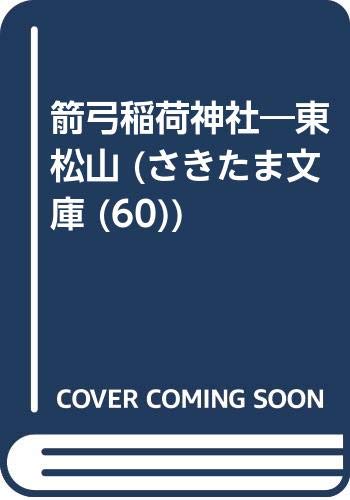こんにちは まさくんです。
昨日に引き続き 箭弓稲荷神社(やきゅうじんじゃ)記事になります
よりしければ境内等は昨日のブログにあります
↓ ↓ ↓ ↓
拝殿
右手に参集殿です
左手には牡丹園などがあります
昨日のブログの境内図に追記しました
名称は正しい名称でない物もありますのでご了承ください
本殿
瑞垣が建てられています
隙間から本殿の彫刻を見る事ができます
彫刻についての説明板も随所にありますので
社殿をゆっくり散策してみることができます。
(上)
本殿花頭窓彫刻 二龍
そもそも、龍には、人民救済、雨乞い、魔除け、鎮火などの御利益があり
ます。当社では二匹の龍が本殿両脇に位置し、ご参拝の方にご利益を
もたらすべく、本殿を守護しております。
(下)
本殿縁の下持送り彫刻 龍
社殿の彫刻で、水に関わりを持つ架空の霊獣や同様の動物などは、
その多くが社殿の地面に近い位置に飾られます。それらは、火の災い
を受けないように祈りを込められているからであり、当社では龍が本殿
の四隅に見られます。
本殿縁の下持送り彫刻 山椒魚
社殿の彫刻で、水に関わりを持つ架空の霊獣や同様の動物などは、
その多くが社殿の地面に近い位置に飾られます。それらは、火の災い
を受けないように祈りを込めらているからであり、水辺に生息する
山椒魚(さんしょううお)の彫刻も本殿の縁の下に飾られています。
また山椒魚は長寿の象徴で、仙人の化身ともいわれています。
本殿地紋彫り 入子菱文様
このように菱型の中に菱型が入る文様を入子菱、これが連なっているものを
菱繋といいます。他にも幸菱や、繁菱などがあり、当社では本殿土台に見る
ことが出来ます。
本殿縁の下持送り彫刻 水犀
水犀は、日本の霊獣で、その体形は鹿に、背中には亀の甲羅を
背負い、頭には一角を持ち、細い足には蹄が付いています。これ
は、水犀の名が示す通り、火災除けの彫刻です。
本殿縁の下持送り彫刻 獏
一見、中小の亀に寄せ来る波が題材と思える彫刻ですが、全体を見渡すと
亀と波とで、大きな獣を形作っていることに気づきます。この大きな獣が、人
の悪夢を食らうという「獏」なのです。
本殿大羽目彫刻 仙人の烏鷺
烏鷺(うろ)とは、烏と鷺(からすとさぎ)、それを黒石と白石に見立てて、
囲碁をするという意味です。この彫刻はひとりの樵(きこり)が仙人の
囲碁対局を見て楽しんでいる様子を題材にしています。ただ、彼の右手
にある斧の柄が腐るほど、長い時間が経過してしまっていたのです。
仙人ならぬ身の我々にとっては、人生を考えさせられる彫刻です。

本殿地紋彫り 蜀江錦繋文様
本殿の装飾を華やかに見せるべく、頭貫にこの文様が施されています。
蜀江錦の起源は、古代の中国四川省蜀地方で錦織物の一種です。
我が国で製作された最古のものは法隆寺にあります。その後、文様だけ
が伝承され、近世の京都西陣織などにも用いられています。
本殿蟇股彫刻 王子喬と唐子
中国周代の仙人である王子喬が鶴に乗り、唐子らに教えを説いている様子で
す。王子喬は、魏晋南北朝時代以来、赤松子と並ぶ古代の仙人の代表とされ、
詩文や絵画などに、たびたび登場してきました。
※蟇股(かえるまた)
上部の荷重を支えるための、かえるの股のように下方に開いた建築部材。
※魏晋南北朝時代(184年-589年)
長江中下流域(江南)における六朝時代がほぼこの時期と対応している。
むすび石
良縁拝受や子孫繁栄の御利益があるといわれています。
また、お食い初めの儀式の際に、石のように固い歯が生えますようにと願いを
込めて歯固めの石としてお使いください。
儀式が無事に終わりましたら、石は社務所にお返しください。
社殿左手側に位置します。

↑こちらの画像は拝借しました↑
稲荷みくじ
記念館の彫刻
駐車場のある記念館にも見事な彫刻が施されています。
海散歩は風が気持ち良かったです