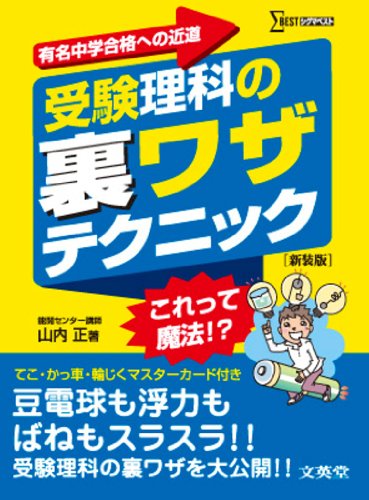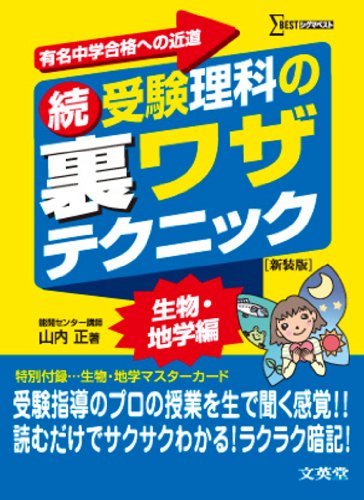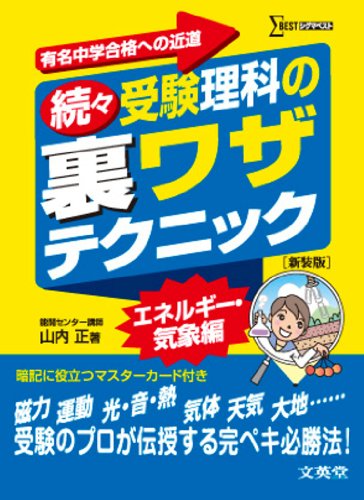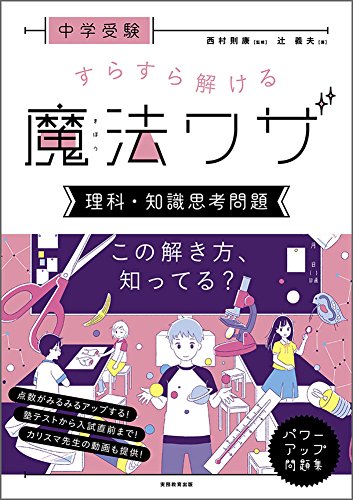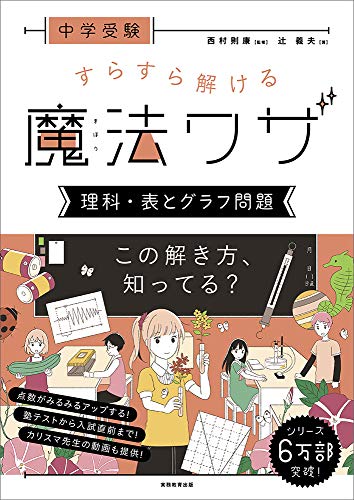おはようございます。ルッタです。
息子の現在の偏差値は、
算数 > 理科 > 国語 = 社会
大体このような感じです。
算数と理科については、ある程度勉強も進んでいます。
先日、算数については、これまでに使用した問題集に対する私見を書きました。
今回は理科について書いてみたいと思います。
以前から書いていますが、私は理科は大の得意です。
自分の入試でも、これまでほぼ点を落としたことはありません。
ある程度勉強法は確立出来ています。
まだまだ息子には伝えきれていませんが![]()
まず最初に特進クラスの理科を使用しましたが、以前書いた通り、これはうちには詳しすぎたため、1章の途中で断念しました。
最初は、軽く一通り流したいと思っていましたので。
そうなると、中学受験用の良い問題集は中々ありません。
色々さがした挙句、算数でも使用した下記の本に行きつきました。
算数でも使用した、このシリーズです。
簡潔に良くまとめられたいい本だと思います。
算数と同様、大人の事情なんでしょうか。
「一通り」勉強するには、若干使いにくいです。
私は、3冊を同時に使い、生物→地学→物理→化学の順番で勉強を進めました。
物理や化学には計算問題も出題され、その多くで比を使います。
なので、算数での比の勉強が進んでから、物理と化学の勉強をしようと考えました。
それと、特に生物は暗記することが多いので、先に勉強して、暗記する時間を出来るだけ増やそうという作戦です。
まだまだ生物の暗記が終わってないので、成功したかどうかは微妙です![]()
理科が苦手な子供の場合、例えば、月の満ち欠けに関しては、新月→上弦→。。。って感じで覚えるだけになっている場合も多いです。
その時の月の見え方(形)と共に覚えようとします。
でも、作図さえできれば、これは覚える必要はありません。
これらのシリーズでは、そういった事も解説されていますので、しっかりと基礎を叩き込むにはいい本だと思います。
そういう作図が出来れば、午前3時に沈む月はどの方向にどんな形で見えますか?みたいな問題はまず間違えません。
ある星が2月1日の午後10時に南中した時、この星は2ヶ月後の4月1日には何時に南中するでしょうか?
こういった問題を解く際も、本来基本は作図です。
もちろん、同じ時間では1日に1度西に動くので。。。みたいな解き方でも正解できますが、これは何回も作図で解いた後に勝手に使えるようになるのがいいと思っています。
作図が出来るようになる前に、こういった事を暗記だけで処理すると、ちょっと条件を変えられると手が出なくなります。
太陽の南中時間や、北極星の高度等、こういった類の問題は作図で処理する方がいいと思います。
話題が逸れましたが。。。。
次の本はこれです。
この本は、かなり繰り返し使っています。
知識編では、必須事項が上手くまとめられています。
コアプラスや、メモリーチェックの前に使うのがいいかもしれません。
思考編は、知識を上手く使えない場合正答率はかなり下がるような問題が選択されています。事実、上手く知識を使えない息子は結構苦労しています。
このシリーズは、3冊発売されており、全て所有しています。
中でも、計算問題は本当に良く出来ていると思います。
”勘”のいい子なら、この本だけでも相当なレベルの問題に対応できる力が付きます。
これは去年発売された一番新しい本です。
一応一通り終わらせましたが、上記2冊と比べると優先順位は低いかなといった印象です。
長くなりそうなので、後1冊。暗記用の本。
SAPIXが出している有名なコアプラスです。
我が家でも何周もして暗記させています。
この本を単なる暗記用の本として使うのは正直勿体ないと思うぐらい、色々な要素が満載の本です。
「すごいなー。」と正直感心しています。当然ですが、私にはこんな本は作れません。
私が思う注意する点としては、この本を単なる暗記用の本として使うのでは本来の効果は期待できないという点です。
それぐらい、色々な要素が満載の本だと思っています。
うちは親塾なので実際の所は全く分かりませんが、SAPIXでどのようにこの本が扱われているのか興味があります。
この本に含まれている「要素」を解説した上で暗記させているのか、それともただ単に暗記させているのか。
もし後者であるなら、申し訳ありませんが、私の方がこの本を「上手く」使えると思います。
最後に少し解説がありますが、基本解説の無い暗記用の本です。
なので、例えば受験理科の裏ワザテクニックみたいな本で、理解できていない項目について解説を加えながら一通り終わらせるのがいいのかなと思います。
その後、暗記用として繰り返していけばいいのではないかと。
やっぱり長くなりましたので、今日はここまでにします。。
クリックをお願いします![]()
ブログ更新の励みになります![]()