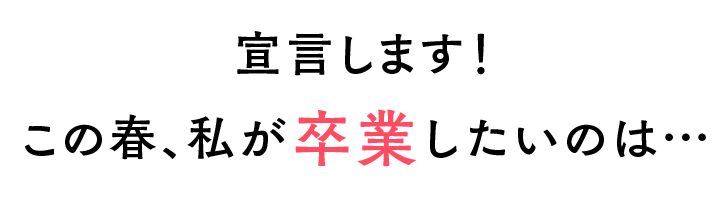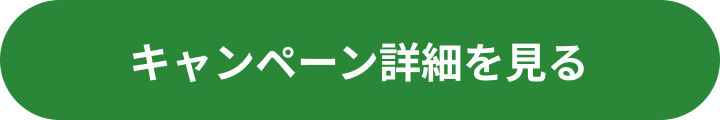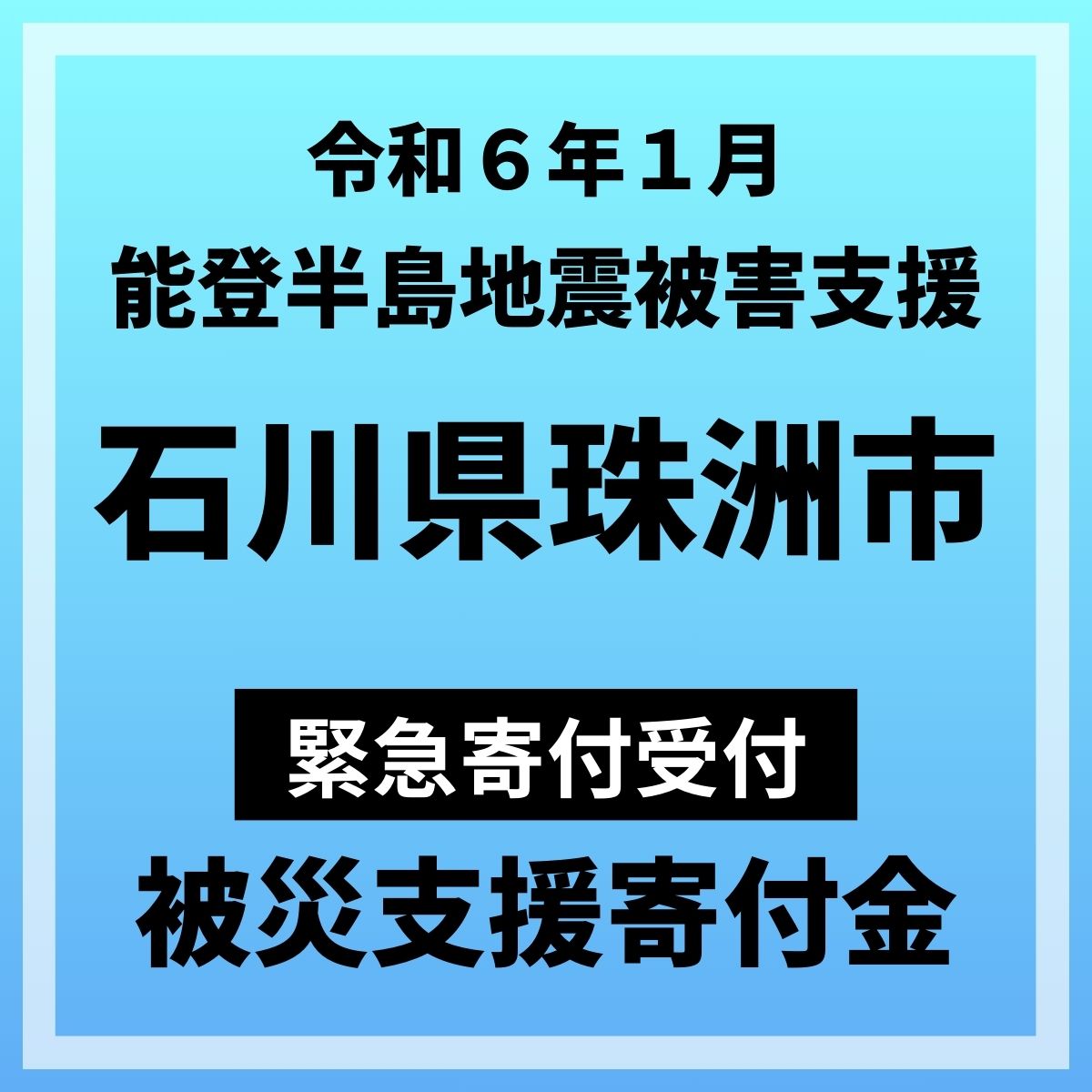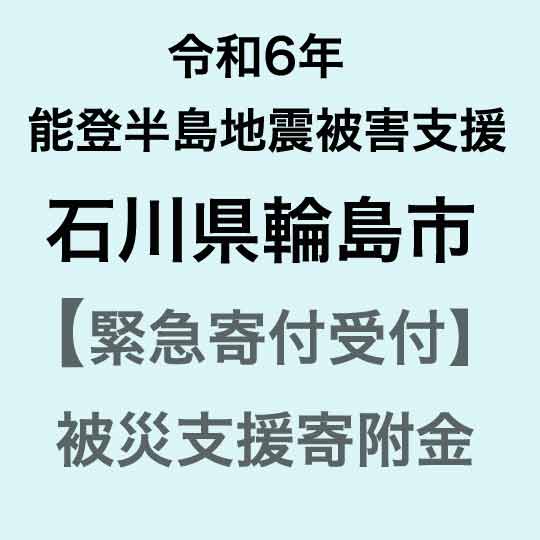義両親の「介護」です
今日も
私のブログを見に来てくださり、
ありがとうございます。
48時間の間に
義両親を亡くしました。
(義母1/31朝、義父2/1夜)
今日は納骨でした。
昨晩は早めに休みましたが、夜中の2時半に目が覚めました。それから眠れなくなってしまいました。
息苦しくなって、喘息予防の吸入をして、どうにか難を逃れましたが、喉もかわいて。水分とって眠れました。
そしたらへんな夢見て、隣で寝ているはずの主人が「悲しい、さびしい」と泣いているのです(夢の話です)。泣いていたのは、義父だったのかもしれない。離れがたいのかな。
四十九日の話を知っていますか?
故人は亡くなってから49日後に仏の元へ向かうとされています。それまでの間、7日ごとにお裁きを受け、49日目に来世の行き先や極楽浄土に行けるかどうかが決まる最後の審判を受ける日が四十九日だと考えられているのだそうです。
故人が極楽浄土に行けるように、遺族も7日ごとに祈ることで故人に善い行いを足していくとのこと。
故人の最後の審判が下る四十九日は、最も重要な日であると考えられているため、盛大な法要を行い供養するというので、「お義父さんとお義母さんの行き先は決まったのかな?」と、そんな思いで、法要に向かいました。
【持っていくもの】
*遺骨2人分(埋葬許可証)
*遺影2つ(大小)
*白木の位牌2つ
*納骨費用
*お布施
*お寺さんへお車代
遺骨は、車の後部座席の孫に抱かれて乗りました。
すごく冷静な自分がいて、「霊園の法要室にはいろんな仏具があるけど、宗派によって使い分けるのかな」とか。
二人一緒の納骨って珍しいですよね。
「こちらです」と通された法要室には、遺影を飾る台が1つしか無かった。すぐにもう1つ出してもらったけど、事前の打ち合わせはどうなってたんだろうかと。
今日まで白木の位牌でしたが、今日の法要では本位牌に魂を入れてもらいました。
魂を抜いた後の白木の位牌はただの木の札になるそうなので、お寺さんに預けて、お焚き上げをして処分してもらうそうです。
法要から納骨まで1時間くらい。
今日は雲1つ無い天気で、高台の墓地に義両親は二人仲良く土に還っていきました。
義両親のお墓には塔婆受けがありません
塔婆受けがあることが当然だと思っていた私は、四十九日にお塔婆を用意しないのかと義兄に話をしました。叔父さんからも問い合わせがあったため。そしたら、返ってきた返事は「無くていい」でした。塔婆受けが無いのだから、準備しても置く場所がありません。
御斎(法事後の会食)は無かった
法事後、施主が列席者を招待して行なう会食の場を御斎(おとき)と言います。僧侶や参列者に対する感謝の思いを示した席であり、参列者全員で思い出話をして故人を偲ぶ目的もあります。
しかし、施主である義兄は「御斎」を省きました。霊園でお食事を用意してくれるそうですが、そんなに大きな場所ではないのと、午後からの法要だったため、「御斎」はありませんでした。
義兄からの指示で、私たちは返礼品を準備しましたが、義父の弟(叔父さん)は、たくさんの香典をくださったので、あまりにも少額の返礼品になってしまいました。
宗派によって違うこと、いろいろ学びました。
【浄土宗】
浄土宗は法然上人を宗祖とする宗派です。当時の仏教は公家や武士だけのものでしたが、法然上人はその根本を変え、一般民衆も救われるようにとすべての人が「南無阿弥陀仏」を唱えることを一般民衆にも根付かせた現在の仏教にとっても重要な宗派です。公家や武士だけでなく、経典を学び、寺院へ寄進や参詣する余裕のなかった多くの一般民衆にも希望を与え、日本全土に浸透しました。
↓この下にも記事は続きます
家に戻って、後飾り壇を片づけて、新しい場所に義両親の夫婦位牌を置きました。
こうして、忌明けを迎えました。
御斎がなかったので、ささやかながら、主人と息子たちと夕飯は外に食べに行きました。
今頃、墓地では、義母が義父に「おとうさん、今日の夕飯何にしましょうか?」と問いかけているかもしれません。
お疲れ様でした。
▼本日限定!ブログスタンプ