ヴァルター/ヴィーン・フィルの1936年5月24日(ちなみに、この日の演奏会は、マーラー没後25年の追悼演奏会であったようですが)の録音によるSPのあと、1951年にクレンペラー/ヴィーン交響楽団の颯爽とした演奏による初LPが米Voxからリリースされるまで、この曲のレコードはまったく出されませんでした。15年もの長い期間、『大地の歌』という曲はヴァルター/ヴィーン・フィル、そして何よりも、トールボリィとカルマン(クルマン)の二人の歌唱によって多くの人に親しまれてきたのでした。
とは言っても、レコードの歴史の上では空白の15年ですが、実際のコンサートではかなりよく取り上げられていたことは言うまでもありません。LP時代にも多少は接する機会があったのですが、CDの時代になって、かなり多くの古い録音に接することができるようになりました。
その中には、第ニ次世界大戦中のものが二つあります。
まず一つ目は、カール・シューリヒト指揮、コンセルトヘボウ・オーケストラのもので、1939年10月5日のライヴです。
独唱は、シャスティン・トールボリィ(注1)とカール・マルティン・エーマン(注2)という二人のスウェーデンの声楽家です。
これは1993年にarchiphonレーベルから出されたもので、第6曲「告別」の途中で、聴衆の中の女性が
“Deutscland uber alles, Herr Schuricht!!”
と非常にはっきりとした、冷静と言ってもいい声で「発言」していることでも有名な録音です。
この「発言」というか「ヤジ」の真意についてはいろいろと取りざたされていて、中には正反対の解釈(つまり、親ナチ的な発言とするものと反ナチ的な発言とするもの)もあるようですが、その発言のタイミング――練習番号47と48の間、ちょうどアルトが
“Er stieh vom Pferd......”
と歌い出す直前――から考えると、悪意をもって演奏の妨害をしようとしたのは明らかなようです。
この妨害にもまったく動揺を感じさせることなくトールボリィは実に立派に最後まで歌っています。
この録音は、その後コンセルトヘボウのアンソロジーの第1巻(1935-1950)に収められていて2002年に出たもの(たぶん音質などはこれが一番いいと思います)をはじめ、何種類かの形で出されていますので、ぜひ一度お聴きになってみてください。
- Mahler: Das Lied von der Erde/Gustav Mahler
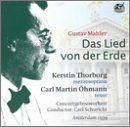
- ¥1,628
- Amazon.co.jp
もう一つの大戦中の録音はアルトゥール・ロジンスキィ指揮、ニューヨーク・フィルによるものです。これも非常に立派な演奏なので、きちんとした形での再発売が切望されます。
1944年11月19日のライヴ
この録音については、あと2点書いておきたいと思います。
まず一つ目は独唱者がトールボリィとクルマンというヴァルター盤のコンビであるということです。『大地の歌』といえばこの人たちが圧倒的な第一人者であるという定評がすでい出来上がっていたのかもしれません。
そしてもう一つ、この録音を聴いて興味深いというか何か微笑ましく感じてしまうのは、一曲終わるたびに(それも決してフライング気味ではなく)盛大な拍手が起こり、演奏者の方もそれを好ましいものとして受け止めている雰囲気が伝わってくることです。60年以上昔の録音ですから、断定的なことは言えませんが、でも、聴いているとそのように感じられてくるのです。
1939年10月5日のアムステルダムと1944年11月19日のニューヨーク、大戦中といってもおそらくいろいろな意味で対照的な状況であったと思われる中での二つの演奏が残されていたことはとても意義深いことだと思います。
そしてそのどちらでも名唱を聴かせてくれているトールボリィという人に限りない感謝を捧げたいと思います。
(注1)Kerstin Thorborgという偉大な歌い手の名前のカタカナ表記が昔から「トルボルク」とか「トルボルイ」などと不安定だったので、とても気になっていました。このたび里の猫さん にお訊きしたところ、「シャスティン・トールボリィ」というのが一番近いのではないかと教えていただくことができました。以後このように書かせていただきたいと思います。里の猫さん、ありがとうございました。
(注2)Carl Martin Ohmann(Oにはウムラウトがあります)なんですが、この人は何という表記がふさわしいのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。



