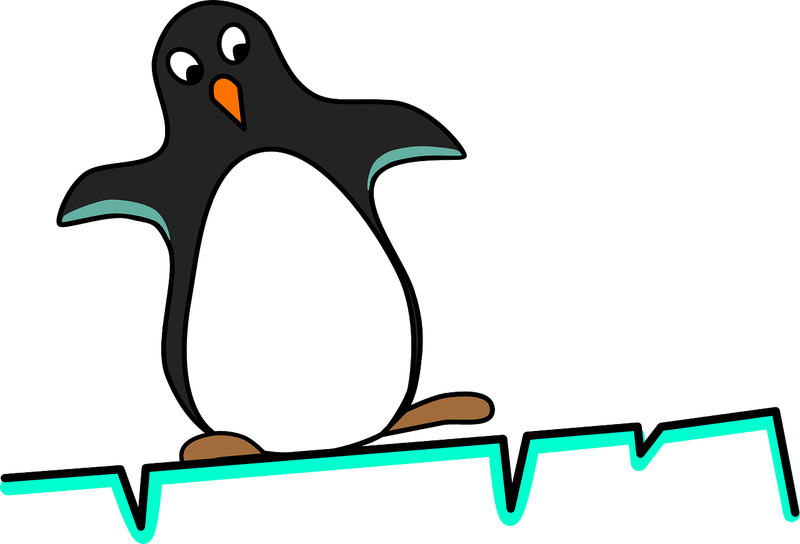起こってもいないことに不安になる人へ その知恵袋と対処法
起きてもいないことなのに、自分で勝手に心配して身動きが取れなくなっている人は多いです。
起きてから不安になるのは当たり前ですが、「起こってもいないことに不安になる」という症状は、いわゆる「不安障害」の一種かもしれません。
筆者もそういうタイプでした。
先読みして不安にならないように慎重にことを運ぼうとしていました。
しかし、それを繰り返すと、なにか不安なことに直面すると、その次は起きてもいない不安のことが不安になり、不安が雪だるま式に膨らんでいくんですよね。
不安は自分を守ってくれるありがたい感情ですが・・・
不安は自分の身を守るためにあります。
ネガティブな感情を言われるすべての感情は意味があります。
全部が自分の命を守るためです、極論すれば。
人間に必要な感情ですが、起きてもいないことに不安になったり、こうなったらどうしようという不安が強いと、逆に自己否定や落ち着かない精神状態に陥り、精神面から自分を守れなくしてしまうことも事実です。
これらの不安障害は、不安や心配や恐怖などの強い感情が、仕事でも日常生活でも、悩む人の脳を支配し、次々と自分で不安を生み出し続けるため、不安が不安を増幅させる負のスパイラルに陥ります。
普通は、起こってもいないことに不安になることはなく、起きてしまったとき初めて狼狽するものですが、不安障害のレベルとなると、何もしていないうちから、自分で不安の種を見つけ出してしまうのです。
もちろん自分では起こってもいないことに不安になることが馬鹿らしいとわかっていますが、どうしてもそう思い込めません。
それは不安の感情が強すぎるからです。
この不安を飼いならすことができるかどうかが、今後の幸せな生活を取り戻せるかどうかの大きなポイントとなります。
起こってもいないことに不安になる原因は?
この不安症状が発生する原因は様々です。
過去のトラウマや心の傷、生育環境、過剰なストレス、自己否定感につながる経験、脳内の神経伝達物質分泌のバランスが崩れている、といった原因が考えられます。
・過去にトラウマやストレスを経験し、時間が解決せず、その負の経験値で不安が生み出されてしまう
・慢性的なストレスに晒され、心が弱っている
・過度に心配性であったり、心配性の親に育てられた
・自己肯定感が低く、自己嫌悪や劣等感を感じやすい
・人間関係が苦手で、孤独感がある人
・人生で満たされた経験が少なく、感情を抑圧して生きている
といった人が、起こってもいないことに不安になりやすい人だといえます。
より具体的に不安障害になりやすい人の特徴を書いていきます。
・過去にトラウマやストレスを経験し、時間が解決せず、その負の経験値で不安が生み出されてしまう
過去に身体的、心理的、あるいは社会的トラウマを経験すると、その後のストレスや不安をもたらす刺激に対し、過剰な防御反応を引き起こします。
自動的に不安が起きてしまうため、過去のトラウマや負の経験値への囚われを解消する必要があります。
それができたとき、不安症状が解消していきます。
・慢性的なストレスに晒され、心が弱っている
長期間にわたってストレスにさらされ、そのはけ口がないと、心理的に強い悪影響を与えます。
常に脳疲労をお越し、自律神経の働きが悪くなり、心がもろくなります。
長年に蓄積されたストレスを解消する必要があり、同時にストレス耐性を強くしていく必要があります。
・過度に心配性であったり、心配性の親に育てられた
些細なことでも過度に心配してしまうには理由があります。
心配することで最悪な場面を避けようとする心の働きがあります。
問題が起こってもいないのに不安になるのは、問題が実際に起きたら更に酷いストレスを感じることになります。
また親が心配性だと、幼少期からその親の特徴をコピーしてしまいます。
大人になって自立したとしても、それは刷り込みのように無意識に深く定着していきます。
心配しても心配を生み出してきた(安心したことがない)自分の人生を振り返ってみましょう。
認知の歪みに気づくことで、起こってもいないことに不安になる馬鹿らしさが笑い飛ばせるようになると、不安や心配する必要はないと無意識レベルで気づいていきます。
・自己肯定感が低く、自己嫌悪や劣等感を感じやすい
自分自身に自信を持っていない、自分が好きではない、どうせ何をやってもだめだと思っている人は、不安が勝手にひどくなっていきます。
自信がない分だけ、不安を感じることで、最悪でリスクのある場面を避けようとしますが、それは心の罠です。
しかし、自己肯定感や自信はいきなりつけようと思ってもつけられないです。
無理やり思い込もうとしてもできない自分にショックを受けるだけですので、まずは自己肯定感がなく不安を感じやすい自分を受け入れることから始める必要があります。
それが後々の自己肯定感を上げ、不安を解消する突破口となります。
そこから始めなければなりません。
・人間関係が苦手で、孤独感がある人
社会は人間関係で成り立っており、人間関係で苦手な人、奥手な人は、不安を感じやすくなります。
不安の多くは対人不安と結びついていることが多く、起こってもないことに不安になる、こうなったらどうしようという不安というものは、どこかで対人的な心配と結びついています。
そして孤独な人ほど、相談できる人がおらず、自分ひとりで問題を解決しようとするため、不安を感じやすい思考をしてしまいます。
認知の歪みを作りやすく、自分で自分を追い込みやすくなります。
・人生で満たされた経験が少なく、感情を抑圧して生きている
ずっと自分を抑えて生きてきた人は、満たされた経験が少なく、ストレスが多い人生だった人は、そのまま不安も強くなります。
ずっと感情を抑圧して生きてくると、そのストレスで不安が強いときに分泌される神経伝達物質のコルチゾールが増えます。
コルチゾールを抑える必要があります。
そのためには、瞑想、呼吸法などが有効的です。
深いリラックス感や意識の変容状態に入ることで、コルチゾールを抑え、幸せホルモンのセロトニンやドーパミンなどを増やすことができます。
他にも人から嫌われることが怖いという人も「こうなったらどうしよう、嫌われたらどうしよう」など起こってもいないことに不安になりやすいタイプでしょう。
「起こってもいないことに不安になる」対処への知恵袋・「こうなったらどうしよう」不安解消への知恵袋
こういった不安障害になった原因や、なぜ自分がそういう思考や負の感情が生まれたのか、しっかりと把握する必要があります。
- 自分を客観視し、不安が生まれるルーツ分析をしましょう
- また無意識に抑圧してきた負の感情を解き放つこと
- 蓄積しているストレスを解消すること
- 悩んでいる自分を受け入れること
- 不安が自分を守ろうとする強い感情であることを理解すること
- なんでも都合よく解釈する癖をつける
- 起こってもいないことは、もう考えてもしょうがない、起きてから対処すればいいと割り切る
- とにかくリラックスする、緩む
- 専門家の力を借りる
はっきりいえば、意味がない不安です。
とてももったいないことをしています。
自分がどのような状況で不安を感じるのかをルーツ分析し、何によって不安が引き起こされるのかを特定しましょう。
そして、その不安というものが、本当に実態があるものなのか、自分の想像の中で膨らんでいるのかも客観的に分析しましょう。
不安と緊張だらけで、しかも想像で膨らんでいるネガティブな感情にダメージを受け続けている脳を緩めましょう。
-
考えすぎが不安を引き寄せる 脳覚醒のために知るべき秘訣
-
不安とは?不安と悩み脱出、不安と成功の関連
-
不安・焦り・恐怖のコントロール方法
-
不安の感情が出た際の対処法
-
安心の中に不安あり、不安の中にこそ安心がある
-
リスク要因はリスクではなく、不安要素は不安ではない
-
パニック障害と自己客観視、パニック脳の上書き
-
あがり症、社会不安障害、対人恐怖克服方法
-
心の悩み好転への恐怖と屈折した心の矛盾
-
不安、焦り、パニック対処法 対策と克服方法
変わることを恐れない コミュニケーション能力不足からの大逆転
高橋与一さんのブログもとても刺激になります。
【あしたのために】岩波の言葉、私が学んだこと
「起こってもいないことに不安になる」ことへの対処法と知恵袋
「こうなったらどうしよう」という不安を解消するための知恵袋
でした。
体験者の動画解説