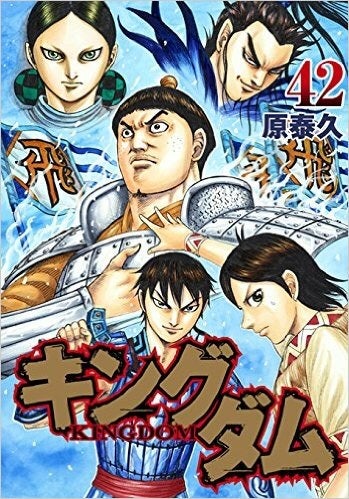今日は横浜からの帰り道、駅まで歩いてたらけっこう雨が降ってきました。見渡す限り半袖で歩いてるのはボクしかいない。「さすが北国から来た男」だと優越感を感じながら傘もないので歩いてたボクです。ということで、今回は最近ハマりにハマってる漫画「キングダム」について書きますが、キングダムに全く興味ない人は時間の無駄になるので閉じて下さいね。
雨がとっても気持ち良かったな。
■信(李信)~たぶん 主人公です(笑)
出典
www.manga-max.com
戦争孤児の少年。低い身分から自らの腕で「天下の大将軍」となることを目指す。1話冒頭で「李信」と呼ばれている。豪気且つ直情径行で、自分の意志を貫く頑強な心を持つ。ただ礼儀作法は知らず、秦王である嬴政も堂々と呼び捨てている。
相手が格上であってもそれに比例して自分の実力を底上げする武の天稟の持ち主。漂によると「自分が勝てない相手に信は勝つことができる」と言う。当初は自分の武力で全てを片付けようとする猪突猛進型であったが、王騎からの修行や助言、幾多の経験を経て「将軍」としての実力を身につけていく。
さて実際は?
“李 信(り しん、生没年不詳)は、中国戦国時代から秦代にかけての秦の武将。”
出典
李信 - Wikipedia
出典
kingdom-chuukatouitsu.com
“紀元前225年、秦王政は、楚を征服したいと思い、対楚戦にどれだけの部隊が必要かを諮問した。李信は、「20万」が必要だと語った。一方で王翦は、「60万」が必要だと語った。<中略> 李信と蒙恬は、郢周辺を攻め、再び楚軍を破る。しかし、城父で李信と蒙恬が合流した所を、三日三晩追跡して来た項燕率いる楚軍に奇襲され、2カ所の塁壁を破られ7人の将校を失う大敗を喫した。そのため、王翦と交代させられた。”
出典
李信 - Wikipedia
キングダムが春秋戦国初体験の読者には、クラクラするような経緯ですね。
李信と蒙恬が共に戦うのはまだしも、失敗して王翦と交代・・・!?
“対楚戦の失敗後も粛清されず、また子孫が残っていることからも秦王政より一応の信用は得ていたと考えられる。曾孫に前漢時代の将軍・李広がおり、その子孫に李陵がいる。五胡十六国時代に西涼を建国した李暠は李広の子孫を称し、その子孫に唐の李白がいる。”
出典
李信 - Wikipedia
秦王政の粛清、というのも気になりますが、その後「信」の一族は命脈を保つようです。
挙句の果てに漢詩で有名な李白が子孫になるとは・・・?
李白 - Wikipedia
李 白(り はく、701年(長安元年) - 762年10月22日(宝応元年9月30日))は、中国の盛唐の時代の詩人である。字は太白(たいはく)。号は青蓮居士[1]。唐代のみならず中国詩歌史上において、同時代の杜甫とともに最高の存在とされる。奔放で変幻自在な詩風から、後世「詩仙」と称される。
■嬴政(始皇帝)
出典
youngjump.jp
秦国の若き王。後の始皇帝。漂と瓜二つの容姿をしている。
出生の関係から幼少時代を趙国で育ち、その際、趙の人々に憎しみの対象として虐げられていたため、味覚・痛覚・嗅覚が全く無く、他人を一切信じようとしない荒んだ性格であった。昭王の崩御後、秦国への帰路で紫夏との出会いを通じて失っていた五感や人を信じる気持ちを取り戻した。
“始皇帝(しこうてい、紀元前259年 - 紀元前210年)は、中国戦国時代の秦王(在位紀元前246年 - 紀元前221年)。姓は嬴(えい)、諱は政(せい)。現代中国語では、始皇帝(Shǐ Huángdì)、または秦始皇(Qín Shǐ Huáng, チンシュフアン)と称する。紀元前221年に史上初の中国統一を成し遂げると最初の皇帝となり、紀元前210年に49歳で死去するまで君臨した。”
出典
始皇帝 - Wikipedia
おおむね今進行中のストーリーと同じです。
さて実際は?
出典
ja.wikipedia.org
始皇帝肖像画
後期に想像で描かれたものだとは思いますが、なんかイメージ狂います(笑)
血筋に対する議論
“漢時代に成立した『史記』「呂不韋列伝」には、政は子楚の実子ではなかったという部分がある。呂不韋が趙姫を子楚に与えた際にはすでに妊娠していたという。後漢時代の班固も『漢書』にて始皇帝を「呂不韋の子」と書いている。”
出典
始皇帝 - Wikipedia
これはショッキングな内容。これから先の物語で使われる可能性もあるかも。
■呂不韋~ボクは呂不韋が大嫌い(笑)
出典
yokimangamotomu.blog24.fc2.com
元商人の立場から前秦王「荘襄王」を秦王にした功績で秦の右丞相となった男。秦の王宮内を竭氏と二分し、権力争いを繰り広げる。
王弟反乱鎮圧後は秦国における最大の勢力となり、政に代わって政治を執り行っている。その裏では政の暗殺を企む(蔡沢曰く遊び心によるもの)など、様々な思惑がある模様。
太后と密通してまで後宮勢力を味方に付けたために、政権争いが大きく動くこととなる。現在は丞相の上の相国という地位に就いている。
さて実際は?
“呂 不韋(りょ ふい、繁体字:呂不韋、簡体字:吕不韦、ピン音:Lǚ Bùwéi、ウェード式:Lü Pu-wei、? - 紀元前235年)は、中国戦国時代の秦の政治家。始皇帝の父・荘襄王を王位につける事に尽力し、秦で権勢を振るった。荘襄王により、文信侯(ぶんしんこう)に封じられた。始皇帝の本当の父親との説もある。”
出典
呂不韋 - Wikipedia
奇貨居くべし
“趙の人質となっていて、みすぼらしい身なりをした秦の公子・異人(後に子楚と改称する。秦の荘襄王のこと)をたまたま目にして、「此奇貨可居[1]」(これ奇貨なり。居くべし。「これは珍しい品物だ。これを買って置くべきだ。」)と言った。こうして陽翟に帰った呂不韋はこのことを自分の父と相談した。度重なる話し合いの結果、呂父子は将来のために異人に投資することで結論がまとまったという。やがて呂不韋は再び趙に赴き、公子の異人と初めて会見した。”
出典
呂不韋 - Wikipedia
■羌瘣
出典
matome.naver.jp
伝説の刺客一族「蚩尤」の後継候補として育てられた羌族の少女。年齢は信の一つ下。緑穂(りょくすい)という剣を武器に戦う。
蚩尤を決める“祭”で姉のように慕っていた羌象を謀殺された事から、復讐のためだけに生きる道を選び、里を出奔。しかし一族からは、“祭”で勝ち残ってもいないのに外界へ出ているため、裏切り者と呼ばれている。
さて実際は?
“羌 瘣(きょう かい、生没年不詳)は、中国戦国時代の秦の武将。秦王政(後の始皇帝)に仕えた。”
出典
羌カイ - Wikipedia
なんと、羌瘣は女性キャラなので架空の人物かと思いきや・・・実在しました。
“紀元前229年(始皇18年)、代を伐った。
紀元前228年(始皇19年)、王翦と共に趙を攻め、幽繆王を東陽で捕らえ趙を滅ぼした。さらに、兵を率いて燕を攻めんと中山に駐屯した。”
出典
羌カイ - Wikipedia
経歴を見ると秦の一武将だったようです。
■王騎~ボクが一番好きな武将
出典
f.hatena.ne.jp
秦国六大将軍の一人。そしてかつて昌文君と共に昭王に仕え、中華全土に名を馳せた武人。
かつてありとあらゆる戦場にどこからともなく参戦し、その武で猛威を振るったことからついたあだ名が「秦の怪鳥」。個人的武勇と戦場全体を見渡せる知略の双方を兼ね備える、最強の六大将軍。その首を取れば50の城をとるよりも価値がある、生きる伝説等敵味方問わずその評価は高い。また六将・摎の出生の秘密を知る一人であり、同時に、摎の想われ人でもあった。
さて実際は?
“王 齮(おう き、? - 紀元前244年)は、中国戦国時代の秦の将軍。同じ秦の将軍、王齕との同一人物説がある[1]。”
出典
王キ - Wikipedia
なんと!!
六大将軍のうちの王騎と王齕が同一人物の可能性がある!?
“紀元前257年(昭襄王50年)、趙の邯鄲を包囲した
紀元前247年(荘襄王3年)、韓の上党を攻めて、太原郡をおいた。
紀元前246年(秦始皇元年)、秦王政が即位すると、蒙驁、麃公らと共に将軍に任じられる[2]。
紀元前244年(秦始皇三年)、同僚の蒙驁が韓を攻め十三城を取るも、同年に死没[3]。”
出典
王キ - Wikipedia
史実では秦王政の即位の際の将軍任命のようです。そうすると昭王からの伝言、というのもオリジナルストーリーになりますね。
“なお、『史記』の「秦本紀」に登場し長平の戦いなどで活躍した将軍王齕は「秦始皇本紀」では一切触れられず、逆に「秦始皇本紀」で初めて現れる王齮は「秦本紀」には登場しない。遅くとも南朝宋代には王齕と同一人物である可能性が論じられており、裴駰の『史記集解』は徐広の説を引いて、「齮」字について「一に齕に作る」と述べている[1]。”
出典
王キ - Wikipedia
■王翦
出典
plus.himote.in
蒙驁軍の副将。王賁の父親で王一族の現頭首。桓騎と同じく化物と評される。
恐ろしい形相を模した鎧に身を包み、目元を隠す仮面を付け、部下すらも味方に向けるものではない目で見る。秦国一の危険人物とされ、昭王の時代からずっと日陰に送られている。その理由として自らが王になりたいという野望を抱えているという噂があり、実際自分の領地を国と表現し、敵将である姜燕を執拗に勧誘した。
自分が王になりたい、という野望で「危険人物」視されていた王翦ですが
さて実際は?
“始皇帝は李信に問うた。
「私は荊を攻め取りたいのだが、将軍はどのくらいの兵が必要だと思うか?」
李信は答えていった。
「二十万もあれば十分でしょう」
始皇帝は王翦にも問うた。
王翦が答えるには「どうしても六十万は必要です」とのこと。”
出典
王翦列伝
王翦を語るに有名な話。ここで李信が勢いのある将軍として逸話の引き立て役になっています。また王翦の政治感覚を現す逸話として続く話も有名です。
“こうして王翦は六十万を率い、始皇帝は自ら灞上まで見送った。
王翦は出発にあたり、美しい田と宅、園池を得たいと繰り返し、請うた。
「将軍、行きたまえ、どうして貧乏を憂えることがあろうか?」
「大王の将軍たるものは、功があっても侯に封ぜられることはなく、なので大王が私に期待をかけられているこの機会に園地を賜り、子孫のためとしたいのです
これを聞いた始皇帝は大いに笑った。
王翦は函谷関に到着すると、使者を出し美田を請うことが五回にも及んだ。”
このように王翦は戦地から始皇帝にご褒美の確認を繰り返します。これにはわけがあったのです。
“ある者が見かねて言った。
「将軍のおねだりは度が過ぎております」
「それは違う。
秦王は粗暴で人を信じない。
今、私が秦の全兵力を率いているので国は空だ。
田宅を請い子孫のために財産を残そうと見せかけねば、秦王に疑われた時、どうすればよいのだ?」”
あえてセコい小物と見せることで、始皇帝に反乱の疑念を抱かせない。その保身のバランス感覚が王翦を大将軍にしたてあげました。
始皇帝を手玉に取る、老獪な将軍だったようです。
出典
blog.livedoor.jp
東周英雄伝より
別の歴史漫画「東周英雄伝」の1ページですが、史実の王翦はこういう好々爺の方がイメージとしては近いのかもしれません。
ちなみにもう一人の登場人物は李信です。
■騰
出典
atsutomo.blog.jp
王騎軍の副官。将軍に進む。常に王騎の傍に控えており、普段は飄々としてポーカーフェイスを崩さない。また王騎へ答える時は「ハ。○○です」と答えることが多い。
飄々としたキャラの騰。劇中での容貌もどこか西洋風でこれもオリジナルキャラかと思いましたが・・・?
さて実際は?
内史 騰(ないし とう、生没年不詳)は、中国戦国時代の秦の将軍。内史は官名であるが、姓氏は不明であり、内史騰とのみ呼ばれる。
実在したーーー!
“紀元前231年、秦が韓より南陽の地を譲られると、騰は仮の守となる。
紀元前230年、韓を討ち、韓王安を虜にし、韓を滅ぼした。
なお、雲夢睡虎地秦簡では『語書』に南郡の郡守としてその名が見える。”
史記にも記載されているかなり信ぴょう性の高い情報のようです。
それも最前線に配置されて任務を全うするなど、能力はかなり高い!?
■壁(へき)
出典
daruyanagi.jp
昌文君の副官。王騎を初めとして多くの人から「生真面目」と評される。名家の生まれだが気取らない性格で、信の兄貴分でもある。
王都奪還の際に自らの無力さを痛感し、武官の極みである大将軍を目指すことを誓い、秦王派(昌文君派)武官の筆頭的な存在となる。登場時は将軍としての力量はまだ発展途上であったが、王騎には秦王派を引っ張っていく存在としてその可能性を認められていた。
シリーズの最初から登場し、ついに将軍となった壁。討伐軍総大将にまで推される実力者に。
けれど史実での存在は物語の中の活躍とはうらはらに、かなりあやふや・・・
“物語の下書きとなっている史記において反乱鎮圧のくだりで「将軍壁死(将軍の壁が死んだ)」とある。ここで死ぬために壁というキャラクターが生まれたが、後に誤訳の説が浮上した(壁死とは城内で戦死することを記す)ため、史実上の死を回避してしまったと作者は苦笑まじりにつづっている。”
出典
キングダム (漫画) - Wikipedia
!!!誤訳で生まれたオリジナルキャラ!?
“成蟜叛乱のときに将軍が死んだとの記述がありますが、「将軍壁が死んだ」、「将軍が壁死した(城内で死んだ)」と二通りの解釈があるようです。しかし後者の解釈は、どの将軍が死んだのか不明だし、壁死という死に方をわざわざ書く必要があるのかも疑問です。”
出典
中国歴史小説「李信伝異聞」 壁将軍は存在したのか?
「将軍壁死」の記述について、こういう説もあります。
また、オリジナルキャラゆえに、そのキャラが将軍になる、という点も波紋を呼んでいます。
キングダム大好きな人にしかわからない内容でした。雨に打たれ濡れたまま電車に乗りながら何を書こうか考えたのがコレでした(笑)
ということで、
やっぱり濡れたっけ寒いわ(笑)
周りみんな長袖やコートだし。
以上です。