こんな新しくて刺激的な本を図書館から借りてきた。![]()
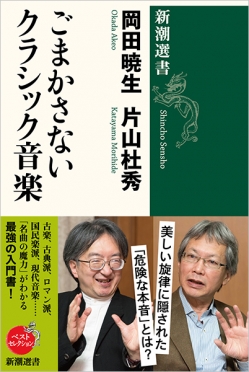
![]() 岡田暁生 片山杜秀「ごまかさないクラシック音楽」(新潮社 2023)
岡田暁生 片山杜秀「ごまかさないクラシック音楽」(新潮社 2023)
<目次>
はじめに――岡田暁生
序章 バッハ以前の一千年はどこに行ったのか
「クラシック音楽」とは何なのか/冷めた目で音楽史を眺める/世界市民化プロジェクト/クラシックと帝国主義/「バッハ以前」のほうがいい?/環境化する音楽/「ECM」レーベルが象徴するもの
第一章 バッハは「音楽の父」か
「神に奉納される音楽」/「表現する音楽」の始まり/音楽の自由と検閲/なぜバッハは「音楽の父」になった?/バッハと靖國神社?/バッハと占星術?/バッハとプロテスタント/《マタイ受難曲》の異様さ/恐るべし、音楽布教/バッハの本質は「コンポジション」/バッハは「おもしろい」vsショパンは「好き」/グールドと《ゴルトベルク変奏曲》/グールドとランダム再生/ポスト・モダンを先取りしていたバッハ?/『惑星ソラリス』におけるバッハ/バッハが辿り着いた「超近代」
第二章 ウィーン古典派と音楽の近代 ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン
1.ハイドン
エステルハージ時代のハイドン/ハイドンのロンドン旅行/クラシック音楽における「イギリス趣味」/イギリスとロシアの共通分母/イギリス人の合唱好き/《God Save the King/Queen》と《ラ・マルセイエーズ》/音楽と金づる/イギリス人の作曲家たち
2.モーツァルト
モーツァルトの浮遊感と根無し草/「核家族」で育ったモーツァルト/小林秀雄の『モオツァルト』
3.ベートーヴェン
天才とバカのあいだ?/ガサツな田舎者?/「ベートーヴェン株式会社」の創業社長/ベートーヴェンと世界平和を祈る音楽/中国で《第九》が禁止?/ベートーヴェンと右肩上がりの時代の音楽/それでもやっぱりベートーヴェンはすごい……/「坂の上の雲」とベートーヴェン/ベートーヴェンと人類の終わり/映画におけるベートーヴェン/『時計じかけのオレンジ』のベートーヴェン/ポスト・ベートーヴェン/年末に《第九》の代わりに何を聴くか
第三章 ロマン派というブラックホール
1.ロマン派とは何か
ロマン派は一括りにできるのか/ロマン派の世代整理/ベートーヴェンはロマン派の開祖なのか/ベルリオーズと吹奏楽/ロマン派と軍隊音楽/観光音楽としてのロマン派/コンサートホールの登場/インテリのための室内楽?/音楽批評の誕生
2.ロマン派と「近代」
ロマン派と「愛」/ロマンチック・ラブは資本主義が生んだ/「女・子ども」で成功したショパン/「人間は三分間しか音楽を聴けない」/ロマン派と制限選挙の時代/哀しき「民族派」の宿命/ロシア五人組のエキゾチシズム/帝国主義と民族派/フランスの民族派?
3.ワーグナーのどこがすごいのか
ワーグナーの「三時間文化」/ワーグナーとエクスタシー/ワーグナーとマイアベーアの違い/SPからLPへ/ワーグナーのアンチグローバリズム/ワーグナーのすごさ/《指環》と『資本論』/ワーグナーとYouTube/ポスト・ワーグナーの戦略/「壊れて」いくロマン派/マーラーとサブカル?/遅ればせながらブルックナーについて
第四章 クラシック音楽の終焉?
1.第二次世界大戦までのクラシック音楽
「西洋音楽史」の見直し/「ユーラシア」の視点から考える/ユダヤ系アメリカ移民の「芸」/ネフスキーとプーチン/「西欧的価値」へのルサンチマン?/第一次世界大戦と「クラシックの時代」の終焉/《春の祭典》とともに第一次世界大戦は始まっていた?/民族派のチャンスとバルトーク/交響曲の終わり/ショスタコーヴィチと全体主義/ロシア音楽とミリタリー/ロシアとアメリカ/東欧ユダヤ系移民がつくったアメリカ音楽?/一九二〇年代とジャズ・エイジ
2.第二次世界大戦後のクラシック音楽
アヴァンギャルドの時代/前衛芸術家がスターだった頃/シンセサイザーの登場/「砂の器」の前衛音楽批判/前衛音楽家たちの戦争体験/自由主義vs社会主義/体制側で生き抜いたフレンニコフ/これがソ連全体主義的名曲だ!?/社会主義的リアリズムは「無葛藤」/ショスタコーヴィチの「殲滅と死」の音楽/前衛の斜陽とミニマル・ミュージック/不毛の三〇年?/ビッグネームの消滅とゾンビ化/アヴァンギャルドは「現実のカタストロフへの前座」?/ミニマル・ミュージックと古楽の先はあるのか/ストリーミング配信で変わったこと/これからのクラシック音楽をどう聴くか/ ベートーヴェン《第九》vsショスタコーヴィチ《第五》
おわりに――片山杜秀
人名索引
岡田暁生(1960- ) 片山杜秀(1963- )
![]() バッハ以前はなぜ「クラシック」ではないのか? ハイドンが学んだ「イギリス趣味」とは何か? モーツァルトが20世紀を先取りできた理由とは? ベートーヴェンは「株式会社の創業社長」? ショパンの「3分間」もワーグナーの「3時間」も根は同じ? 古楽から現代音楽まで、「名曲の魔力」を学び直せる最強の入門書。
バッハ以前はなぜ「クラシック」ではないのか? ハイドンが学んだ「イギリス趣味」とは何か? モーツァルトが20世紀を先取りできた理由とは? ベートーヴェンは「株式会社の創業社長」? ショパンの「3分間」もワーグナーの「3時間」も根は同じ? 古楽から現代音楽まで、「名曲の魔力」を学び直せる最強の入門書。
今の日本クラシック音楽界の評論を牽引している碩学二人の対談は、どこを読んでも興味深いなあ。
![]()
引用したい部分は数多あれど、こんな文章が目に留まった。
片山 そういえば「精神分析医」なんて職業も、この時代のウィーンで登場した専門業の一つですよね。
それまでは、何か自分では解決できない悩みがあったら、地元の教会の懺悔室に行って神父さまや牧師さまに懺悔して悩みを聞いてもらっていた。ところが、都市化が進むと、大都市には各地から人々が寄り集まってくるから、地元の教会との縁も切れて、どの神父さまか牧師さんに懺悔していいかわからなくなってくる。しかも、その頃には教会の権威も落ちてきて、いつまでも神さまを信じているようでは、個人も社会も立ち行かないという雰囲気になってくる。そこへ精神分析医が出てきて、マーラーのようにフロイトのところに通って精神分析してもらうような作曲家もあらわれた。
岡田 「私の心」のコンサルタント業ですね。「私」を分析批評してくれる。社会の中でのポジション取りが音楽批評と似ている。「ワタシってなあに? センセイ、教えてください」 ----- これが精神分析の顧客だとすると、「センセイ、僕はどうして昨日のコンサートに感動したんでしょう? 教えてください」が音楽批評の顧客(笑)・・・(p.174)
もともと代言人と呼ばれていた弁護士(当時は詐欺師と紙一重だった)が、口喧嘩の代行をして裁判に臨むというところから地位が上がってきたのだった。![]()
現代社会では、弁護士も精神分析医も、はたまた音楽批評家もそれなりのステイタスを得て久しいけど、元はと言えば、そんな経緯があったのだ。批評家の先鞭をつけたハンスリックは弁護士から音楽批評家になったのだった。
(次回に続く)