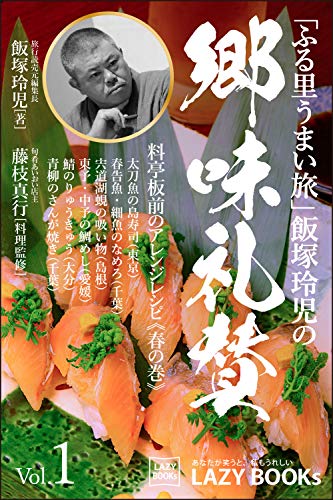江戸時代の貨幣価値はかなり大幅に変動があったらしい。
俗に「二八蕎麦」は「そば粉8割、繋ぎ2割」という意味のほか
2*8=16文で、かけ蕎麦が味わえたからという話もある。
これを基にして考えると、2009年の都市部のかけ蕎麦の金額が
520円だそうで、これが16文だとすると1文は現在の32円50銭
ということになる。幕末の頃は貨幣価値の変動があって、1867
年には、かけ蕎麦1杯が22文だったそうだ。
すると1文は約24円となる。
で、一両はいくらかというと1867年の相場で一両=約8300文
くらいだったようである。すると、現在の価値にすると一両=
約19万9200円というわけだ。
と考えると町民から「サンピン」と言われた「3両一人扶持」
(一人扶持は1年約5俵)の貧乏御家人では、年収は米5俵+
現在の金額で60万円以下ということになる。
なるほど、これは極貧であるな。
鬼平犯科帳などで、密偵などが煮売屋にお金を支払って、店員が
「まあ、2朱も!」と驚く下りがよく出てくるが、1朱は一両の
16分の1で、金でも銀でも16朱=一両だったようだ。
すると、さっきの計算でいけば、2朱は19万9200円の8分の1
ということで、2万4900円ということになる。
1朱はその半分だから、1万2450円ということである。
本当にこんなに支払ったのだろうか。
もっとも、幕末も最後の方になると貨幣価値もこの10分の1
くらいまで下がったとも聞いている。
なかなか、江戸時代の貨幣価値を肌感覚で掴むのは難しい。