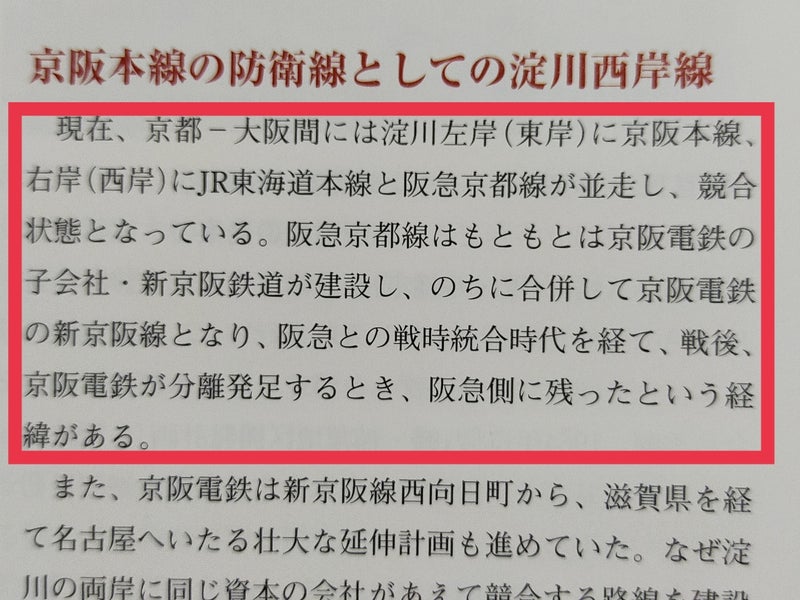みなさんこんにちは。前回からの続きです。
府南部、和泉市(いずみし)の「弥生文化博物館」で、今年3月まで開催されていた「泉州を貫く軌跡 阪和電鉄全通90周年」という特別展の訪問記を、引き続いてお送りしています。
シリーズのまとめに入っております。
現在の「JR阪和線」を建設した「阪和電気鉄道」。1940(昭和15)年12月、国の強い意向を受け「阪和電気鉄道」は現在に至るまでのライバル「南海鉄道(現在の南海電車)」に吸収合併されることになります。
1929(昭和4)年に最初の区間の開業にこぎつけてから、わずか11年後のこと…というところについて、前回の記事まで述べました。
引き続き、南海に吸収合併され、同社の「山手線(やまのてせん)」となった後の展開について、フリー百科事典「Wikipedia#阪和電気鉄道」から拾って参ります。南海との合併だけでは、ついに事が収まりませんでした。
両社の合併と「鉄道省紀勢西線(現在のJR紀勢本線)」への直通運転について述べた記事から。
「阪和線を南紀への直通線として列車を乗入れ天王寺から直通列車を運転する方針に決定」…と、右下にくだり。
「大阪朝日新聞」昭和15年7月17日付けより。
…紀勢西線の全通により鉄道省では大阪、熊野路の直通運転を実現すべく研究した結果、南海、阪和両社の合併に乗り出した。
国鉄としてはかねてから阪和を買収すべく陰に陽に保護を加え(中略)大蔵省が起債を許さないためついに南海と一応合併せしめ、阪和線を南紀への直通線として列車を乗入れ天王寺から直通列車を運転する方針に決定したもの…
つまり表面上では、経営難に陥っていた阪和を南海が救済する目的で吸収合併した、ということにはなっているものの、実際は「阪和電気鉄道を国有化する(→国有鉄道として大阪・和歌山間の直結ルートを確保するとともに、和歌山駅が北端だった紀勢西線とそれをつなげ、大都市・大阪へ独自の路線網を持ちたかった)」という目論見が、最終的な目的であったことが記事から窺えます。出典①。
この「鉄道路線網の国有化、一元化」という動きは、世界大戦へ突き進む当時の国の方針でもあり、ある法令に拠るものが大でした。
両社を合併させることで紀勢西線への直通列車に関するダイヤ改正交渉を一元化できる鉄道省や、1938年に公布された「陸上交通事業調整法」に基いて過度な競争を抑えて軍事輸送を強化したい国の意向によるものであった…とWikiは続きます。
本来であれば、鉄道事業のみならず、競合する相手が存在することで、その分野の寡占、独占というものは阻まれます。市場原理としては、今日の我が国では極めて健全で、当然の考え方ですが、その「陸上交通事業調整法」なるものはまったく逆の効果を企図したものでした。
同一事業を営む事業者を可能な限り合併させることで競争原理を失わせ、国の意向に従い易くさせる(交通事業者に対しては、窓口がまとまっていると戦時中、軍事輸送を最優先させるための命令がし易くなる)という、極めて歪な法令でした。出典②。
戦前、京阪資本が開業させた「新京阪鉄道」。鉄道省車両をはるかに凌ぐ、高速運転が可能な高性能車両「P-6(デイ100形)」を投入。
同じく、京阪が資本参加した「阪和電気鉄道」の直線を追求した高速走行可能な線形、高性能車両もこれに通じるものがあった。出典③。
この法令により、関西では「京阪電車+阪神急行電鉄(阪急)=京阪神急行電鉄」や「大阪電気軌道(大軌)+参宮急行電鉄など=関西急行電鉄(現在の近鉄)」が成立。
関東ではさらに大規模な鉄道事業者の合併により、いわゆる「大東急(現在の東京急行・京浜急行・京王・小田急・相模鉄道などによる)」が設立されました。余談でした。出典同。
ただ、そうなるとなぜ「阪和電気鉄道」を直接、国が引き取るのではなく、一時、南海に吸収合併させたのか、という疑問が残ります。
これについては…
この時、国としては阪和電鉄買収の意思もあったが、1940年の時点(南海による阪和の吸収合併時)では実現しなかった。
阪和電鉄線は高規格であるため、買収費用が高額となることが予想された。
また当時日中戦争の戦費確保が優先されていたために、買収資金調達のための国債発行も困難であった。このような事情から買収が見送られ、代わりに南海への合併という形で当座の措置としたと言われる。
実際は、この解説に尽きるようです。
国家予算が軍事費に最優先される中では、適正価格での買収という観点は、国にはもはや眼中になかったようです。
そこで、まず阪和を合併させた後、国が南海に持ち出して来たのは「戦時買収」という手段でした。こちらについても、フリー百科事典「Wikipedia#戦時買収私鉄」より。
「改正陸運統制令(先述の「陸上交通事業調整法」よりさらに強力に交通事業をまとめようと公布された法令)」に基づく戦時買収は、大東亜戦争(太平洋戦争)完遂のための軍事目的を前面に押し出したもので、当時の国家総動員法などに基く強制的なものであった。
その方法は、突然買収対象となった私鉄会社の関係者が電報一本で呼び出され、行った先で有無を言わせず書類に押印を強要するといったもので、押さなければ「非国民」扱いされるために、従わざるを得なかったというものである。
買収代金の支払いは戦時公債によって行われたため、実質的には換金不可能であった。また、買収路線は戦争終了後には(建前では)元の会社に戻す事が条件づけられていたため、会社を解散する事は禁止されていた。
そういったことで、世界大戦を完遂しようという当時の国策にはどうにも抗えない、という構図に持ち込まれました。出典②。
ちなみに、南海と阪和以外の例で、この法令によって国に強制買収された私鉄としては「宮城電気鉄道(宮電)」、現在の「JR東日本 仙石線(せんせきせん)」も知られています。
仙台周辺のJR線があまねく交流電化なのに対し「仙石線」だけが直流電化なのは、買収されたかつての宮電が電化私鉄の主力だった直流方式で開業したためです。余談でした。
石巻(宮城県石巻市)にて、2016(平成28)年撮影。
そして、1941(昭和16)年12月8日、帝国陸海空は、アメリカ・イギリスと全面的な戦争に突入しました。いわゆる「アジア・太平洋戦争」です。国内はすべてが戦争に向けられました。出典同。
本題に戻ります。
そして、古くから阪和間の独自ルートを希求していた鉄道省はこの時勢に乗じ、懸案であった南海山手線の買収を決定した。
南海からの反発も排され、山手線は1944年5月1日、戦時買収により国有化、国有鉄道阪和線(国鉄阪和線。現在のJR阪和線)となった。
南海への吸収合併からはわずか4年、戦乱の中「阪和電気鉄道」は「南海山手線」を経て「国鉄阪和線」となりました。
終戦の前年、1944(昭和19)年のことです。
(出典①「阪和電気鉄道 沿線御案内」阪和電気鉄道発行 昭和6年)
(出典②「新詳日本史図説」浜島書店編集部編・著 浜島書店発行 1991年11月)
(出典③「京阪百年のあゆみ」京阪電気鉄道株式会社編・刊 2010年)
次回に続きます。
今日はこんなところです。