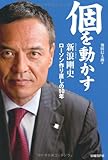』 財部誠一
本当は『個を動かす・・・』の方を読みたかったのですが、この本を読み終えてから、自分が本当に読みたかった本がこれでなかったということに気づきました(笑)
でも、せっかく読んだので、いい機会ので、今度『個を動かす・・・』も読んで、比べてみようかな。
話がそれてしまいましたが、この本は筆頭株主がダイエーから三菱商事に代わり、43歳だった新浪剛史氏が社長に就任してからのローソンについて書かれています。
コンビニと言えば、当然セブンイレブンがナンバー1であり、コンビニついて書くのであれば、わざわざナンバー2のローソンではなく、圧倒的ナンバー1のセブンイレブンに注目して書けばいいのですが、今回ローソンに着目した点について著者の財部さんはこう書かれています。
新浪の経営は有言実行で、たびたび失敗を繰り返し、それでもあきらめないものだから、最終的には結果がついてくる。トライ&エラーの果てに具体的な結果が出る事を目の前で見せてくれる面白さは、新浪ローソンの真骨頂だろう。
その新浪ローソンについてですが、一般の人の自分からみて気づいた部分としては、
・生鮮食品の展開
・Pontaカードの展開
・ローソンストア100
ということが挙げられますが、この点についてもしっかりと裏事情が書かれていますし、他にもセブンイレブンとは違う展開を行っている点がしっかりと書かれています。
特に自分が気になった部分が、ローソンはMO(マネジメントオーナー)制度を導入し、本部での加盟店管理を減らしているということ。
ローソンがオーナーの店舗運営を支援する人材を抱えるのではなく、MOという経営のプロを育成することを通じて人件費を削減し、利益率の向上を目指すと言う。
これって、マクドナルドが直営店比率を下げ、フランチャイズ店舗(フランチャイズオーナー)を増やしているのに似ているような・・・。
とにかくこれまでセブンイレブンが構築して来たコンビニエンスストアの仕組みを作り変えようとしている点は間違いありません。
セブンイレブンについて書かれた本を読んだ方は、ぜひこの本も読んで、同じコンビニでもやり方などが変わりつつあることを感じてみてください。
======================
目次
序章 新浪剛史から目が離せない
第1章 瞳輝き心も躍るイノベーション
第2章 ビッグデータの嘘と真
第3章 夢と野心のコラボレーション
第4章 苦悩と葛藤の人事ステーション
第5章 Good byeセブン‐イレブン
第6章 「まかせる」強さ
第7章 新浪剛史の“告白”
======================
セブンイレブンとファミリーマートは、働く独身女性や年配の夫婦をターゲットにしたお惣菜に力を入れた。他方、ローソンは生鮮食品だ。コンビニには野菜や果物などの生鮮食品はない、というのが従来の認識だった。生鮮食品はスーパーマーケットで買うという常識を覆し、女性やお年寄りのために小分けされた野菜や果物を新鮮な状態で取りそろえることで、ローソンは見事に女性客の比率を劇的に向上させた。
リピート率の高い商品を見つけたら勝ち
他社で売れたら、すぐに模倣する。それでコンビニ業界は伸びてきた。だがそんな幸福な時代はとうに過ぎ去り、今や目指すべきは他社が真似したくても容易に真似できない”模倣困難性”だ。
その雌雄を分けるのは、ビックデータの中から有益な仮説を抽出し、加盟店に高いレベルの実践を施し、模倣困難な商品群でどれだけ店舗の棚を埋められるかにかかっている。
新浪が来て、この縦型組織を一気に横型に革新した。地域単位で完結できる組織、現在の支社制です。
セブンイレブンは10店舗行くと8、9店舗で私は買いたいおにぎりや総菜が並んでいる。ところがローソンだと10店舗中、 4 、 5 店ぐらいしか十分な商品陳列量はないというのが私の印象です。お客様視点で考えた品揃えがどこまでできているか。セブンイレブンとローソンは、その徹底力が違うのです。
「そこに、みんなを思いやる気持ちはありますか」
「そこに、今までにない発想や行動のチャレンジはありますか」
「そこに、なんとしても目標を達成するこだわりはありますか」
(ローソンの行動指針)
新浪はまるで口癖のように「まかせる」を連発する。これはと思った人物には徹底的に「まかせる」 。ただし権限は責任を伴う。任せて失敗すれば降格する。ただし、降格を致命傷にはしない。再起を促し、期待に応えれば、復活できる。厳格な「責任と権限」の大原則を貫いてきた。