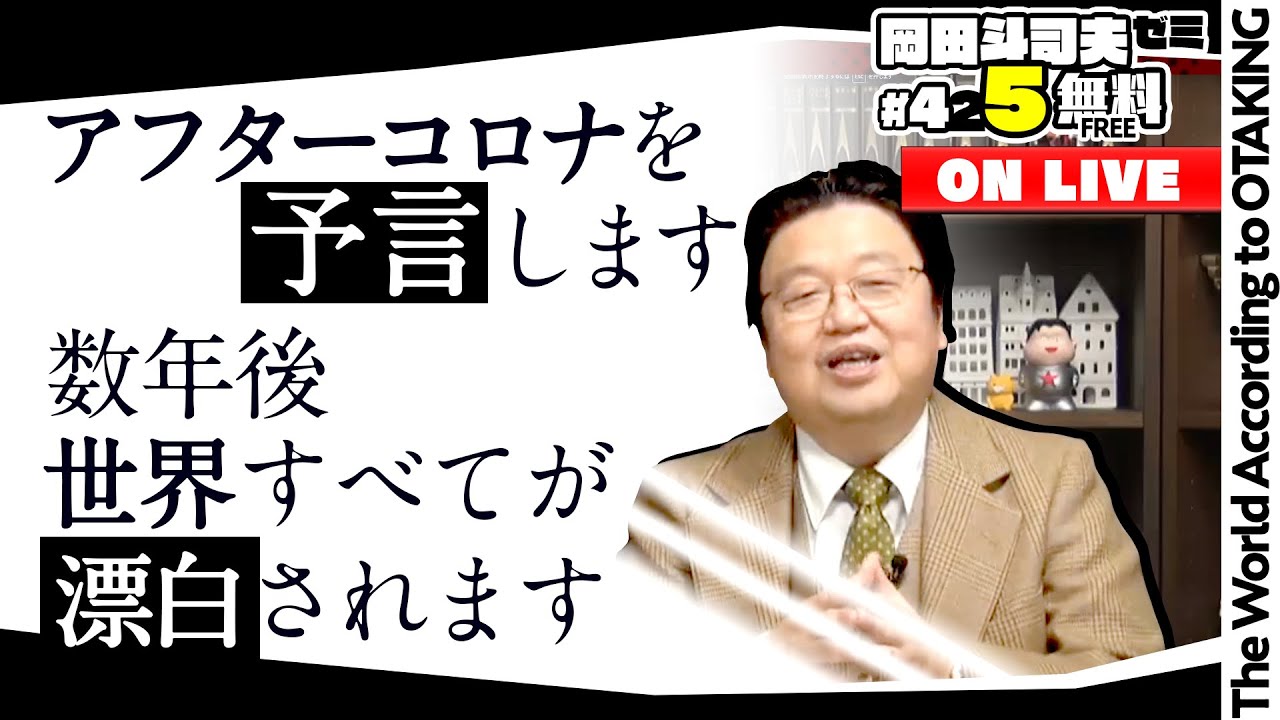医療職に限らず、援助職は、
けっこうイライラする場面が多いのではないかと思います。
そもそも、人間にとって(人間である限り)怒りは避けられません。
世の中、ずっと自分の思うとおりにいくことは無いからです。
思い通りにいかないことは、特に対人関係において多いため、
人を相手にする仕事では、イライラする気持ちと以下に向き合うか、
アンガーマネジメントは必須ではないでしょうか。
さらに、対人関係というだけでなく、
援助職は、さらに怒りが生じやすい気がしています。
援助は、
「相手にこうなってほしい、こうなったらきっと喜んでもらえるはず」
という動機から始まります。
その通りに相手が喜んでくださればいいのですが、
必ずしもそうならないのが、世の常です。
話を聴いてほしいのかなと思って話しかけたら、そうっとしておいてくれと言われたり、
今はそうっとしておいてほしいのかなと思いきや、なんで放っておくんだ、全然話も聞いてくれない、とすれ違ったり。
小さな親切が、大きなお世話になってしまうこともあり、
何が相手の望みなのかを100%予測できるはずもなく、難しい場面は多々あります。
「こうじゃない、そうでもない、どうしてもらいたいのか自分でもわからないけど、とにかくつらい。。。」
そんな訴えも珍しくありません。
しかし、よくよく考えれば、
人はそれぞれ、経験も能力も性格も体調も、全く同じではありえず、千差万別、億差兆別。
怒りの心は、「普通はこうでしょ(こうすればラクになるはず)」という自分の基準で、
相手を推し量ろうとするところから出ていると言われます。
まずは、「相手のため」と思いながらも、
つい「自分なりの善意」の押し付けになっていなかったかを反省するところから始めねばと思います。
そして、訴えが多いのは「自分を困らせようとしてのことではない」という確認も意外と有用です。
いわゆる
「困った人は、困っている人」とみることです。
「自分を困らせようとしている、困った人」と相手をみてしまうと、怒りの心が燃え上がりますが、
「困っているが故の訴えなんだよな」と思い直すと、怒りの心は静まり、優しくありたい自分がよみがえってきます。
「なぜ生きる」という座右の書に、
「善いことをすると腹が立つ」という章があります。
親切心のウラに、見返りを待つ心が見え隠れするいやらしさを「雑毒の善」と表現されています。
よいと思って努めているのに、相手が”ほめもせず””感謝もしない”ととたんに腹が立つ。
「あんなにしてやったのに」「これだけしてやっているのに」
「してやっている」の恩着せ心の思惑が外れると、二度とやるまいと決意する。そういえば偽善者とは、「人の為といって善をする者」と書いてあるのに感心する。
受けるよりも、与えるよろこびを知ってはいるが、「与えた」という意識が離れ切れない。千円与えた礼を聞けないよりも、一万円の時が不愉快だ。一万円よりも十万円、十万よりも百万ともなれば後悔どころではすまないだろう。
大善ほど猛毒を含む人間の善の実態を、龍樹菩薩はこう道破する。
「四十里四方の池に張りつめた氷の上に、二升や三升の熱湯をかけても、翌日そこは、ふくれ上がっている」(大智度論)
しかしここで、こんな誤解に答えておかねばならないだろう。
それでは冷淡な人間であってもよいのか。ものをあわれむ心は要らないのか。善に向かう姿勢を嫌うのか。放逸に油を注ぐことにはならないか。
もちろんそれは逆である。
逆境の人をあわれみ悲しんで、ふと気がつくと”慈悲深い我”と得意になっている醜さに驚くのは、心から善に向かった者だけだ。真の善人になろうと努めるほど「悪性さらにやめがたし」と悪性の根の深さを知り「これではいけない」と反省し努力せずにおれなくなる。
怒りの心と向き合うことは、自分の心と向き合うことです。
良かれと思ってやったのに、相手に拒否されてしまうと、
ついつい怒りの心で「全部やめた」と投げ出したくなりますが、
そこでグッとこらえて色々考えてみると、今まで気づかなかったような自分の心が照らし出されます。
援助を通して、自分自身と向き合う機会にしていきたいと思います。
関連記事: