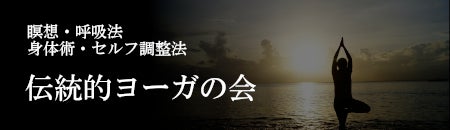「腰や痛い…」「喉が違和感…」
季節の変わり目は、不調が出やすかったりしますよね。
でも、不調が出るというのは、
自分の内側から出る「切り替わりのサイン」
でもありますね。
私は、生徒さんから不調の相談を受けると、
具体的な調整法も紹介しますが
「この症状を出すことで、自身は何に気づきたかったのか」
(この症状を、自分はどうして必要としたのか?)
といった、内面の自己探求を、
一緒に確認することがあります。
『どんな経験も、自分をより自由に、
実現したいものを実現してくプロセス』
症状は出ない方がいい、
とする前に、
症状のおかげで生まれる自己実現がある。
そう思うとき、
私は主に、4つの質問を大事にしています。
~~~~~
①「症状が出たきっかけって、何だと思う?」
思い返すと
「どんな行為から、この不調が出たか」
きっかけってありますよね。
その行為がいけない、
と言いたいのではなく、
「本来、こんな症状を出すはずじゃなかったのに、
出すことになった」
この事実を、受け止めたいのです。
自分にとってそのつもりがなくても、
症状を起こすだけの
「負荷(無理しているもの)」
が、そこにはあった。
肉体的な負荷だけでなく、
心理的な負荷があるからこそ、
症状が出ると思わなかったのに、出た、
とも言えそうです。
(先日、肩を痛めた方は
『実家の庭木の切り落とし』とおっしゃってました)
もちろん、きっかけがよくわからない、
というのもあるでしょう。
「わからない」という答えも
実は、自分が抱えている負荷の
在り様を示しているような気がします。
そこで、負荷の真相に迫るのが次の質問。
~~~~~
②「それをやったとき、自分の中に、なにか執着や自己防御、
本当はこうしたいのにできない…みたいな葛藤はあった?」
面白いもので、最初は「特にない…」と言っていても、
よく話していると、何かしら出てきます。笑
自分の心の中にある
「何か」を受け止めるために、
症状を出して、立ち止まらせる。
そういうことは、よくあるものです。
ヨーガ思想で言えば
「自分で自分の可能性を制限しているもの」
これに気づきたい。
(これを『煩悩』と言います)
自分で自分を縛っているものに気づかないと
解放もできません。
症状はそれに気づくための、
立ち止まる時間をくれたりしますね。
ちゃんと受容できれば、解放のヒントも見つかりやすいです。
「自分はどうありたいのか」
結局は、ここに尽きると思います。
自分が自分の本意に気づくと、意外と
「ああ、これに気づくために
症状を出して、立ち止まったのかも…」
と、素直に感じられたりします。
ただ、これを明確にするには、次の質問も有効です。
~~~~~
③「この症状のせいで、
できなくなったことがいくつかあったはず。
やらないことで『ほっとしたり、楽になった』ことってある?」
面白いもので、この質問に関しては、皆さん
ハッとした顔をして、あれがそうだった!と言います。
そうなんですよね。
症状を出すことで、やれなくなるものは、
深層心理が「やりたくないもの」だったりする。
もしくは、
「ほかのやりたいことを、
やれなくするような壁を作っていたもの」
でもある。
それまでの流れを止めた時
「本当はこうしたいんだ」
と、自分に必要なことが明確になります。
(前述の生徒さんは、
実家がらみで、自分がやらねばと思っていた、
親御さんのとあるお世話が、それにあたるようでした)
そして、最後の質問は…
~~~~~
④「不調になったことでやったこと、
もしくは、やってしまったことで、
何かよかったと思うことはある?」
これは、最初は
「生活リズムがよくなった」
「食生活が改善した」
が出たりしますが、
よくよく話すと、
「不調をきっかけに、何か失敗した、
予定どおりのことができず、
別のことせざるを得なくなった。
でも、それがかえってよかった」
といった、
面白い発見が見えてきたりもします。
表層では望んでいないと思っていても、
じつは、
新しい自分を体験するきっかけになったり、
自分が望んでいたものを知る
ヒントになったりします。
症状が出て、
できないことがあるからこそ
新しく与えられる経験がある。
あるがままを、まっさらに受け止めると
自分が望む、新しい方向性が見えてきそうです。
~~~~~
こうした自己対話ができてくると、
自ずと、
「自分は現状をこう変えたいんだな」
とわかってきます。
もっとも、ヨーガの体験をしている方のほうが
ひらめきは早い、と思います。
「経験のプロセス」を信頼しているからです。
『あるがままを観じれば(受容すれば)
調和へと向かう変化のプロセスは、必ず見える』
これが、伝統的ヨーガが
感覚を通じて身につける体験ですね。
体の不調は、一見、否定したくなる経験ですが、
それが起きる必然は、必ず、
「自分をより自由に、より豊かなものへと
変化させるために起こっている」
と信頼できます。
そして、目指す調和とは、
「全体にとって、無理がない、安らいだもの」
であり、
それが具体的にどういうことか、
直観的(感覚的)に見えてきます。
これぞ、伝統的ヨーガの智恵ですね!
そして、面白いもので、
ある程度、この症状の『意味』が
自分なりに納得できると、
不調は自然と回復することが多いです。
(私は「あ、これで治るな」
という手ごたえが、わりとあります)
もっとも
「もっと深く、自分が実現したいものを理解したい」
と深層が望めば、
その症状と、もうしばらくつきあうかもしれません。
結局は、
自分の深層とつながればつながるほど、
経験に無駄なものはなく、
すべてが、
「自分が必要とした経験にふさわしいことが起きている」
という実感になりそうです。
外と内の統合ですね。
(ヨーガとは「つながる」の意味)
もっとも、こういう境地、
私もヨーガモードなら、すぐに入れますが、
ちょっと自我モードが出ると、
「なんで、こんなこと起きるんだよ~」
と、振り回されます…笑
もっと、ヨーガに親しみたいところです笑。
最後に。
私自身も、先日「喉を痛めた」ことで
そのきっかけ、
その時の思い、
やらなくてほっとしたこと、
代わりに経験したこと
を受け止めました。
自分が何を望んでいるのか、
納得できるプロセスがありました。
「自分のヨーガライフを積極的に書こう」
と思った次第です。
今回、長い文章になったのも
そのせいだと思って、許してください。笑
長らくお休みだったツイッターも始めました。
(https://twitter.com/dentouyoga)
(いつまで続くか…と、危ぶむ皆さんの声も、聞こえそうですが…笑)
体の不調は、ある意味、
新しい自分の経験に開かれるチャンスですね。
不調を否定するよりも、
よき味方にして、人生のプロセスを観察したいものです。
それでは、皆さん、
ヨーガとともに、人生のプロセスを信頼し、
変化を愉しむ秋をお過ごしください!
~~~~~~

◆当会のHP◆
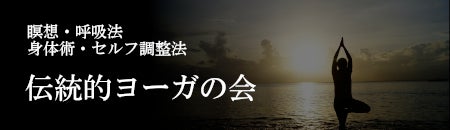



※体験レッスン受付中↑よりお申し込みください。
レッスン予約・お問合せもこちらからお願いします。