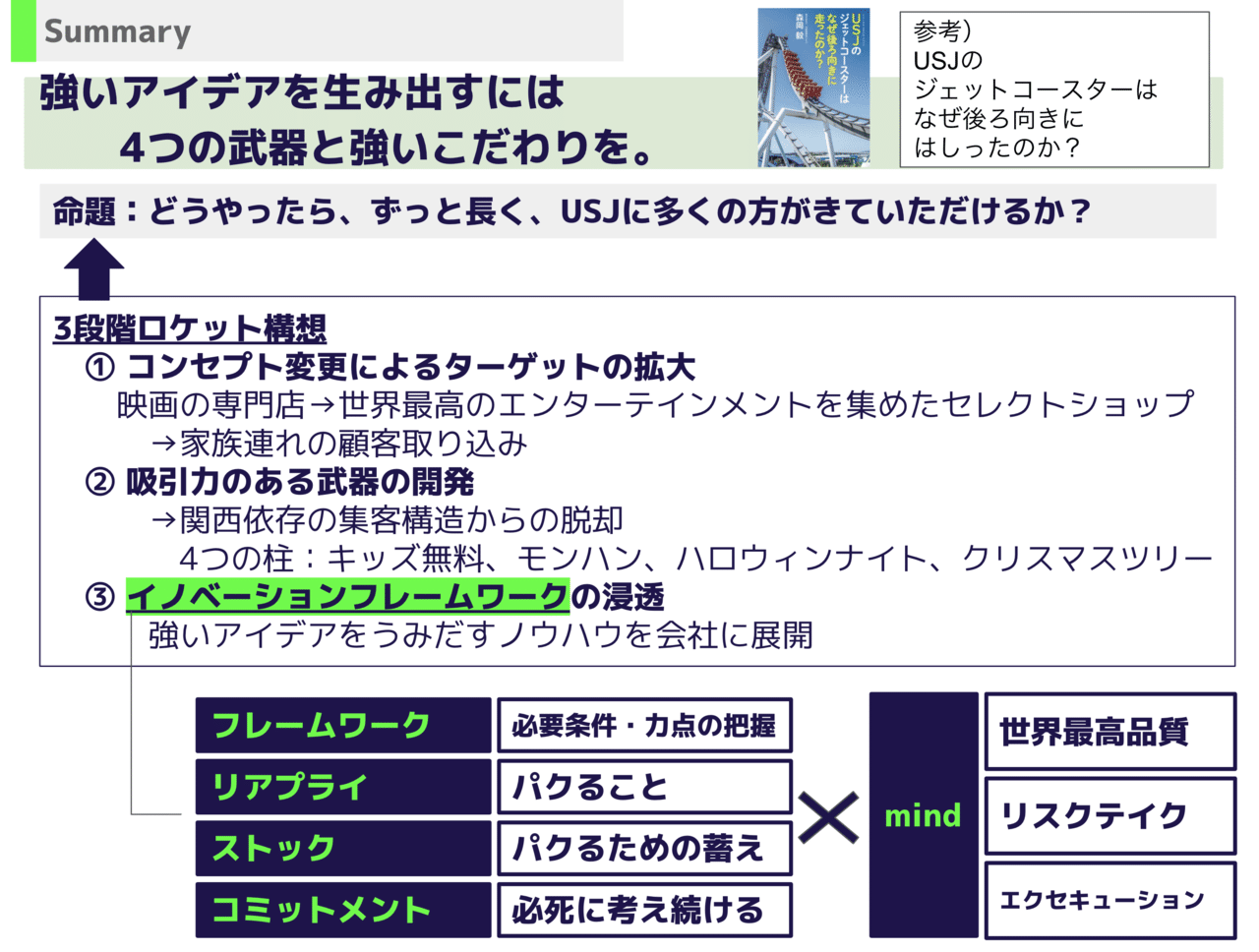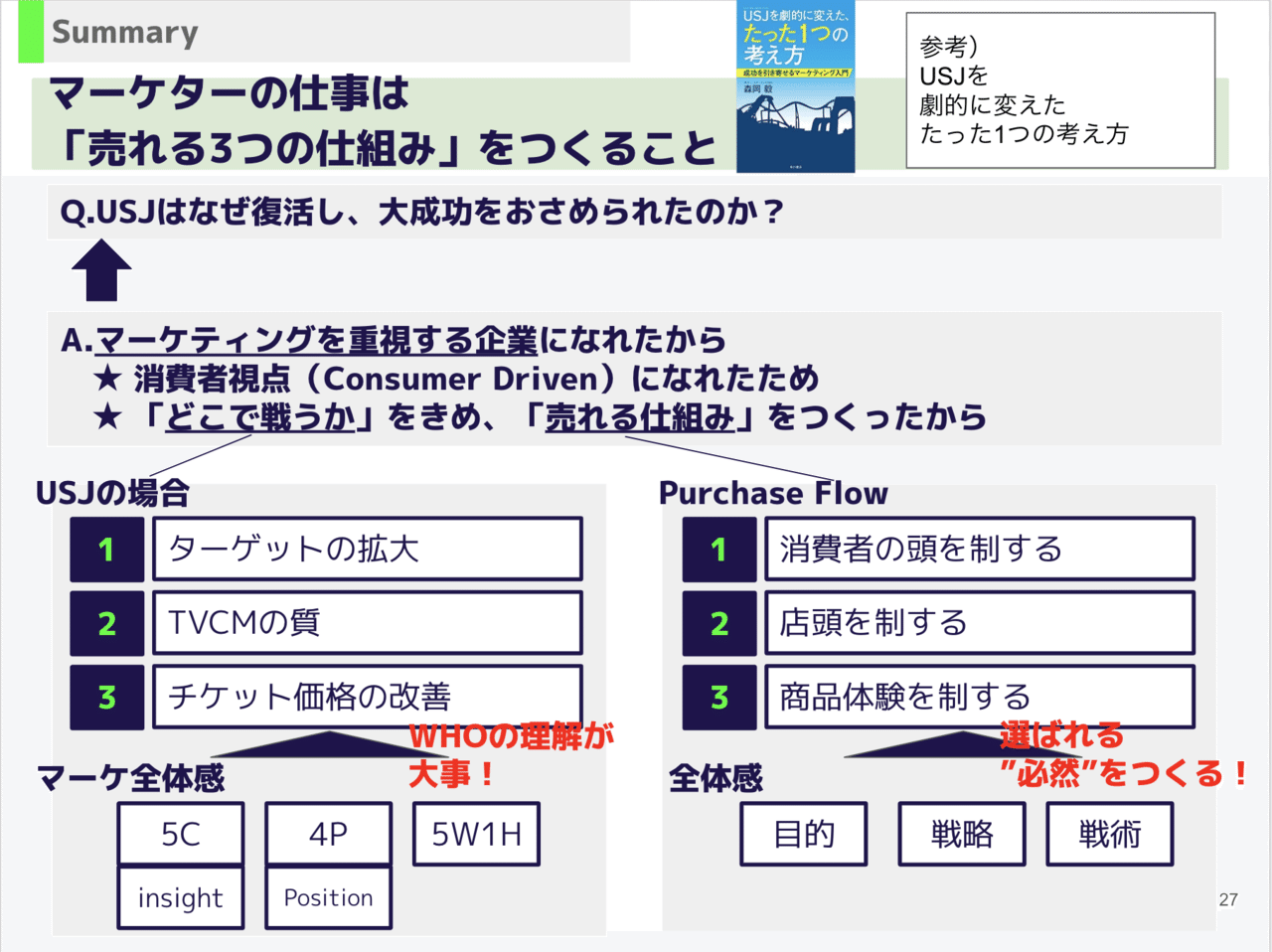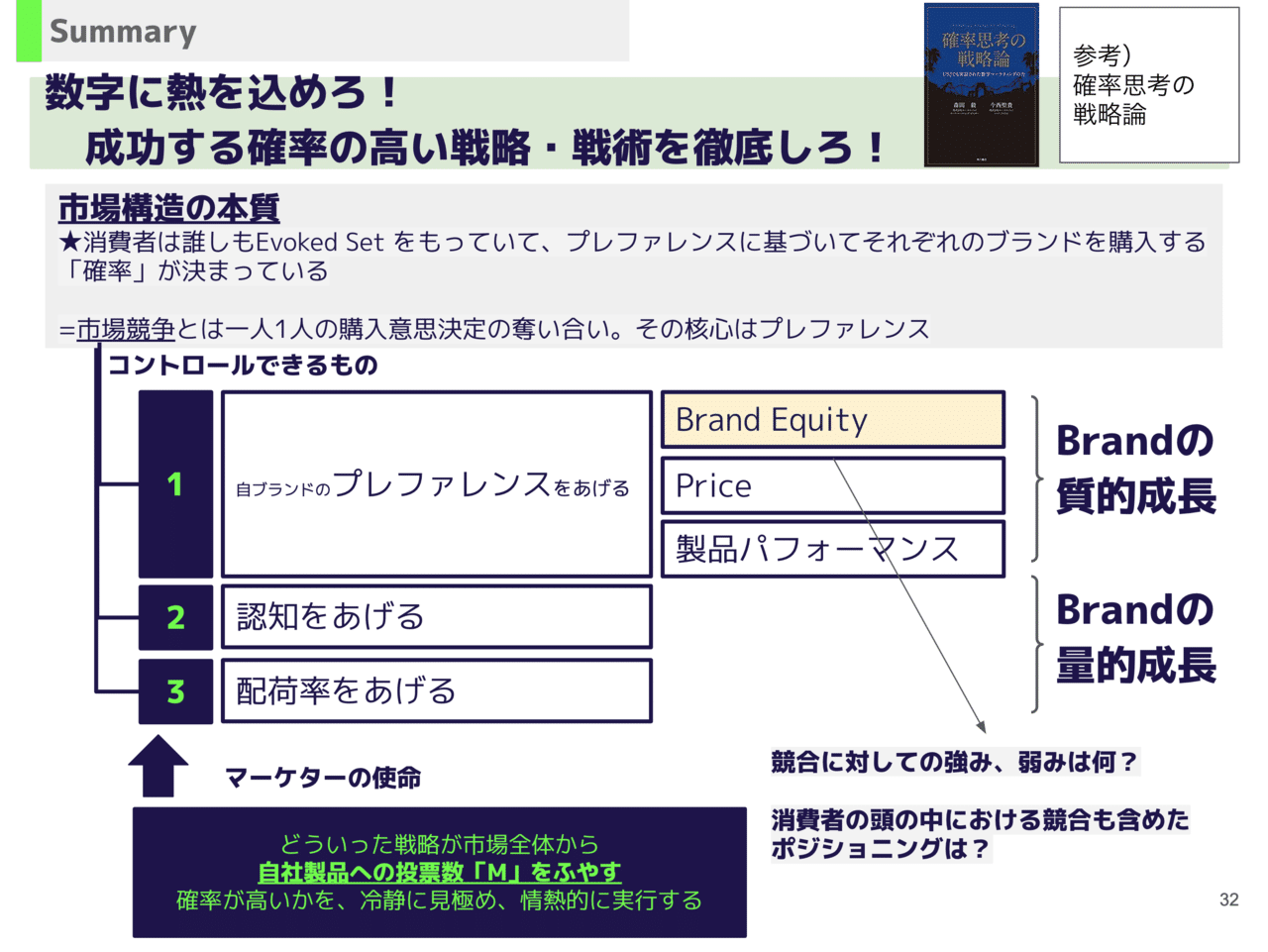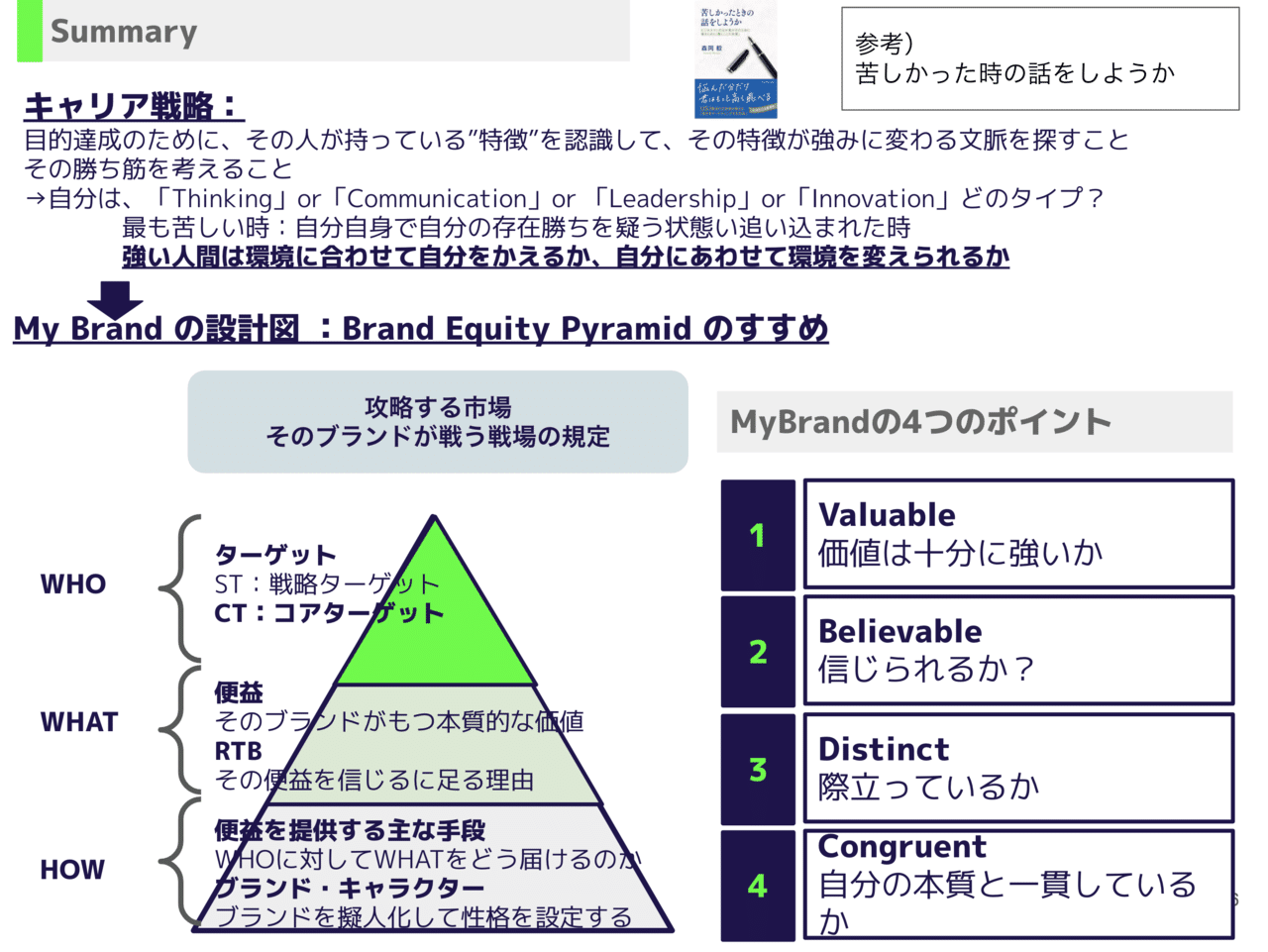社内向けです。
11月末をもって、内定者時代からお世話になったゲーム事業部を離れ、
新規事業へとジョインします。

CA内でのキャリアとして、個人的にも大きなターニングポイントになり、
節目としてSGEでの今までや、今後のことについてまとめておきたいと思いブログを書こうと思いました。
(書いていていたら、結構長くなりましたw)
<目次>==================
<今まで>
【経験:地力をつけれたSGE】
【感じたこと:標準化と差別化】
【課題】
<これから>
【次のミッションについて】
◆なぜゲームから、別ミッションを選んだか
◆何を成し遂げたいか
========================
<今まで>
【経験:地力をつけれたSGE】
内定者時代からあわせると2.5年ほどSGE内にてマーケ/プロモを担当し数々の業務を体験しました。
長寿タイトルのダカイや、新規タイトルの立ち上げ、売上拡大のグロースタイミング等
数々のフェーズのタイトルのマーケティングを担当できました
・2度のCMの設計、プランニング、ディレクション、クリエイティブ
(2度目は本当に1人で全部やって、まぁ大変だった笑)
・超有名IPやスポーツ団体とのコラボの開拓、アライアンス
・インターネット広告のインハウス化(主導ではなく、サポート?)
・ゲーム内KPIを飛躍させたキャンペーン、企画
・キャンペーンwebサイトのディレクション5個以上
・特定分野で1位に上り詰めれたASO
・100万登録以上の事前登録の設計、運用
・担当タイトルのクローズ体験
・アイドルのプロデュース/プロジェクトマネジメント
・ファンリアルイベントの0からの設計、実施
・リーダーとしてのチームマネジメント
・100名規模プロジェクトのボードメンバー
今月25歳になるのですが、市場を見渡しても同世代で
これだけのマーケティングアプローチを経験できた人はいないだろうなと思いますし、
確実にマーケティングに関しての経験やスキル、戦略設計については
地力がついてきたなと思えております。
改めて機会を与えてくださった、部署のみなさま、SGEの皆さまには感謝しかありません。
自分の力以上のことを任せてくださったということを忘れず、謙虚に邁進したいと思います!
【感じたこと:標準化と差別化】
僕はマーケティングや諸々の仕事は
・標準化
・差別化
の2種類にわけられると思っています。
ゲーム市場は成熟したマーケットになっていて、
マーケティングの手法もある種固定化しはじめてる市場です。
だからこそ、他社にひけをとらないための標準化はもちろん、
そこから抜きん出るために、付加価値をつけたり、いままでみたことがないことをする等「差別化」が重要です。
だけど、標準化がそもそもできていないと、差別化にも至れない。
最後に1年間ほど担当した
「戦国炎舞 -KIZNA-」では、プロジェクトの方針から
いままで実施していたマーケティングとは180度異なる内容をすることになり、
上記の2点をかなり強く意識できることができました。
例えば、以下のような感じです。(全部自分が、でなくたくさんの方に助けられてのことです)

この両輪をまわすことが出来たらこそ、
KPIもかなり改善し、所属組織のミッションである、
「マーケティングで事業を伸ばす」ことが出来たのかと思っています。
【課題】
担当タイトルのプロデューサーから「好きなようにやっていい」と言われてから、
本当に自分の好きなように、一番成果がでるだろう、ということを好き勝手やらせていただきましたが、
かなり自分でも反省すべき点が多々ありました。
その中で個人的な一番の反省点としては
「チームメンバーのポテンシャルの最大化、喜びの最大化」が出来なかった点です。
一番成果がでることはなんなのかを考えたり、
自分が業務を担当するあまり、育成やケアがなかなか出来ず、
チームメンバーの方々にはかなりの負担やストレスを与えてしまったと思っています。
「チームメンバーをもつことは、少なくともその人の人生に責任をもつこと」と常に意識していたものの
なかなかメンバーの皆さんにプラスになることができなかったことが非常に悔やまれます。
信じること、自己開示と期待値のすり合わせの3点が自分の課題かとおもっているので、
次のミッションでは、同じ過ちは繰り返さないようにしたいです。
<これから>
【次のミッションについて】
12月からはゲーム事業部を離れて、メディア事業部の完全新規事業を担当します。
(異動ではなく、同じ部署で、別ミッションを担当する、ということです。)
事業内容についてはまだ詳細なことは言えませんが、
◆なぜゲームから、別ミッションを選んだか
◆何を成し遂げたいか
を記載したいとおもいます。
◆なぜゲームから、別ミッションを選んだか
ゲーム事業からミッション変更の話を聞いた時は、
かなりゲーム事業への愛着や、まだやりたいことや、絶対これ成果出るじゃん!というのもあったので、
「ゲーム事業に残りたい」と上長にも伝えました。
ただ、やはり自分はゲームというドメインに限らず、
「マーケッターとして大成したい」という気持ちがありました。
何となくこの1年後の自分がイメージできる環境よりも、
・1ヶ月後なにやっているかわからない
・自分が動かないと事業が成功しない、自分がやるしかない、と思えた
(誰より自分がやったほうが成功角度が高いとおもった)
・絶対的に、ゲームでは出来なかったマーケティングができる
・先駆者や事例がいないので、自分がパイオニアになれる
・尊敬する上長や、CA8の方々との接点をもつことで、強制的に視点があげられる
・根拠はないが、成功イメージが湧いた
・沸々と事業責任者、会社経営をしたいという気持ちが出てきたので、今よりも近く、リアルな場所で
事業の立ち上げ、グロースに責任を持ちたい
という点から、新しい領域でのチャレンジを決めました。
◆何を成し遂げたいか
まだ具体的な事業内容を言えないので、イメージもつきづらく、
もしかしたら大それたことなのかもしれませが、僕は次回のミッションを通じて
「世の中のエンターテイメントを拡張する」 ことをしたいと思っています。
ここに関しては、サービスリリースがあってから詳細を記載したいと思っていますが、
確実に、世の中のエンターテイメントをもう一歩進化させることに寄与できると思っています。
この思いは事業ありきで、でてきた考えでなく、
事業を聞かされる前から、自分のなかでかんがえていたことでもあるので、
自分中での納得度も高く、実現したいことでもあります。
こうした思いや、SGEを離れて挑戦させていただけるという気持ちを忘れず、
必ず成功させてきます。
<最後に>
事業的に絶好調で、これからまた勝負だ!という時でもあり
組織的にも大変な中でも、この挑戦を快く受け入れてくださった
桑田社長や、大森Pはじめ戦国炎舞チームの皆さん、
サムザッププロモチームの皆さん、SGEの皆さんに感謝しかありません。
ミッション異動してから、竹内の声を聞かなくなったと言われないよう、
新ミッション頑張ります!