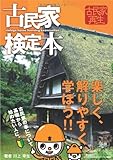古民家で(木造の建築は今でも)使われる寸法は尺貫法が多いです。
ただし、体積はメートル方ですね。
また、1間は1820mmで図面を書くことが多いです。
尺貫法とは
今でも建築においては大工さんは昔の長さの単位である尺(しゃく)を使っています。
これは尺貫法(しゃっかんほう)と呼ばれ長さ、面積などの単位の一つです。
尺は長さの単位で貫は質量の単位です。
ちなみに貫は日本独特の単位で中国では斤が使われるので
中国では尺貫法ではなく尺斤法となります。
この単位は東アジア一帯でつかわれていますが
現在日本では計量法という法律で取引や証明で尺貫法を使う事は
禁止されていて違反者には50万円以下の罰金だそうです!
しかし建築の現場の世界ではまだまだ現役で
尺の寸法体系のあわせて部材などの寸法が決められていて、
現場ではいまでも尺で寸法が話されています。
尺での長さの単位は 1尺が約0.303メートルで
10寸→1尺、
10尺→1丈(じょう)、
6尺→1間(けん)
360尺が60間で1町(ちょう)となっていきます。
(「古民家検定本」より)
・北海道のグリーン建築(循環型建築社会)応援よろしくお願いします。
1、新しい建築をするにあたり、全てを捨てることなく生かせる資材(伝統資材)を活用する(古材の活用)
2、新しい建築をするにあたり、将来再使用できる資材を使用する(道産材の活用)
3、使える建築に関しては、出来るだけ長期間使用できる提案を行う(古民家の再活用)
・民家の甲子園進めています
・古民家の保存活動進めています
===================================================
一般社団法人 北海道古民家再生協会
理事長 江崎 幹夫
011-643-2078
http://www.kominkakyokai.net/
===================================================