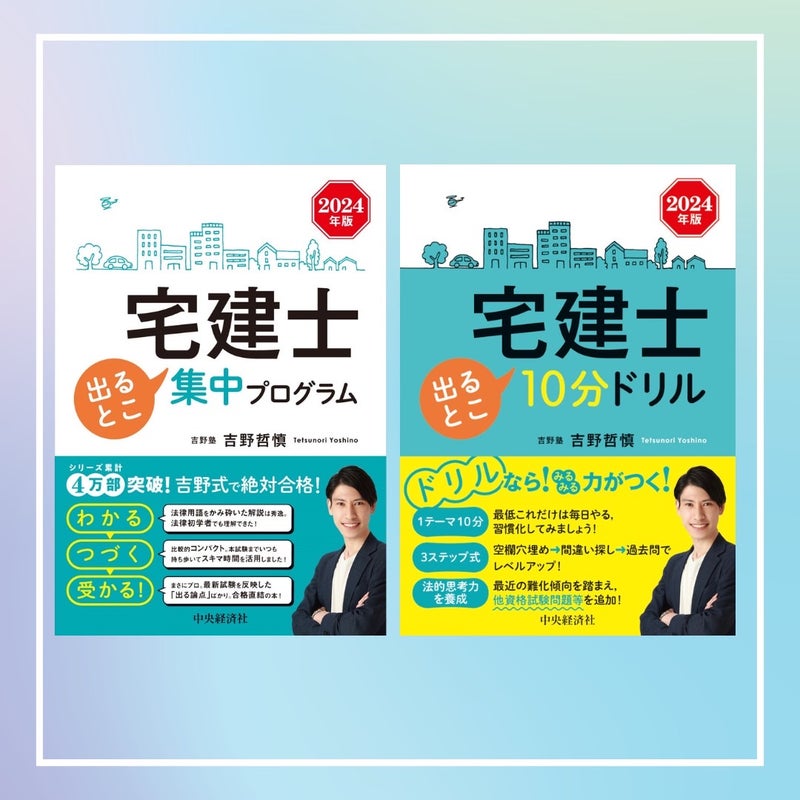皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m
👇短期間で合格へ! 直前必勝講座はこちら👇
◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法】
・債務者B、Cの2名が、令和6年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Aに対して1,000万円の連帯債務を負った。その後、BとAとの間に混同があったときは、Bは、弁済をしたものとみなされる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
混同は、絶対効。
混同が生じると、弁済した場合と同じ効果が生じます。
他の連帯債務者の債務もそれにより消滅することになります。
さぁ、今回は、連帯債務の「絶対効」がテーマ。
連帯債務においては、相対効が原則で、絶対効が例外でしたね![]()
復習しましょう♪
連帯債務者の一人に何かあっても、他の連帯債務者に一切効力を及ぼさない(影響しない)のが相対効。
反対に、連帯債務者の一人に何かあった場合、他の連帯債務者にも効力を及ぼす(影響する)のが絶対効。
では、どんなものが絶対効??
【主な絶対効】
①相殺
②混同
③更改
【②混同について】
たとえば、債権者が死亡し、連帯債務者の1人が相続し債権者と債務者が同一人になった場合、債権は消滅します。
自分が自分に借金を返すっていうのもおかしいですよね![]()
債権の混同といって、このケースでは、債権を消滅させます(弁済したものとみなされます)。
これは、他の連帯債務者に対しても効力を及ぼします。
【③更改について】
契約の内容を変えて、まったく新しい債務を発生させるのが更改。
たとえば、今まで「1,000万円を現金で支払う」という内容の債務だったのを、「1,000万円の価値がある不動産を引き渡す」といった感じです。
この場合、今までの債務(1,000万円を現金で支払う)は消滅します。
その部分に関しては、他の連帯債務者に対しても効力を及ぼします(当初の債権は消滅)。
上記3つは、ゴロで覚えちゃいましょう![]()
そして、この言葉だけ覚えるのではなく、内容もしっかり理解しましょうね(^^♪
昨年のご利用者1万名超 大人気模試👇
【大好評発売中】
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m