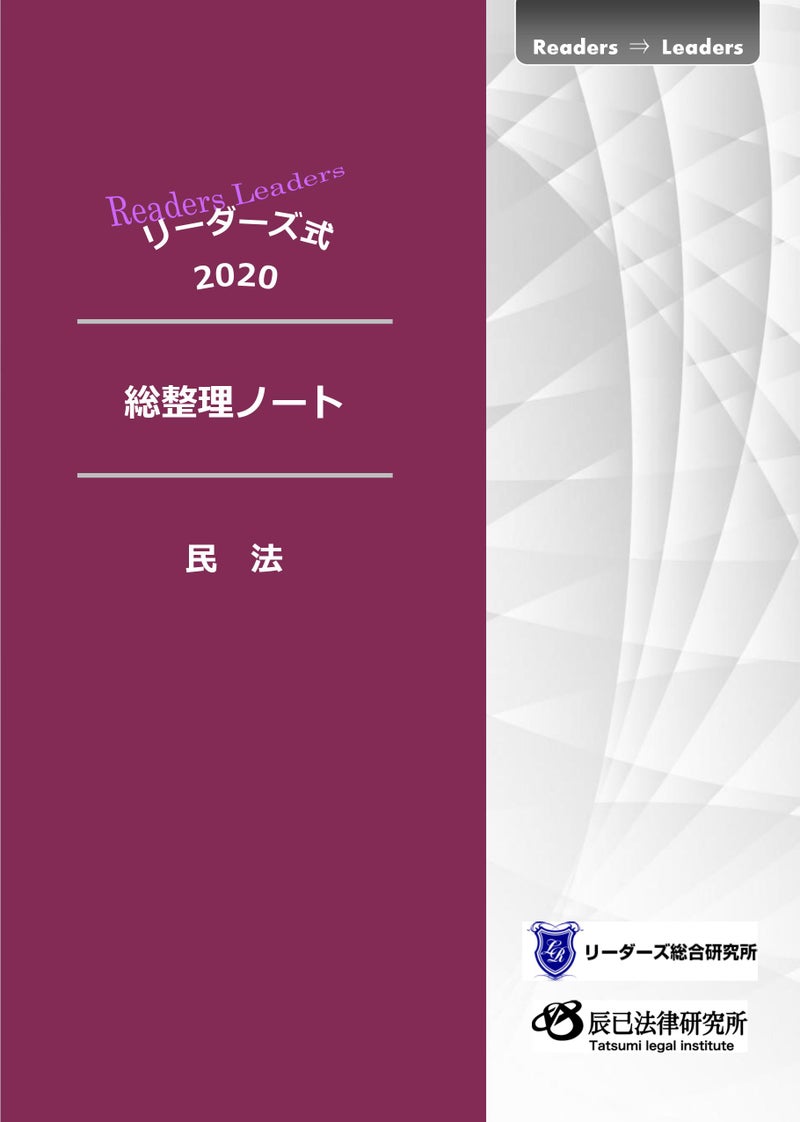人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
リーダーズ式☆3ステップ学習法
本試験では、条文と判例の知識を聞いてくる訳ですから、合格点をクリアーするためには、それらの
知識の精度を高めていくことが重要です。
したがって、直前1カ月前は、知識の精度を高めるため、記憶用のツールである総整理ノートを使っ
た知識の定着化(記憶)に重点を置いた学習を心がけてほしいと思います。
直前1か月前プログラム
合格する人ほど、この知識の定着化(記憶)の作業を、何回も何回も繰り返して、知識の精度を高め
ていっています。
知識の精度を高める!
これとは反対に、合格できない方ほど、直前期に公開模試等を受けまくって、記憶の作業に時間を割
いていません・・・
行政書士試験の場合、記述式がありますので、要件・効果等を、きちんと「記憶」していないと書けま
せんので、合格するのが難しくなってしまいます。
エビングハウスの忘却曲線によれば、
1時間後には、56%忘却し、44%記憶
1日後には、74%忘却し、26%記憶
1週間後には、77%忘却し、23%記憶
1ヶ月後には、79%忘却し、21%記憶
1ヶ月後には、79%は忘れてしまう訳ですから、知識を定着化させるためには、やはり、何回も何回も
繰り返すこと(復習)が重要となってきます。
知識の定着化(記憶)の前提として、当然のごとく、記憶すべき知識を選別し、それらをひとつに集約
しておく必要があります。
そのためのツールが総整理ノートです。
復習する際には、ただテキスト読んだり、ただ問題を解くのではなく、①何を、②どのように記憶して
おけば本試験で得点することができるのかという視点から、常に、記憶を意識した学習を心がけて
ほしいと思います。
出題の「ツボ」を掴む!
合格者の方の総整理ノートを見せていただくと、やはり、講義の中でお話している出題のツボ等が上
手に集約されています。
合格できる方と合格できない方との大きな「差」は、この集約力にもあるのではないかと思います。
受講生の皆さんは、講義の中でお話している出題のツボや当ブログを参考にしながら、総整理ノート
に、記憶しておくべきことを、きちんと集約化をしていってください。
2 復習のポイント
① 賃貸借契約(3)
まずは、民法(全)p438、総整理ノートp298、パワーポイント(第6章賃貸借⑫)で、賃 貸人及び賃借
人が移転した場合の敷金返還義務の承継について、知識を整理しておいてください。
民法は、事例の「類型化」がきちんと出来ないと、答えが逆になってしまうことが多々ありますので、
図解をしながら「類型化」の練習も行ってみてください。
敷金は、判例法理が明文化されたテーマです。
② 請負・委任契約等
まずは、パワーポイント(第8章請負②)で、請負・委任・雇用の違いを、ざっくりと理解しておいてくだ
さい。
また、民法(全)p443、総整理ノートp316で、請負人の義務と注文者の義務に分けて、知識を整理し
ておいてください。
請負は、改正前は、瑕疵担保責任がよく問われていましたが、改正後は、売買の契約不適合責任を
準用する形に大きく変わります。
したがって、この部分の知識は、消去しておいてください。
次に、民法(全)p444、総整理ノートp317、パワーポイント(第8章請負④⑤)で、目的物の所有権の
帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分けて、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp318の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく理解しておいて
ください。
最後に、民法(全)p451、総整理ノートp320で、委任者の義務と受任者の義務について、条文を中心
に、ざっくりと確認しておいてください。
委任契約は、
本試験では、事務管理との比較の問題で出題されています。
委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があるがないかの違
いがあります。
この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較問題を出題する
際の出題意図です。
民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾がつかなくなってし
まう科目です。
そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
昨年も、この委任と事務管理の比較の図表問題が出題されたように、このテーマは、、典型的パター
ン問題ですから、昨年の本試験で、きちんと得点出来ているかを確認してみてください。
やはり、典型的パターン問題で落とさないことが重要です!
この典型的パターン問題で落とさない!を主眼にした講座が、3月27日(金)より、配信が始まってい
る民・行☆解法ナビゲーション講座です。
≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫
① 民・行のAランク問題を落とさない!
② 民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!
③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング
民・行☆解法ナビゲーション講座
↓詳細
こちらも、基本書フレームワーク講座の復習として、上手に活用してみてください。
③ 不当利得
まずは、民法(全)p480以下で、不当利得の2つの大きな類型について、ケースを理解しておいてくだ
さい。
今回の改正で、侵害利得と給付利得とでは、不当利得を処理する適用条文が変わってきますので、
要注意です。
もう一度、民法総則の取消しと無効と、契約各論の解除の復習を行ってみてください。
給付利得の場合、契約が表の世界で、契約関係の巻き戻しである不当利得が裏の世界となります。
表の世界と裏の世界!
次に、民法(全)p487以下、総整理ノートp336以下、パワーポイント(第2章不当利得②③④)で、3つ
の判例のロジックを理解しておいてください。
本試験では、転用物訴権の判例が頻出していますので、法律上の原因の要件に絡めて、判例のロ
ジックをよく理解しておいてください。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。