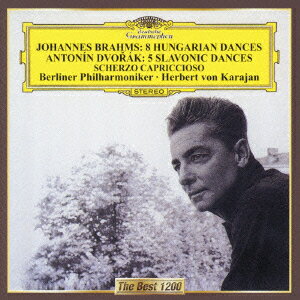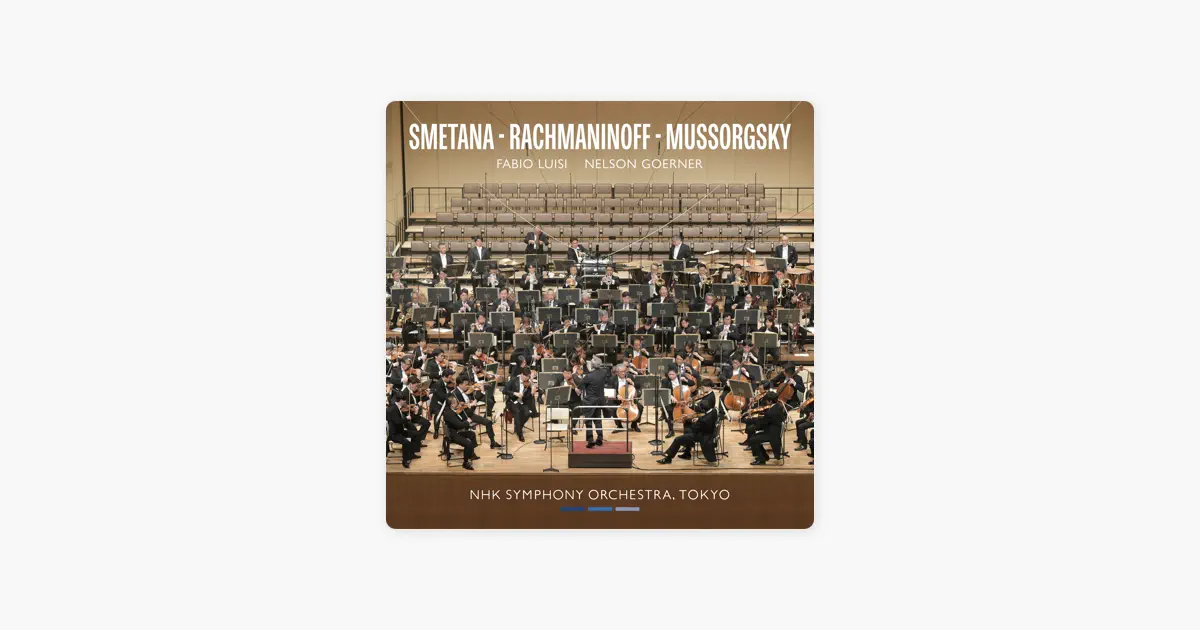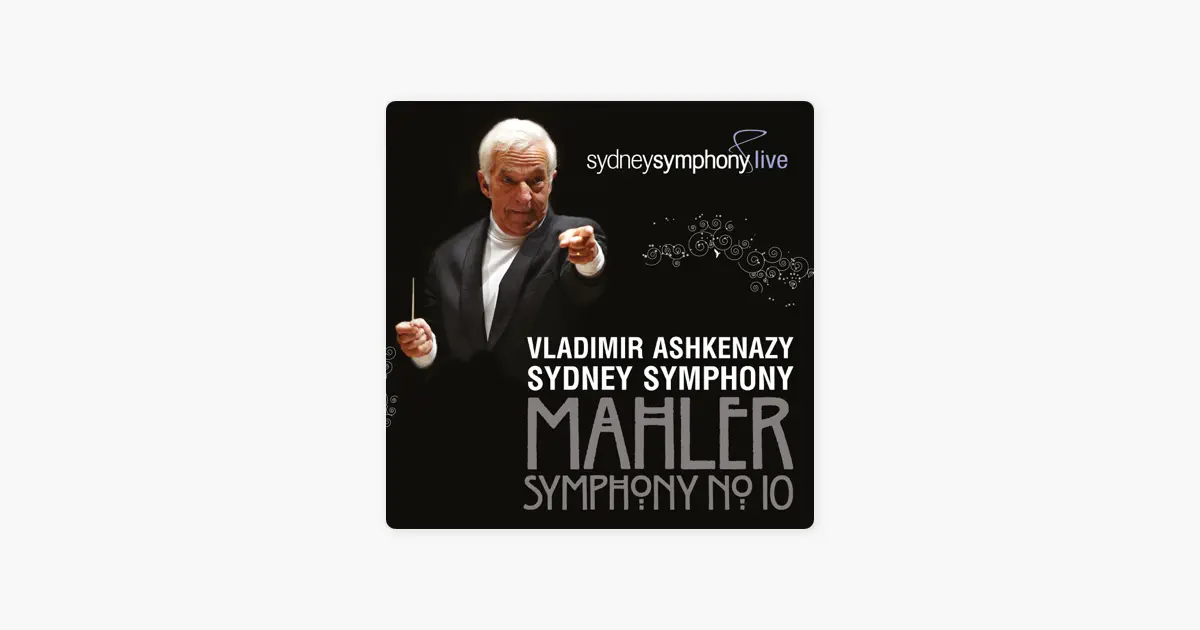みなさんこんにちは😃本日2月20日は、日本を代表とする作曲家武満徹の命日です。今年で没後30年になります。そんな本日ご紹介していくのは、1984年にNHK交響楽団の「作曲家の個展」シリーズにて演奏されたライヴです。「オリオンとプレアデス」が初演された記念すべき演奏会となっています。他にも「ノヴェンバー・ステップス」など武満徹の名作が収録されています。
武満徹作曲:
「岩城宏之指揮/NHK交響楽団」
地平線のドーリア
鳥は星形の庭に降りる
「堤剛(チェロ)、岩城宏之指揮/NHK交響楽団」
オリオンとプレアデス
「鶴田錦史(琵琶)、横山勝也(尺八)、岩城宏之指揮/NHK交響楽団」
ノヴェンバー・ステップス
1981年から始まった「作曲家の個展」。松平頼則、黛敏郎、山田耕作ときて武満徹が4年目に演奏された。日本初演となった「オリオンとプレアデス」の他に、「ノヴェンバー・ステップス」など代表的な作品が多数収録されている。また、注目的なのは、「ノヴェンバー・ステップス」で尺八や琵琶を演奏しているのが世界初演と同じ奏者であるということ。名盤であり歴史的な録音である。
[Disc 1]
・武満徹:地平線のドーリア
録音:1984年6月13日(ライヴ)
セルゲイ・クーセヴィツキー財団からの委嘱として1966年に作曲された。録音による初演は同年の7月に若杉弘&読売日本交響楽団によって行われ、公開初演は1967年2月にアーロン・コープランド&サンフランシスコ・ムジカ・ヴィヴァにて行われた。曲名にある「ドーリア」はドーリア旋法のことで、2群の弦楽合奏によって演奏が展開されていく。演奏が弦楽器ということもあって、その細部まで細かく演奏されるダイナミクス変化の細かさには驚かされるものがあり、不協和音ではあるが大きな苦になるような響きではないというのが面白い。岩城さんとN響による安定感のある演奏ながら明確な点と線による演奏を聴くことができるようになっているので、自由度の高い作品を楽しめるようになっている。
・ノヴェンバー・ステップス
録音:1984年6月13日(ライヴ)
武満が作曲した琵琶と尺八のための「エクリプス」を小澤征爾がバーンスタインに聴かせたところ、非常に気に入り日本の楽器とオーケストラによる協奏曲を書いてほしいと依頼したことがきっかけで1967年に作曲された。ニューヨーク・フィルハーモニック125周年記念委嘱作品。1967年11月9日に今回もソリストとして演奏している鶴田錦史、横山勝也、小澤征爾&ニューヨーク・フィルハーモニックによる演奏で初演が行われた。この曲を聴くことによる安心感はいつになっても消えることはなく、紛うことなき武満徹作品の代表的な名作であることは間違いない。複雑ではあるが尺八と琵琶の協奏的な世界観が独特ではあるおしても、N響がオーケストラであることによって非常に素晴らしい安定感を生み出しているのは間違いない。ライヴであるということもあり、その圧倒的な臨場感には演奏を聴くだけで圧倒されてしまうのは間違いない。
[Disc 2]
・鳥は星形の庭に降りる
録音:1984年6月13日(ライヴ)
1977年にサンフランシスコ交響楽団の委嘱によって作曲。同年11月30日に小澤征爾&ボストン交響楽団によって初演が行われた。作曲の委嘱を受けた年の春にポンピドゥー・センターで後頭部を星形に刈り上げたマルセル・デュシャンを写真家のマン・レイが撮影した写真を見た武満がそれによって喚起された夢を見た逸話がある。ベルクとの関連性を指摘されており、現代的で強烈なサウンドを聴くことができる一方で弦楽器が奏でる音色からは美しい響きを合わせて聴くことができるようになっている。曲が終わる瞬間の響きも美しい。N響による演奏では、抜群の安定感からなるテンポの緩急と弦楽器による細かいサウンド演奏を聴くことができる。
・ドリームタイム(夢の時)
録音:1984年6月13日(ライヴ)
チェコの振付師イリ・キリアンの委嘱により、ネーデルランド・ダンス・シアターのために1981年に作曲。1982年6月27日に岩城宏之&札幌交響楽団によって初演された。曲名はアボリジニの神話「夢の時」から採られている。テンポの揺らぎからなる緩急が絶妙な演奏で、一体感あるN響の演奏も素晴らしい。指揮を岩城さんが行っていることの安定感、一音一音における細かいダイナミクス変化の演奏も含めて非常に面白い演奏となっている。
・オリオンとプレアデス(日本初演)
録音:1984年6月13日(ライヴ)
1984年にサントリー音楽財団によって委嘱されて作曲。パリにて世界初演。今回の演奏は日本初演となっている。チェロとオーケストラのための作品で、ここまでに聴いてきた作品と比べても非常に聴きやすい印象を受ける。攻撃的な不協和音もなく、スッキリとしていて聴きやすく透明度の高さも非常に良い。ダイナミクス変化がスケールのある演奏から行われていることによって、チェロとオーケストラそれぞれにおける濃厚さと透明度の高い音色からなる演奏を聴くことができる。ライヴの臨場感も含めて収録されているので、最初から最後までたっぷりとした演奏を楽しめた。
武満作品の名盤は手元にいくつかあるが、今日まであまり聴いてこなかったところがある。苦手意識があるのかもしれない。ただ、セッションよりもライヴ録音の方が武満作品の素晴らしさについて理解しやすい印象が深まった。武満作品についてはこれまでに聴いてこなかった分これから少しずつ取り上げていけたらと考えている。
https://tower.jp/item/2130502