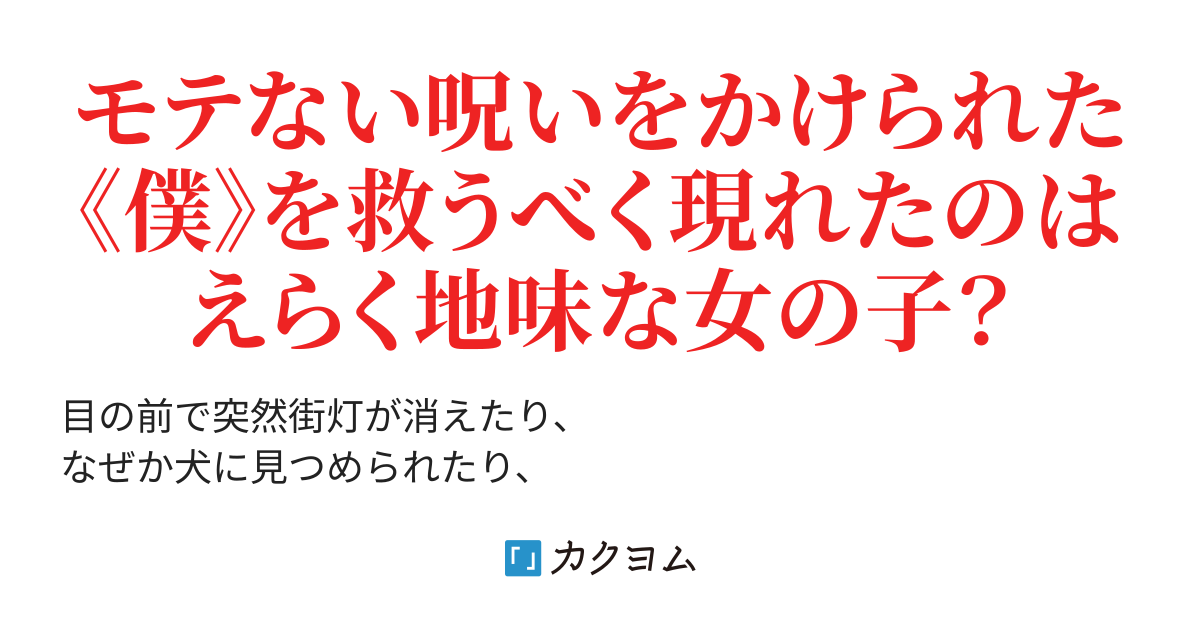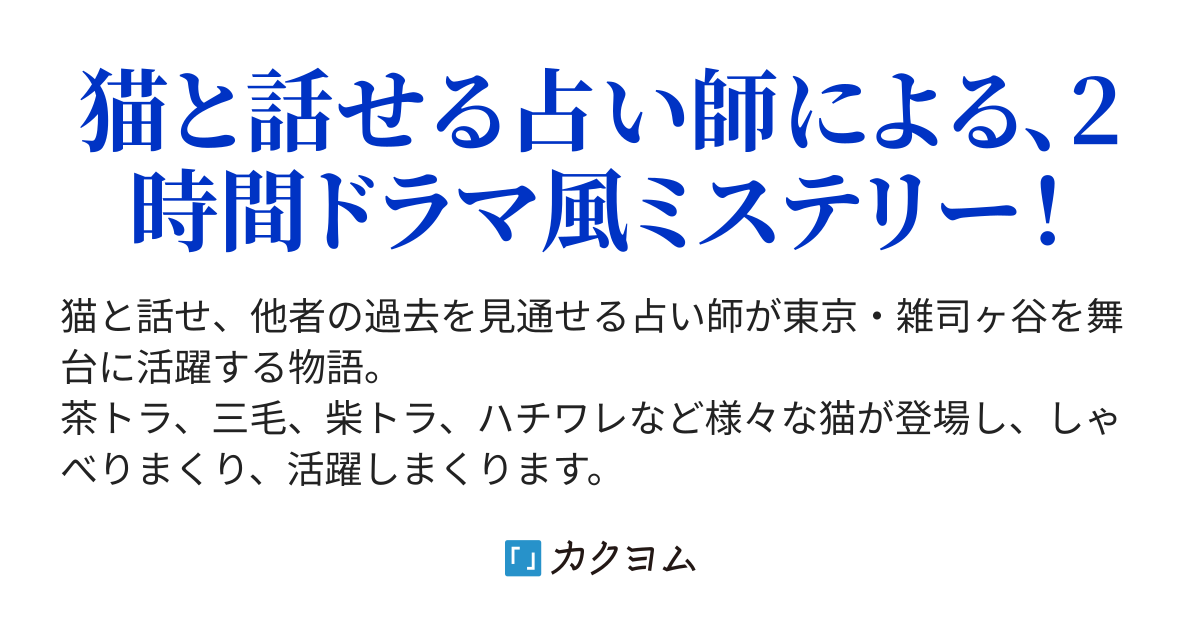「では、安川さんは?」
「あの、はじめの方に野々宮くんがポケットを探るシーンがあって、女の人の字が書かれてる封筒がはみ出てたというのが、」
「素晴らしい。いや、すごいですね。そうです、その通り。これはかなり前ですよ。――ああ、あった、三十三ページですね。
『野々宮君は少時池の水を眺めていたが、右の手を隠袋へ入れて何か探し出した。隠袋から半分封筒が食み出している。その上に書いてある字が女の手蹟らしい。野々宮君は思う物を探し宛てなかったと見えて、元の通りの手を出してぶらりと下げた』
ここはさっき読んだところと似てますね。彼のポケットからは美禰子の手紙が二度出てくるんです。まあ、一度目のは確実じゃないですがそう考えていいでしょう。で、二度目のときは結婚披露の招待状なわけです。このように前に置いたシーンを焼き直して、そこへ違った意味をつけるというのは面白いやり方だし、関係の移り変わりが読めますよね。そして野々宮くんはその招待状を千切って棄てます。しかし、ちょっと妙じゃないですか? 超然としてたはずの野々宮くんが激しい行為をしてるんですから矛盾にもみえます。ただ、この矛盾も意図して入れられたものですよ。超然と激した行為という矛盾に野々宮くんの内面をあらわしてるんです。逆にいうと、この行動のために漱石は敢えて野々宮くんを超然として入らせたんですね。それともうひとつ、これもさらっと書かれてますが、三四郎が東京に戻ってきたのは披露宴の後なんですね。ということは教会の前で別れてから二人は顔を合わせていないわけです。漱石は三四郎を披露宴に出席させることもできたのにそうはさせなかったんですね。これは深刻にさせないためなんでしょう。ところで、もしそこに三四郎が行ってたら、そして美禰子を諦めきれてなかったらどうなってたんでしょうね」
高く手が挙がった。高槻さんは肩をすくめてる。
「なにを言いたいかわかる気がしますけど、なんですか?」
「そりゃ『卒業』のパターンになるんだろ。ダスティン・ホフマンだ」
「いや、そんなのこの子たちにはわかりませんよ。いったい何十年前の映画です? ――ああ、いえ、そういう映画があるんです。僕もよくは知りませんが、結婚式に乱入して花嫁を奪い去るシーンで終わるんですよね?」
「そうだよ。でも、正確にはその少し後までつづく。その二人はバスに乗りこむ。大笑いしながらね。ただ、乗客に見られると真顔になって正面を向く。顔を合わそうともしないんだ。もし三四郎が披露宴に行き、まあそんなことはしないと思うが美禰子を奪い去ったとしたら、この二人もきっとすぐ後で真顔になるんだろ。再会したばかりの代助と三千代みたいにね」
高槻さんは天井へ目を向けた。そのままでうなずいている。
「なるほど、そういうことですか。ただ茶々を入れたんじゃないんですね。――いや、すみません。前に『それから』の話をしましたね。漱石がこの『三四郎』の次に書いた小説です。そこではより深刻になった関係が描かれてました。新井田さんはそれを言ってるんですよ。『それから』は真顔になって互いを見ようとしなくなった三四郎と美禰子の話でもあるってね。衝動に、いえ、漱石の言葉でいうと『自然』ってことになるんでしょうが、主人公がそれに従ったとき、この物語はより深刻さを増すんです。そしてその『自然』というのは形こそ違え、この『三四郎』にもあらわれてます。とくに美禰子が言った『われは我が愆を知る。我が罪は常に我が前にあり』という台詞にね。しかし、それについては後で話しましょう。宿題にしときましたからね。――では、つづけます。最後の件を読みますよ。
『与次郎だけが三四郎の傍へ来た。
「どうだ森の女は」
「森の女という題が悪い」
「じゃ、何とすれば好いんだ」
三四郎は何とも答なかった。ただ口の内で迷羊、迷羊と繰返した』」
本を伏せ、高槻さんはひとりひとりに目を向けた。みな首をあげ、正面を見つめてる。
「ここでこの物語は終わるんです。広田先生と野々宮くんは『森の女』から離れました。三四郎は腰掛けにもたれかかってます。そこで与次郎が絵の感想を訊くんですね。三四郎は『題が悪い』とだけこたえます。『じゃ、何とすれば好いんだ』という問いかけにはこたえず、口の中で『迷羊、迷羊』と繰り返すんです。これはつまり、このライフサイズで描かれた絵に相応しいのは『迷羊』であるということです。またそれは美禰子自体を指し示しているのでしょう。なにしろ目の前にあるのは等身大の美禰子なんですから。では、なぜそう言ったのでしょう? 僕はこう思うんです。それまでずっと美禰子に振りまわされていて、常に一定の謎を感じていた三四郎は教会の前で会ったときに納得というか、ある程度は腑に落ちるものを得たんでしょう。それは美禰子の『われは我が愆を知る。我が罪は常に我が前にあり』という言葉やヘリオトロープを嗅がせた行動によって受け取ったものに思えます。それに三四郎には美禰子を迷う存在と認めることが必要だったんでしょう。しかし、それは当たってると思いますよ。美禰子はずっと迷う存在だったんですから」
雲は走るように流れてる。髪を撫でながら高槻さんは窓の方を向いた。
「先ほど僕は美禰子夫婦を第三の世界の象徴と言いましたが、それは外側から見てのことに過ぎません。美禰子はどの世界にも属せない存在なんです。第一の世界は両親の死によって半分以上ほど欠けたものになってます。第二の世界にだって彼女の居場所はありません。女学校を出たからといって学者にはなれないんです。そして第三の世界は、――うん、これは読んだ方がいいでしょうね。ええと、ここですか。
『第三の世界は燦(さん)として春の如く盪いている。電燈がある。銀匙がある。歓声がある。笑語がある。泡立つ三鞭の盃がある。そうして凡ての上の冠として美しい女性がある』
つまり女性である美禰子は第三の世界の付加物なんです。中心ではないんですね。結婚することによって彼女はその世界へ行ってしまったのですが、それはそうせざるを得なかった結果なんです。いや、もしかしたら美禰子は第四の世界を求めたのかもしれません。三四郎と駆け落ちして、どうなるかはわからないものの恋だけは成就させるといった世界をね。しかし、迷った末に第三の世界の付加物になることを決めました。それが三四郎にはわかったのでしょう。そして、彼からすると美禰子の決定が迷った末のものであると認めることで最終的な別れを告げたってことになるんです。美禰子にも自分の恋にもね。それがつまり、この絵を『迷羊』と呼ぶ理由なんです。口に出して言わなかったのは二人の間にあったことを大切にしたいからなのでしょう。他者と共有したくない思いなんですよ」
本は完全に閉じられた。顔をあげ、高槻さんは微笑んでいる。
「ということで、十回にわたっての講義はひとまず終わりました。最後の章は短いもののかなり充実した内容だったのがわかったと思います。物語の終結部はこうすべきという見本のようです。――では、かなり時間をとってしまいましたので休憩にしましょう。新井田さん、この後もすこしだけ『三四郎』の話をしたいんですが大丈夫でしょうかね?」
「ん? ああ、ま、大丈夫だろ。じゃ、一休みしよう。いやぁ、高尚な論説を聴きすぎて疲れちゃったよ。高槻くん、一服しようぜ」
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》