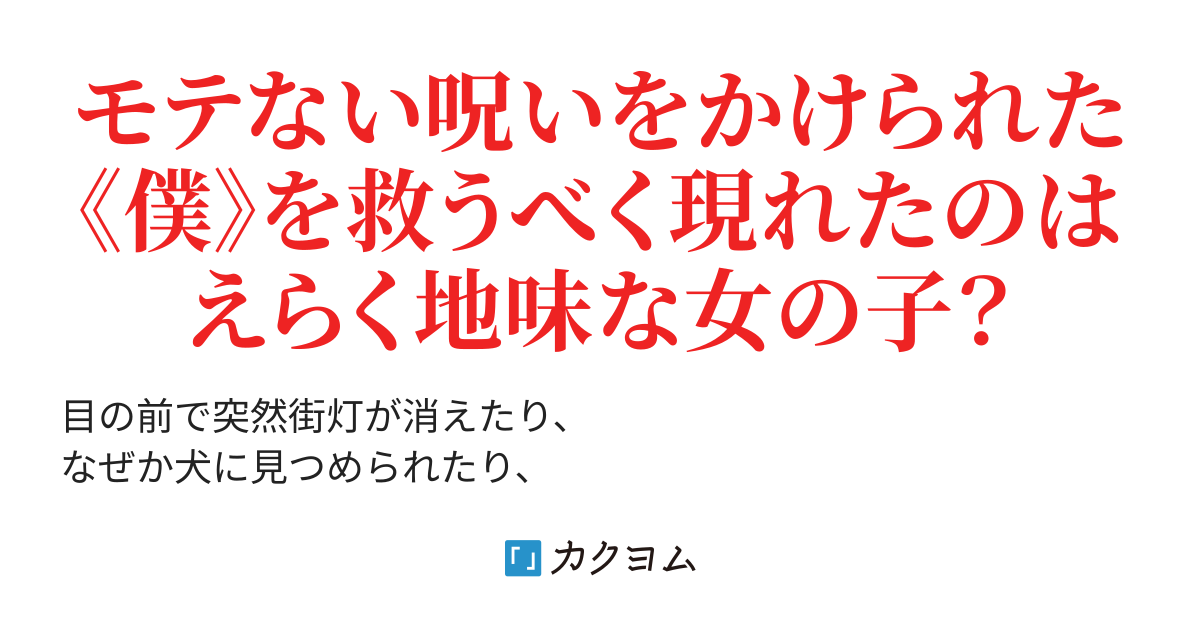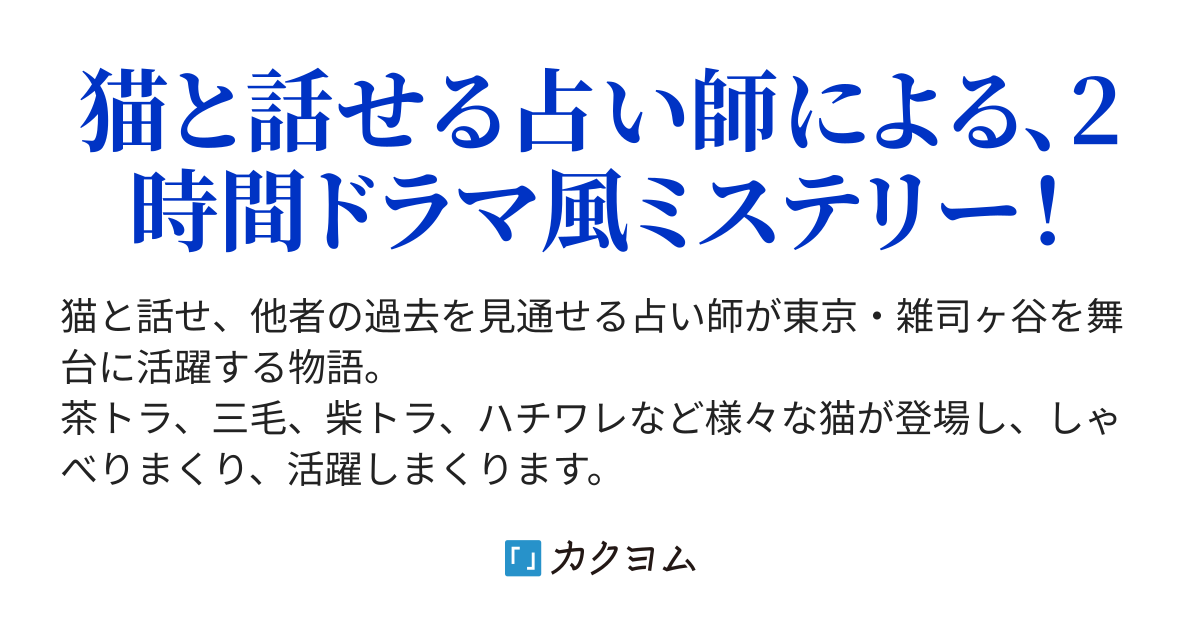「いや、もう憎んじゃいないよ。そういう時期もあったけどそうでもなくなってきた。あのさ、人間はそんなに長くひとつの感情を持ちつづけられないんだ。とくに生きてる人間にたいしての感情は揺れまくり、常に一定じゃない」
そう言いながら高槻さんは身を引くようにした。門の陰には加藤さんがいて、唇を薄く反らしてる。
「どう? いろいろ質問できた?」
「あ、はい。――あの、さっきはありがとうございました」
「ああ、あれね。でも、行かなくて大丈夫だったみたい。篠田さんだけでね」
高槻さんは頬を撫でるようにしてる。それから、なにも言わずに歩きだした。
「あの、新井田先生から連絡はありました?」
「ん、あったよ。さっき職員室で聴いた。なんかわからないけど直接言ってこないんだ。次回は出てくるそうだ。その前に会って話したいんだってさ。ま、引き継ぎってことだろうな」
「じゃあ、ほんとに次で最後ってことですか?」
「そうだね。もとから十回ってことだったし、こっちにもいろいろできちゃってさ、昼まで出てるわけにもいかなくなってきたんだよ」
「そうですか。――その、私、次で最後じゃ言えないかもしれないと思って待ってたんです」
「どういうこと?」
「あの、ありがとうございますって言いたくて」
「え? なんで?」
加藤さんは先へ行った。振り向きもせず、ぐんぐん歩いていく。
「その、なんとなくいろんなことがわかってきたように思えるんです。『三四郎』を読んで、それに先生の講義を聴いてわかったんです。それと自分のまわりも少しすっきりしてきたっていうか。――あの、ほんというと初めのうちはちょっと嫌だなって思ってたんです。なんか、私や特定の人にだけ変な質問してくるように思えたんで。だけど、そのうちに少しずついろんなことが変わっていって、――私が言ってること、なんとなくでもわかります?」
「ああ、なんとなくわかる気がする。ま、君がどういった選択をしたかまではわからないけどね」
振り返って加藤さんは顔をあげた。口は今にも笑いだしそうになっている。
「それはきっとすぐにわかると思います。坂を降りきったあとで」
「そうか。ということは真剣に関わり合おうとした者が出てきたんだな。そいつはよかった。君は絵に収まることなく、ひとつの物語を終えられたってわけだ。ま、それはこれからもつづく物語なんだろうけどね。そうだろ?」
加藤さんは我慢しきれなくなったように笑った。
「はい、そうなればいいって思ってます」
加藤さんはロッテリアに入っていった。通り側の席につき、笑顔を見せている。向かいの人はだらしなく脚を伸ばしていた。
「うーん、これは丸く収まったってことになるのかな?」
「そうなんじゃないですか」
「でも、ちょっと微妙だな。登場人物に起こったと考えたらそれまでだけど目の前にいる人間だとかわいそうになる。ほら、『三四郎』における勝者はディテールのわからない男で、三四郎も野々宮くんも敗者なわけだろ。だから安心して読める部分もあると思うんだ。だいたいすべての男がかわいそうなんだからね。――うん、そういうところでもあれは巧くできてるんだな。勉強になるよ。君たちに教えることで僕も教わったことが多い」
階段を降りながら高槻さんはうなずいている。私は何度も目を向けていた。
「いつも小説のことばかり考えてるんですか?」
「ん? そんなことはないよ」
「じゃあ、他になにを考えてるんです?」
「他に?」
首を傾げながら高槻さんは改札を通った。ホームに降りてからは掲示板を見つめてる。
「あの、小説の他に考えることってなんです?」
「いろいろ考えてるよ。店のこともあるし、他にもいろいろとね。今日は仕入れてるとこの人間が来るんだ。なんだか一部値上げしたいとか言ってるみたいなんだけど、そんなことされたら本気で困るからね。――って感じにいろいろ考えてる。ほんとは小説のことだけ考えていたいけど、どうもそうはならない。生きてくってのはそういうものなんだ」
私は胸を押さえた。訊きたいことはもっとあった。でも、言葉が出てくる前に電車が入ってきた。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》