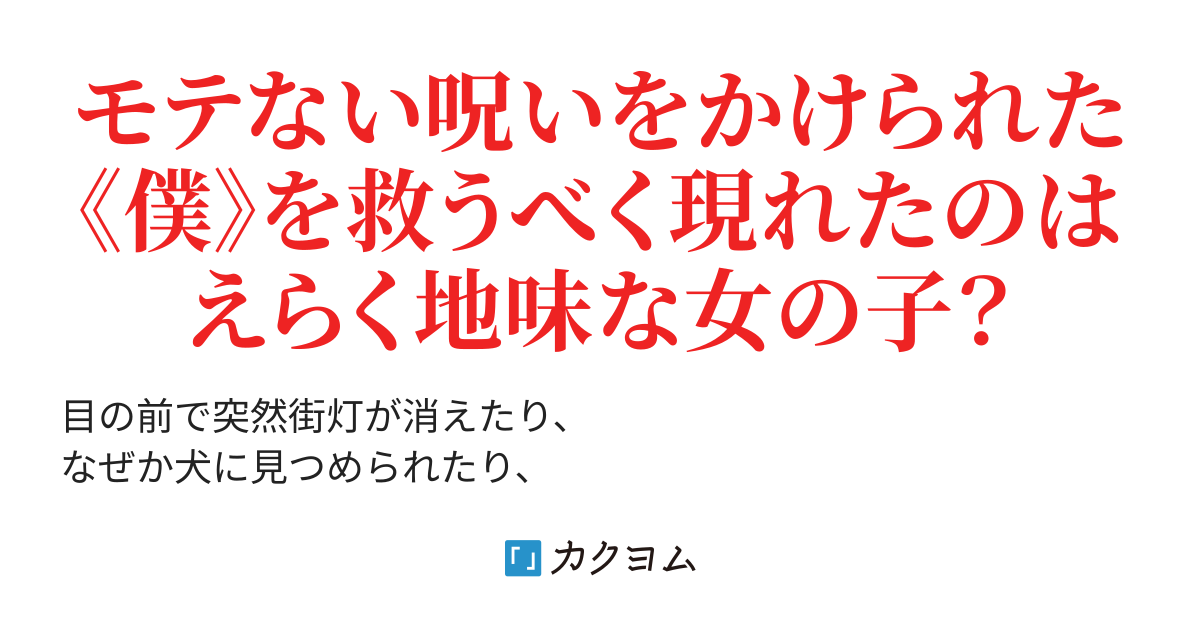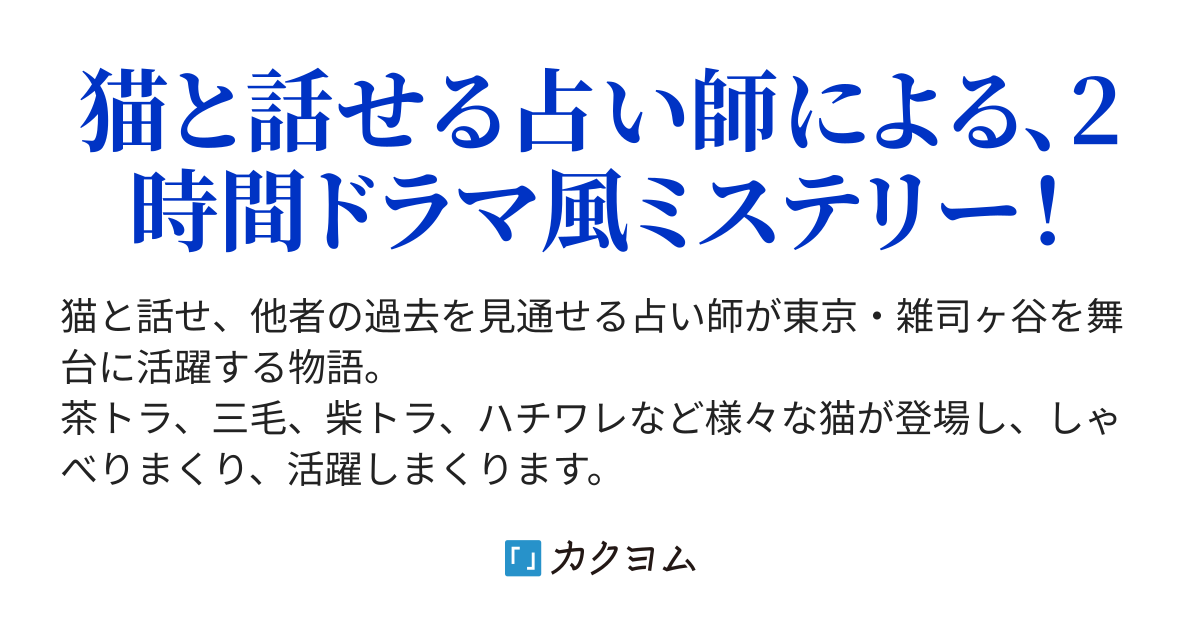◇
『三四郎は長火鉢の前へ坐った。鉄瓶がちんちん鳴っている。婆さんは遠慮をして下女部屋へ引取った。三四郎は胡坐をかいて、鉄瓶に手を翳して、先生の起きるのを待っている。先生は熟睡している。三四郎は静かで好い心持になった。爪で鉄瓶を敲いて見た。熱い湯を茶碗に注いでふうふう吹いて飲んだ。先生は向をむいて寐ている。二、三日前に頭を刈ったと見えて、髪が甚だ短い。髭の端が濃く出ている。鼻も向うを向ている。鼻の穴がすうすういう。安眠だ』
未玖は顎を上向きにさせている。それが気になるようで高槻さんは何度か顔を向けた。その目を見ているとさっき聴いた言葉がふとあらわれた。私のものにしたい。私も彼のものになりたいの。バットがボールを打つ音が聞こえた。大会が終わり、野球部はまた練習をはじめたようだった。
「『そうすると、広田先生がむくりと起きた。首だけ持上げて、三四郎を見た。
「何時来たの」と聞いた。三四郎はもっと寐て御出なさいと勧めた。実際退屈ではなかったのである。先生は、
「いや起る」といって起きた。それから例の如く哲学の烟を吹き始めた。烟が沈黙の間に、棒になって出る。
「有難う。書物を返します」
「ああ。――読んだの」
「読んだけれどもよく解らんです。第一表題が解らんです」
「『ハイドリオタフィア』」
「何の事ですか」
「何の事か僕にも分らない。とにかく希臘語らしいね」
三四郎はあとを尋ねる勇気が抜けてしまった。先生は欠を一つした』
うん、ここはちょっと妙な部分ですね。――いや、失礼。無駄なことを言いました。このまま章の最後まで読んでください」
目はこちらへ向かってる。ゆっくりうなずくと同じようにした。だいたいの者は気づいていないようだった。ただ、私はその後で窓の方を窺った。
「いいでしょうか。では、この部分について話します。――と、その前にさっき口走った妙なことを言っておきますね。いえ、これはとくに重要でもないのですが気になるかと思ったので」
ノートを閉じ、高槻さんは表紙をじっと見つめてる。加藤さんは首を伸ばしかけた。変な間をあけたように感じたのだろう。
「いま読んでもらった最初の方に本を返すシーンがありましたね。そのとき三四郎が『ハイドリオタフィア』というタイトルについて『何の事ですか』と訊いてます。それにたいし広田先生は『とにかく希臘語らしいね』とこたえてます。またかなり前ですが大学の懇親会があったとき与次郎は『ダーター・ファブラ』と言いつづけていました。三四郎がなんのことだと訊くと『希臘語だ』とこたえてます。ところで、この『ダーター・ファブラ』とはなにかというと後注に『他人事ではないの意』とあります。それとラテン語であるとも記されてます。あれ? と思いますよね。与次郎はギリシャ語と言ってるのにほんとはラテン語なんです。ただし、それについても後注は言及しています。与次郎がよく知らずに使ってるのだろうと」
高槻さんは教室を見まわしてる。頬は平坦になっていた。
「与次郎であればそうであってもいいでしょう。しかし、『ハイドリオタフィア』の方は問題です。これはギリシャ語起源の言葉を掛け合わせた造語のようですが、やはりラテン語らしいし、内容も主にラテン語で書かれてるようなんです。まあ、タイトルについて訊かれただけだから勘違いとも思えますが、それでも妙です。そもそもどうしてこんな会話を入れ込んだのかわかりませんよね。しかも『ダーター・ファブラ』については細かな言及のあった後注にもそのことは書かれてません。いえ、これはたいしたことじゃないのかもしれませんよ。しかし、妙なのは確かです。なので読んでもらってる間に考えてみたんですね。まあ、ほんのすこし考えただけなので間違ってるかもしれませんが、僕の考え――いや、思いついたことを言っておこうと思います。ええと、二百五十八ページにこういう文章がありますね。
『門内をちょっと覗込んだ三四郎は、口の内で「ハイドリオタフィア」という字を二度繰返した。この字は三四郎の覚えた外国語のうちで、尤も長い、また尤も六ずかしい言葉の一つであった。意味はまだ分らない。広田先生に聞いて見るつもりでいる。かつて与次郎に尋ねたら、恐らくダーター・ファブラの類だろうといっていた。けれども三四郎から見ると二つの間には大変な違がある。ダーター・ファブラは躍るべき性質のものと思える。ハイドリオタフィアは覚えるのにさえ暇が入る。二返繰り返すと歩調が自から緩慢になる。広田先生の使うために古人が作って置いたような音がする』
これは通勤する広田先生を見た後での三四郎の感想なんですね。ここには『ダーター・ファブラ』と『ハイドリオタフィア』がともに出てきます。で、与次郎はまた適当なことを言ってるわけです。また、こういうところもありました。二百六十一ページです。
『何でこんな六ずかしい書物を自分に貸したものだろうと思った。それから、この六ずかしい書物が、何故解らないながらも、自分の興味を惹くのだろうと思った。最後に広田先生は畢竟ハイドリオタフィアだと思った』
これらの文章が示すのは広田先生は『ハイドリオタフィア』ということですね。そして、それは広田先生が難解であるのを示しています。さらにはその難解な広田先生に三四郎が惹かれているのもわかります。しかし、当の本人はその『ハイドリオタフィア』の意味を正確に理解してないんですね。僕はそこに否定の予感を持ちました。この時点での三四郎は広田先生に興味を持ち、尊敬もしてるのでしょう。ただ漱石は広田先生に間違いを埋め込んでるんですね。これは雲を『雪の粉』と説明する野々宮くんと『雲は雲でなくっちゃいけない』と言う美禰子に視線の違いがあったのと似てるように思えます。その隔たりはわずかなものかもしれない。でも、それはじきに広がり、引き離される可能性がある。美禰子と野々宮くんがそうであったように三四郎も広田先生と距離を置くことになると示してるように思えるんです」
高槻さんは肩をすくめてる。私はその顔を見つめていた。
「いや、これはふと思いついたことですよ。もっと考えなければならない問題なんでしょう。しかし、このように十一章はかなりの部分を広田先生の考察に使ってます。休憩前にはエピローグの推進力として残していたと言いましたが、それだけではないんですね。この章は広田先生のためにあるといってもいいんです。では、なぜそのようにしたかですが、これはある程度必然的なことに思えます。また、物語の構成として考えると非常に巧みだとも思うんです。というのは、すべての登場人物の中で三四郎がはじめに会ったのが、この広田先生なんですね。だから最後にその人物についてページを割いてるんです。しかも、この人には謎が多いんですよ。その謎を完全にではないにせよ述べるための章なんです。つまり、広田先生に関してはこの章で決着をつけようというわけです」
高槻さんは窓の外を見た。私たちも自然と顔を向けていた。ただ、そこには空があるだけだった。
「最初のときに僕はこう言いました。汽車で会う女性は読み手に予感を持たせるものだと。それに、広田先生が出てくる場面にも予感があると言いましたね。三四郎の未来に二つの世界があるのを示してると言ったはずです。漱石は『三つの世界』と書いてますね。過去――故郷の世界と、学問に埋没した世界、それに成功とその象徴である美しい女性のいる世界です。しかし、だったら広田先生はどの世界の住人なんでしょうか? すぐ思いつくのは第二の世界、つまり学問の世界ですね。だけど、広田先生は見識に見合うような活躍をしていません。なにかはしてそうなんですが、簡単には公にしないんですね。それを考えると広田先生は第四の世界にいるように思えます。あらゆるものから遠のき、高いか低いかはわからないけれど、そこから世間を眺めるといった立場です。そして、この章では彼がどうしてそのような立場に身を置くことになったかがにおわされてるんです」
溜息のような音が聞こえてきた。それくらい教室は静かだった。私は息が詰まるような気がした。胸を押さえたくなるほどだった。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》