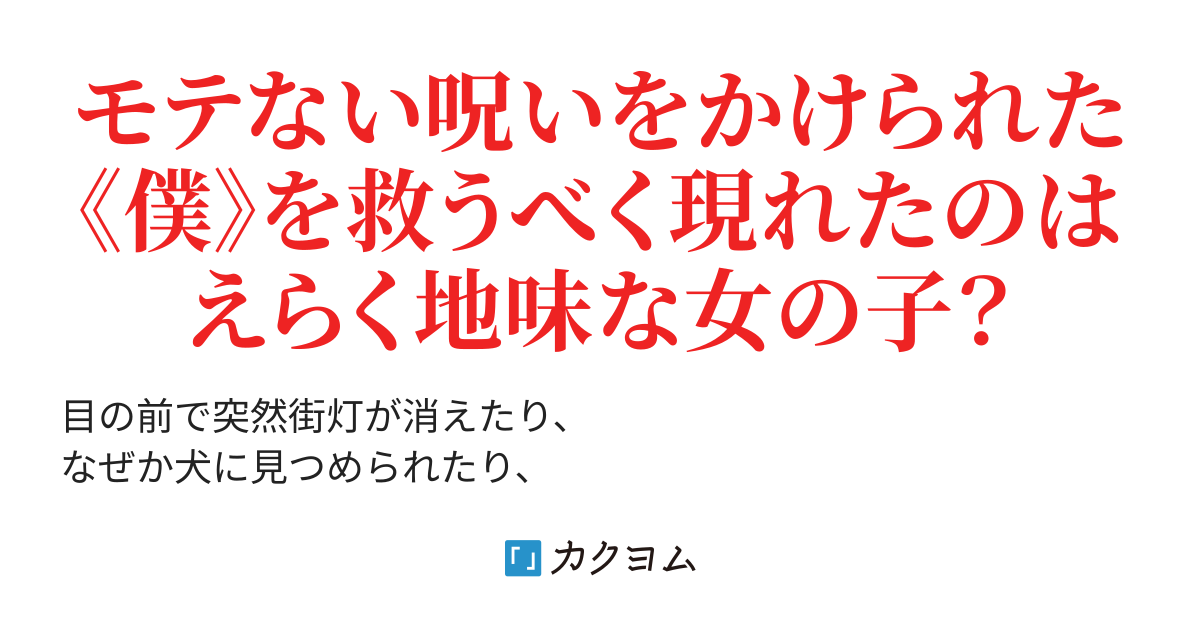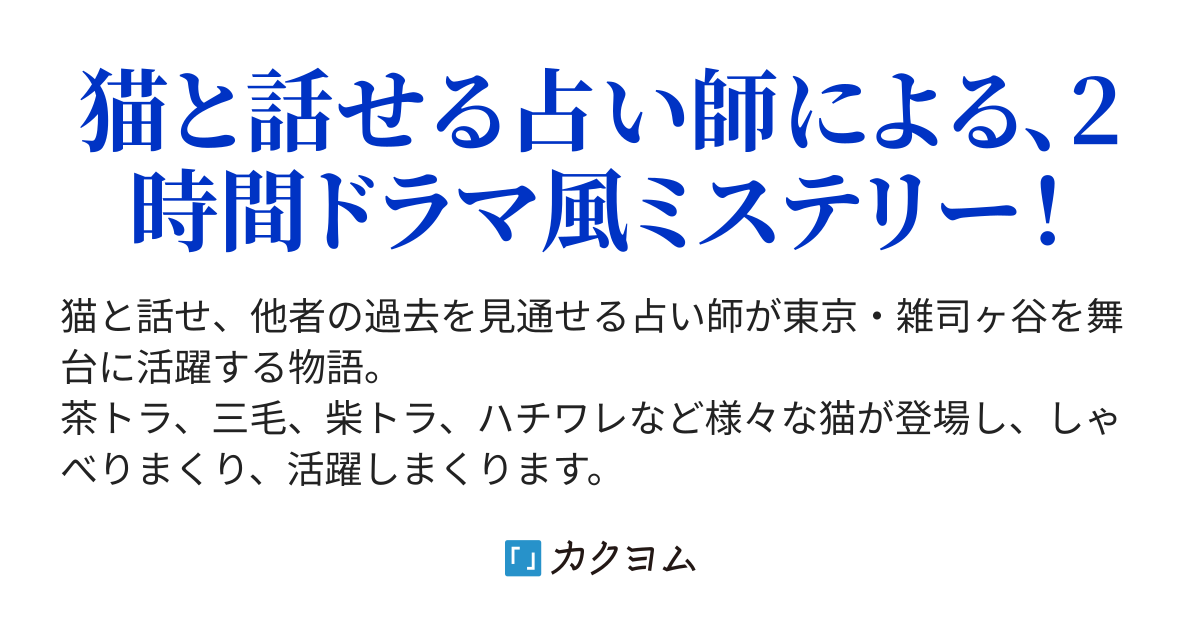コーヒーを飲み終えると亀井くんは財布を取り出した。
「あの、もう帰らなきゃならないんで」
「ああ、そう。――ん? あの人はいくらって言ってた?」
「いえ、順子さんはなにも言ってなくて」
「そう。じゃ、六百円でいいんじゃない。それでもいい?」
「っていうか、それだけでいいんですか?」
「いいと思うよ。いつもそれくらいでしょ」
亀井くんは怪訝そうな顔をしてる。高槻さんは微笑んでいた。
「今日は話したかったことが言えてよかったよ。僕は君の書こうとしてるテーマが好きなんだ。なぜある程度の年齢になると人は誰かを好きになるのか? うん、すごくいいテーマだ」
「はい、ありがとうございます」
「まあ、あまり説明的にならないよう書くんだね。冷淡さを持ってね」
スツールを降り、亀井くんは後ろに立った。
「落合はまだ帰らないのか?」
「帰るけど、順子さんに挨拶だけはしとこうと思って」
「じゃ、俺からもお礼を言っといてくれよ。すごく美味しかったって」
「うん、わかった」
入れ替わりでスーツのおじさんが入ってきた。それからもぽつりぽつりと来客はある。バッグを見つめ、私は弱く息を吐いた。
「大丈夫?」
「え?」
「いや、大丈夫ならいいけど、ちょっと気になったから」
瞳には満月のようなライトが映ってる。それを見ていると本当に夜空を眺めてるような気分になった。不思議な感覚だった。安心できるのとは違ってる。ただ、なにも考えなくていいように思えた。
「大丈夫です。なんでもないんで」
「そう。――ところで、この前から僕たちはこう言いあってるね。『大丈夫?』『大丈夫です』って」
薄く笑い、高槻さんは顔を覆うようにした。ただ、すぐに顎を突き出させた。眉間には皺が寄っている。
「どうかした?」
「いえ、さっきも同じようにしてたなって思って。その、亀井くんが電車に乗ったとき笑ってましたよね? で、それをすぐに隠しませんでした?」
「そんなことしてたかな?」
「してました。私、ちゃんと見てましたから」
「そうだっけ? ――ん? してたかも。いや、落合さんは観察力があるね」
「どうしてあのとき笑ったんです?」
「うーん、ちょっと言いづらいんだけどさ、亀井くんは電車に乗ったとき『なんだかそうした方がいいと思って』みたいなこと言ってたろ。それで笑ったんだよ。あのとき亀井くんはああすべきだった。そしてその場合に起こるストーリーを思い描いた。ただ、落合さんから非常に素直な質問をされたから言葉に詰まったんだね。それでああいうふうに口走った。――わかる?」
私は首を振った。鼻の脇を掻きながら高槻さんも同じようにしてる。
「またも悪い癖だ。どうもいけないね。言動から動機を探る癖がついてるんだよ。とくに君たちと関わるようになってからその傾向が強くなったようだ。こんなこと話したっていいことなんかない」
「だけど、ちゃんと言って欲しいです」
「そう? うーん、そうだなぁ、『三四郎』にこういうのがあったろ? 索引のついてる人の心さえあててみようとしない。今の落合さんはまさにそういう状態なんだよ。でも、観察力のある落合さんならわかるんじゃない? 一連のことがなにを示してるか。――って、その顔は納得してないってこと? それとも別に訊きたいことがあるの?」
「両方です」
「じゃ、お聴きしましょうか。なんでしょう?」
私はニヤついた顔を見つめた。馬鹿にしてる。子供扱いしてるんだ。
「これは文学についての質問です。先生は経験だけで書かれた小説は嫌いだって言ってましたけど、どんなものにも経験は含まれてるって言ってましたよね? で、訊きたいんですけど経験ってどれくらい入ってるものなんですか? たとえば『三四郎』に漱石の経験はどれくらい入ってると思います?」
「ああ、なるほど。それは確かに文学に関する質問だ。そうだね、『三四郎』に経験が含まれてたとしてもそれは非常に少ないんじゃないかな。まあ、広田先生を教授にする運動なんかには含まれてるだろうし、大学で三四郎が見聞きすることなんかも経験の可能性はある。ただ、美禰子との恋はご本人の経験じゃない。あれは弟子から聴いた話に想像を足したものらしいんだ。でも、僕はそれを詳しく知りたいとは思わない」
「なんで知りたいと思わないんです?」
「知ったところでなにもならないからさ。小説の中に書かれてることだけで充分ってことでもある。そうだな、――いや、これは仲間内の話で落合さんに向かって言うのはどうかと思うけど、」
「はあ」と私は言った。そういう間をおかれたのだ。
「たとえば君に『いま何色のパンツはいてるの?』と訊くとする」
「え?」
「そういう反応になるよね。恥ずかしいし、そもそも無意味な問いだ。君が何色のパンツをはいてようが僕には関係無い。ま、若干だけは興味があるけどね」
口を尖らせ、私は首を引いた。身体の奥には痼りができている。それは脈打ち、火照っていた。
「小説の中に経験がどれくらい含まれてるか考えたり、作家の生い立ちなんかを知って、だからこういう文章を書いたんだろうって考えるのは人のはいてるパンツを気にするようなものなんだよ。それこそ若干ばかりの興味を満たすだけのことさ。書き手は小説の中にすべてを注ぎ込んでるんだ。それを受け取るだけで充分だ。それにね、経験を中心に据えてるようなものは自己満足にすぎない。日記を読まされてるようなもんだ。そんなのは小説とはいえないんだよ」
顔をあげ、高槻さんは会計に向かった。私は壁の時計を見ながら溜息をついた。高槻さんと同じだ。どこかズレてる。
誰もいなくなると高槻さんは厨房に籠もった。鈍く水音が聞こえてる。
「今度は僕が質問してもいい?」
「なんですか?」
「うちの母親が出てったとき、なんか気にしてなかった? なんでもないならいいけど、ちょっと気になったんでね」
深く座り直し、私はどうこたえるか考えた。日は急に翳ったようだ。床の影も弱くなり、斑になっている。
「はい、これは僕からの奢りだ。それとこれにはオマケが付いてるんだ。ここにはあまり子供が来ないからね。特別サービスとしてこういうのを付けてるんだよ」
指にはフェルトでつくられたウサギがぶら下がっている。私はそれとニヤついた顔を交互に見た。
「あの、私はそこまで子供じゃないんですけど」
「じゃ、要らない?」
「いえ、一応はもらっておきます」
「そうしてよ。それもうちの母親がつくってるんだ。いじましい努力だろ? どうにかして店を盛り立てようとしてる。ま、あまりうまくいってないけどね」
「でも、今日は混んでたじゃないですか」
「これで?」
高槻さんはお店を見渡してる。指は窓へ向けていた。
「あの花も母親がやってるんだ。いじましい努力その二ってわけだ。――で、さっきの質問なんだけど、なんかあった?」
「いえ、よくわからないんですけど、ちょっと様子が違ってたというか、あの、私、憧れてますって言ったんですね。そしたら、私みたいな人間に憧れちゃいけないって。そのときの顔がすこし気になったから」
「なるほど、そうか」
「私、なにか悪いこと言いました?」
「いや、気にすることはないよ。忘れてもらっていい」
「はあ」
煙草を抜き取り、高槻さんは覗きこんできた。
「喫ってもいい?」
「はい」
「じゃ、お言葉に甘えて」
火が一瞬の明かりをみせた。外は灰色に濁ってる。鈍い音も聞こえてきた。遠雷だ。
「もうひとつ訊いてもいい?」
「はい、なんですか?」
「落合さんは亀井くんのことどう思ってるの?」
「え?」
「ほら、さっき言った一連のことだよ。それに、小説を渡されたろ? あれはきっとラブレターのつもりなんだよ。新井田さんと同じとは思わないけどそういうことだと思う。まあ、あれを聞いてそういう手もあるのかと思ったのかもね。内容からするとそうも考えられる」
煙草の先を私は見つめていた。灰が伸びてるところをだ。それはいまにも零れ落ちそうになっている。
「さっき彼に言ったのは、――そうだな、その後の方だけど、つまり、感情を抑制してって言ったのは違うふうに書いてもらいたいからなんだよ。僕も気づかなかったんだ。でも、ここのところの展開でわかるようになってきた。彼はあの中で希望を実現させようとしてるんだ。経験したことじゃなく、したいことを書いてるってことだよ。それはちょっとばかり危険に思える。しかもそのために傷つく人間が出てくるかもしれない。そうなって欲しくないんだ。誰も傷つけて欲しくないし、その誰かが傷つくのを見るてのはつらい」
「それで?」
灰は落ちた。私はそれが落下する様を見ていた。高槻さんも零れた灰を見てるようだった。
「それで、――その、なんて言ったらいいかわからないけど、このまま進んだら良くないことが起こるような気がするんだ。小説の中だけじゃ済まないことになるんじゃないかってね」
「どういうことですか?」
そう訊いたとき、奥のドアがひらいた。私は胸を押さえた。自然とそうなっていたのだ。
「昴平、雷がきたわ。雨もひどく降って、――あら、あの子は帰ったの?」
「ん? ああ、塾があるんだってさ」
「そう。結月ちゃん、傘持ってる? って、持ってるわけないか。ま、通り雨でしょうからじきにやむとは思うけど」
順子さんは窓へ向かった。腕を組み、雨が降るのを眺めてるようだった。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》