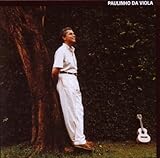Paulinho Da Viola / "Eu Canto Samba"
確信は尊い
そう思うのは
潔い心地の目に宿るものが
永遠につながる野生のいのちの
覚悟を秘めているからだ
こんこんと続く人の世で
何も成さなかった人が
その本当の痛みを知った事があったか
その本当の苦味を知った事があったか
吐き捨てたくなるほどのお世辞なら
15分の出会いこそが重要ではないか
言葉などはどうでもいい
覚悟を光らせる行動が欲しい
やっぱり月は昇っていて
日増しに風は暖かくなる
こんなに早く一日が過ぎる
時間の列車は待ってはくれない
誰が何を成し遂げるのか
眺めている余裕など毛頭ないのだ
風を読む暇を捨てなければならないなら
素直に動く4つの体と引き換えに
僕は甘んじてその暇を捨て去ろう
美しい声と地べたに転がる歌
そんな音楽が聞きたかった
土を払い落とし丁寧に磨き
広い空間に置いておくと
何でも無いものが美しく見える
拾い上げる面白さ
美しさ
自作がほとんどとは言え
これだけの歌声の持ち主が
地面の下の砂だらけになった
サンバを歌う
ブラジル音楽の豊穣な土壌を
まざまざと見せつけられた様な傑作だ
サンバも音楽の成立としては
ブルーズに似たものがある
大衆音楽としての側面を持ちながら
裏山では数々の知られざる歌い手によって
陽の目を見ない曲が数多く存在したと言う
そんな精神性が
パウリーニョ・ダ・ヴィオラの歌には
棲みついているようだ
アレンジが美しいこのアルバムは
パウリーニョ・ダ・ヴィオラの歌声と
その生命力に溢れた曲の数々
これらが最大の聞き所だと思う
89年の録音ながら
時代におもねったところが一つも無い
まっすぐにサンバを歌っている
その気概がまた美しいのだ
こんな風に歌う事ができれば
毎日の残り糟なんて
どこかへ吹き飛んでいくのだろうか
"Everything Happens to Me" 聞き比べ考
マット・デニスの
"Everything Happens to Me"を
聞き比べしている
きっかけはソニーから出ている
1000円シリーズのバルネ・ウィラン
この盤はどちらかというと
ハードバップの申し子と言うべき
ケニー・ドーハムと
透明度のあるトーンで弾きまくる
デューク・ジョーダンの二人に
バルネが引っ張られるような演奏である
全体的にテンションは高めなのだが
ボーナストラックとして収められている
"Everything Happens to Me"
これがなかなか渋く聞かせてくれた
本当はじっくりとバラードで料理する曲だが
少しスウィングテンポでやったのが良かった
こんな良い曲だったかと
色々な人の聴き比べをやってみた
まずはソニー・ロリンズのインパルス盤
"On Impulse!"に収録されたもの
さすがはロリンズ、堂々の風格
11分もの長さだが曲をあっちへこっちへと
多彩な旋律をもって飽きさせない
でも好みで言うと少し男っぽすぎる
骨がありすぎるというか
この曲を演奏するには逞しすぎるのだ
では女性っぽいのがいいのかと思い
チェット・ベイカーの同曲を聴く


チェットはこの曲、十八番のようで
自伝映画レッツ・ゲット・ロストの
サントラでも取り上げている
59年のリバーサイド盤はうら若きチェット
ロマンチックで水が滴る
やはりチェットが歌うこの歌には
説得力があった
サントラ盤の方はどうかと言うと
曲の枯れ方が凄まじい
これほど甘酸っぱい曲が
ここまで枯れてしまうのかと思うほど
歌が成熟している
ここまでくると切ないと言うよりも
むしろ達観の様なものを感じる
冒頭のバルネ盤でも
ピアノを弾いているデューク・ジョーダン
さすがと言うべき解釈
切ないフレーズがどんどん出てくる
甘いと言えば甘い
しかしこれこそジョーダンの真骨頂
と言いたい
賛否両論はあると思うが
僕はこの演奏、大いに結構
スタン・ゲッツは51年のライブで取り上げている
良くも悪くも曲に淡白なこの人は
原曲を上回る歌心で聞かせてしまうだけに
テーマの演奏はとてもドライ
ジョーダンとは対極の解釈だ
僕はこの曲にドラマが欲しいので
少しもったいない演奏だとは思うが
ゲッツの音色はワン・アンド・オンリー
どうしようにもジャズになってしまう
- エイプリル・イン・パリ~チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス+4/
- ユニバーサル ミュージック クラシック

最後はパーカー
少々大げさなストリングスのイントロの後に
パーカーが一くさりテーマを奏でる
これがねっとりと素晴らしい
文句の付けようが無いテーマである
パーカーは曲の押し引きを知っていて
こうすればドラマティックに聞こえる
というツボと言うツボを押さえているから
どんな曲も感動的に聞こえる
アドリブはほとんどない
パーカーはテーマを何度か吹くだけである
しかしこの曲には
ポップス史に永遠に残る美しいメロディがある
これをパーカーのあの音色に吹かせれば
極上の一品ができると考えた
プロデューサーは偉いと思う
結論としては
パーカーの演奏がもっとも良かった
これだけの名演が出るということは
やはりこの曲は名スタンダードである
と再認識した
Bud Powell / "Strictly Powell"
もうすぐ春だと言うのに街に出ると
みんな袋小路に入った顔をしている
動脈の血流が詰まってきて
ゲートルを履いた足を引きずって
ただただ寒さが過ぎるのを待っている
受ける事に慣れてしまうと
ボールの投げ方を忘れてしまう
捕手が投手に返球するのは
自分の投げ方を思い出すためだ
投手に主導権を握らせているのではない
ましてや
投げた球の行方など
思い通りにさせてなるものか
本屋に並んだ処世術に
うつつをぬかしている前に
自分の表現を全うしたかと
腹の中の声に問え
蝉が死んで行く時すら
心の内の自分に大音声で語りかける
何を開いたとて定かではない
得体の知れない正体が相手なのだ
存分に喚き、嘆き、のた打ち回り
拾い上げたものにため息をつくこと
全てが己に始まり、己に終わる
情念を掬い上げろ
丹念に凍りつくような水で洗い流し
岩のように硬い地面に打ち付け
ささくれだらけの表面から
にじみ出した濃厚な苦味こそが
誰のものでもない
真に独創的な表現なのだ
接してすぐにわかる様なものなら
端からそんな物は捨てても構わない
安売りされた安直な苦味に
決して騙されるな
誰の間に音楽が存在しても
そこには必ず出会いの喜びがある
甘い笑顔もあれば変な緊張もある
渦を巻いている感情が音楽を通して
ポロポロとこぼれだしたもの
僕はそれが美しいと思う
素晴らしい音楽だと思う
バド・パウエルのピアノは
聞いた時にひれ伏してしまうように
人間の回路ができているのではないか
どこまでも重たく重たくスウィングし
ジャズという大衆性を真っ向から否定する
ピアノの神様は表裏一体の悪魔で
本当はピアノと言う楽器を
恨んでいたのではないかとも思う
RCA時代に出たこのレコードは
そのバラッドに深い価値がある
"I Cover The Waterfront"
"Lush Life"といったスタンダードが
パウエルの両手を通してどんどん重たくなり
果ては曲そのものが鉛のようになる
パウエルがバラッドに何を託したか知る由も無いが
驚くべきはこれだけの深遠な演奏にも関わらず
言いたいことを言い切った清々しさが
全編に充満している
この清々しさのおかげで
なんとかジャズしての面目を保っているようだ
バート・ゴールドブラットのジャケット写真
そんな彼の全てを
物語っているように思えてならない