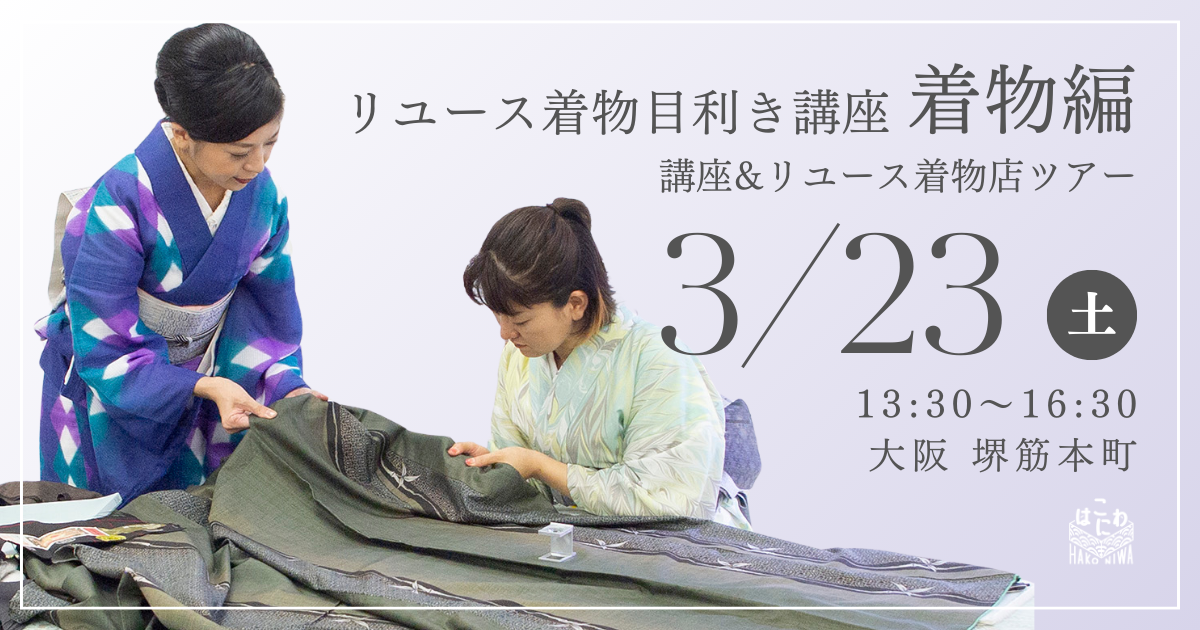京都の着付け教室 きものシャン
レッスン会場:烏丸御池教室 (京都市営地下鉄烏丸御池駅すぐ)
当教室についてはこちら→レッスンメニュー
京都市内・公共交通機関の範囲でしたら 出張レッスンもお受けしております^^
お知らせ
レッスン募集状況については必ずこちらもご覧ください。
⚫︎レッスンご予約受付中
※ただいま新規のご依頼は、平日のみ受け付けております。
10:45-12:15 または 13:45-15:15
1レッスン 90分
(ご希望の日時をご相談ください。)
土曜日曜祝日のレッスンは現在満席が続いており、新規の募集は再来年度から行います。
※2024年の7月および8月のレッスン開講はございません。
(講座やイベントの開催はございます。)
予約先着順で埋まってゆきますので、はやめのご予約をお願いいたします。
ドアノブや机類など室内のアルコール除菌、また換気も徹底しております。
講師はマクスを着用いたします。
↑当教室に資料として置いてある自然布の本です。
別冊太陽には、もうひとつ新しいバージョンがあり、「日本の自然布」というタイトルで、吉岡幸雄氏と、コレクターの吉田真一郎氏がまとめられています。
これも持っていたはずなのですが、見当たらず...
自然布とは
新しい情報については、こちらの日本の自然布(宵衣堂 小野健太氏)も参考にしながら説明してゆきます。
まずはじめに、自然布(しぜんふ)とは、草の茎の皮や、木の皮から採った繊維を用いた布を指します。
草木布(そうもくふ)、原始布(げんしふ)と呼ばれることもあり、1989年の別冊太陽では、この「原始布」の言葉が使われており、2003年版では、「自然布」という言葉が使われています。
厳密にいうと、原始布には、木綿や紬織物など原始ではない(笑)ものは含まれませんから、自然布とは、より幅広い枠組みでの、近代化以前の手仕事の布を指しているとも言えます。
着物業界(流通)のなかでの感覚だと、自然布とは、木綿や麻、絹織物以外の、植物原料の手織物を指すと思いますので、この記事の中でも、自然布と呼ぶことにします。
自然布の糸は、緯糸のみに用いる場合と、経糸・緯糸共に用いる場合がありますが、北から俯瞰すると、
・アットゥシ織
・榀布(しなふ)
・葛布(くずふ)
・藤布(ふじふ)
・太布(たふ)
・芭蕉布(ばしょうふ)
などがあります。
など、と言うのはどっからどこまでを自然布と言うのか場合によると思いますので、あくまでも着物流通における感覚で分けました。
さて、いまここに上げた自然布のなかで、自分の仕事として唯一仕入れ・販売経験のあるのが、芭蕉布でした。
それ以外は、作り手さんとの繋がりがあるものもありますし、見て触れたことはありますが、仕事での関わりが少なく、それゆえ着付け講師としてもなかなかフォロー出来ていないのが現状。
ただ1989年版の別冊太陽を手にした時期は早く、自分の興味として読んでいましたので、付録についている榀布には馴染みがありました。
榀布について
この牛首を染めてもらった際に、この生地の地厚でワイルドな感じ、あ、榀布が合う、と
閃いたのです。
・原料のしな皮は、「しな煮」、「しなこき」、「しな漬け」を行うこと。
・しな皮を幅三ミリメートル程度に裂き、撚りをかけながら手作業で糸状に績むこと。
・経糸にあっては五から八回程度、緯糸にあっては二から三回程度糸車を回転させて糸に撚りをかけること。
榀布ができるまで
※別冊太陽 日本の布 原始布探訪より
この時点では、めっちゃ木ですね。
ことあと、繊維を柔らかくするために大量の木灰で煮ます。洗った後、「しな漬け」と呼ばれる作業で、繊維の色を白く戻すためと柔らかくするために数日間「糠漬け」にされます!
※別冊太陽 日本の布 原始布探訪より
この後は、繊維を割きながら、指先で繊維を撚りながら繋いで糸にします。
さらに糸車をつかい、撚りかけ(糸に撚りをかけること)をして、機ごしらえをし、高機で織り上げます。
大変に根気のいる、キツイ仕事だと思いますが、山の暮らしにおける「生きる知恵と文化」を現代に残す織物であると言えます。
まさに牛首の産地である白山の山の暮らしともリンクして、コーディネートに選んだ、という背景もあります。
榀布の品質
榀布の特徴としてあげられるのは、まず強靭であること。さらに撥水、耐腐食性があるため、野良着、漁網、漉し布、敷布や収納袋として流通していました。
そんな特徴の榀布ですので、帯とした時に結びやすいのか?また品質差はあるのか?どんな榀布が良いのか?伝統的工芸品以外もあるなら何を選ぶ?という疑問も着物ファンのなかには生まれてきそうですね。
手仕事のことですから、個体差はありそうですし、やはり帯として良いと思うもの、気に入るものを素直に選ぶのが良いと思います。
ただ、見比べないとなんとも言えませんので、初めての方は、実物を目の前にして検討する時間があったほうがいいのかなと思います。
もちろん流通数のそれほど多くない自然布である榀布を1箇所で大量に見比べるなんてことはできませんので、問屋さんや、呉服屋さんにて目にした際に、私もチェックしていました。
いま流通しているもののなかに、伝統的工芸品指定のものだけでなく、他の地域の工房で織られているものや、ラオス産の榀布もありました。
染織技術の高いラオス。私自身、西陣織や京縫(刺繍)の見学にラオスの方をご案内したこともあります。
日本の帯用にラオス産の榀布の八寸が京都の商社さんによって出ているので、室町エリアで見ることが出来ます。お値段も国産の半額ほど。
単純に製造地域が違うだけというよりは、植物や繊維にする過程の方法も違うのではないかと思います。
素朴で優しい表情の織物でしたが、自分にとって「おっ」と感じるインパクトはありませんでした。
しかしその他もラオス産の糸や織物は素晴らしいのでまた改めて。ゆっくり機会を作って楽しみお伝えできればと思います。
その他、呉服屋さんでも国産の八寸を見せてもらいましたが、こちらはかなりワイルドな織で、好みとしては「もう少しきれいに織り上げられていた方が私はいいな笑」という感じでした。
売り切り特価ということでかなりお安くなっており、さっそくネットで売れたとのことで、それ以上に詳しくは見られませんでした。
(購入者が決まったものを、もっと見せてくれとは言えませんので ^^;)
まあこうやって、いろいろ見てみるといいですね。
最終的に自分が気に入ったものを買えばいいのだから。ということで納得して、こちらに決めました。
しなやかで、織も丁寧で、シンプルな平織りの良さが出ています。こういう織物の場合、捩りよりも平織りの方が組織の安定もあるので、自分が求めている質感と存在感でした。
ちなみに私は今回平織りのキナリ無地が希望だったのですが、榀布には、捩り織などデザインされたものもあります。
なお、しなやかと言ってもやはり固さのある繊維で織られたもののため、擦れによるダメージを気にする必要のある繊細な着物にこういう帯はNGです。
とっくに無くなっていたはずの
自然布、全体的に共通して言えることかと思いますが、現在でも継続して製造されていることに驚きます。
継続されたのはひとえに、「残してゆきたい」と強く願う外部からの力によるものです。
単純に需要と供給、現地の人々の生活に必要であるかどうかだけの問題であれば、とっくの大昔に無くなっていたでしょう。
希少性をありがたがるとか、そういうことではなく、残っているものから何を学ぶか、10人いたら10人皆それぞれの目線での考察が生まれそうなトピックだと思います。
それくらいに、多くの現代日本人からすると、自然布は生活からかけ離れた異次元のものだと言えます。
榀布に会いに
ご興味のある方はぜひ!