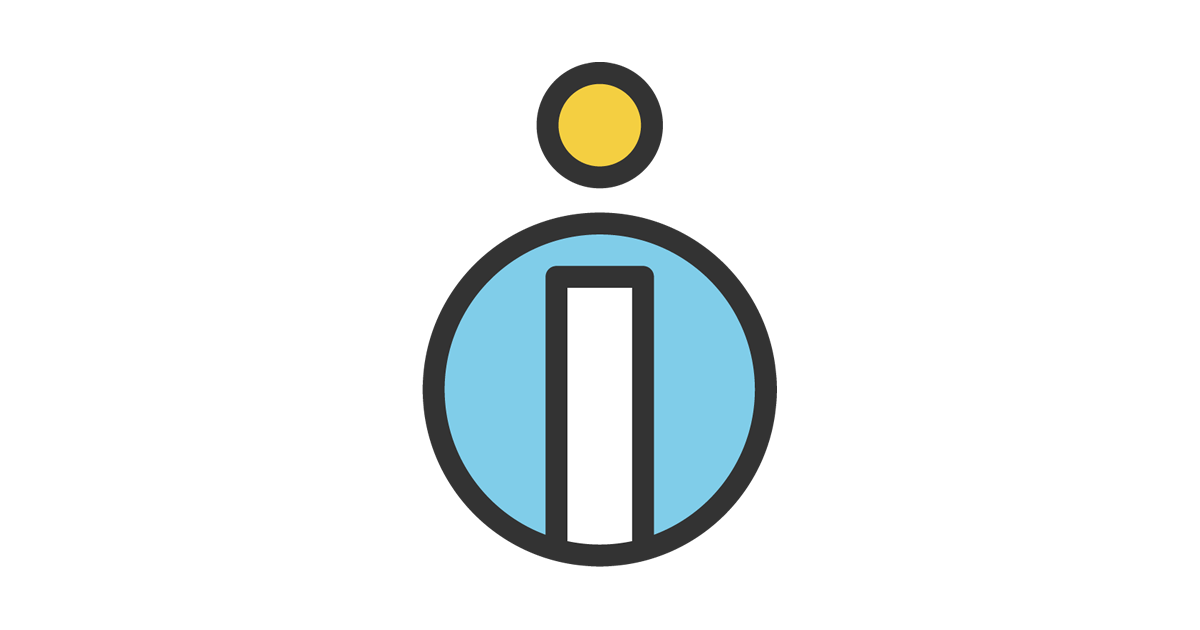読んでみました![]()
一番、耳が痛かったのは、
子どもがいやがるからという理由で、簡単に学習を中断する母親がいるが、わが子に学力をつけることよりも、子どもの感情や意見を尊重するのか?
子どもがいやがろうと、必要最低限の学力をつけることは親としての義務である。
生身の人間だから、機械のように規則正しく、一定のペースで進みつづけることは困難。
子どが勉強を怠けたり、成績が上げられなかったりすると、親はすぐ子どもを叱るが、その責任は教育者や親にある。
おっしゃる通りです![]()
うちの場合、子どもたちは決してて公文式の学習をやめたいとは言っていません。
やめたいと言ったことは、一度もありません。
むしろ、やめたくない!!!と言っています。
それなのに、私は、毎日の親子バトルが辛いという理由で、子どもたちから公文式を取り上げようとしていたのです。
ホント、ダメな親...![]()
この本に書かれていた名言、ある公文式の教室の先生の言葉です。
自分の学年をやっている子は、今は自分のことだけに集中していればいい。
1学年上まで進んだ子は、学校のクラス全員約30人のことを考えられるようになってほしい。
2学年上まで進んだ子は、30人の2乗で900人のことを考えられるようになってほしい。
3学年上まで進んだ子は、30の3乗で2万7000人のことを考えられるようになってほしい。
そして最終教材を終えた子は、世界中の人のことを考えられるようになってほしい。
つまり、学年を超えて学習している子は、それだけ優秀であり、多くの人たちのリーダーになってほしいということです。
娘たちは、それぞれ学年を超えた学習に取り組んでいます。
それは、すごいことのはず。
よその子であれば、
「〇〇教材にあがれたんだよ~!」と言われたとき、
「すごいね!!! 頑張ってるんだね![]() 」
」
と、素直に褒めることができます。
なのに、自分の子になると、そんな声掛けはできません。
なぜだろう...???![]()
![]()
![]()
ダメだなぁ![]()
また、別のベテラン塾講師はこう語っています。
公文式をやっていたというからには、最低でも3学年は上位の進度である必要がある。
それ以下の場合は、『触れていただけ』とみなすべき。
き、厳しいお言葉![]()
この3学年先というのが、結構、大変![]()
公文式には1年に1回トロフィーをもらえるチャンスがあります。
3月末の時点で、自分の学年よりも3学年以上先の教材に進んでいる生徒は、「高進度学習者」と表彰されて、トロフィーがもらえます![]()
長女は、1年生の頃、英語のトロフィーを、
次女は、幼稚園の年長の頃、算数のトロフィーをもらいました![]()
昨年度(2023年3月)、長女は国語もギリギリ3学年先まで進んだので、今回は英語と国語を、
次女は昨年に続き、算数でトロフィーをもらえる予定です。
3学年先の教材をやっている娘たちのことを、もっとリスペクトするべきなのに...
ガミガミ言うだけではなく、すごいことをやってるんだ!って思って接すれば、こっちのイライラも少しは減るのかな。
さらに、小学校中学年で最低でも中学教材を修了させ、その後の公文式は英語のみに切り替え、算国理社は進学塾に任せる
と書かれていました。
なるほど![]()
って、長女はもう中学年じゃないかーーーっ![]()
確かに、それが理想です。
もう少し、頑張ってみるかな、そんな風に思えたので、読んでよかったです![]()
ちなみにタイトルの感想ですが、東大生に限らず、私の感覚的には子どもたちの周りも3人に1人は公文式に通っているイメージです![]()
![]() なぜ、東大生の3人に1人が公文式なのか?
なぜ、東大生の3人に1人が公文式なのか?![]()
◆目次
第1章 東大生の3人に1人は公文式出身
・小6で因数分解、5歳で受動態の否定文
・公文式は「塾歴社会」への登龍門!?
・「やってて良かった!」現役東大生座談会
・公文式の先生が中学受験を勧めてくれた
・公文式の「紹介」で私立中高一貫校に進学
・グローバル人材育成にも公文式!?
第2章 なぜ月6000円で学力が伸びるのか?
・教室の中では「聖徳太子」状態の指導者
・算数・数学のプリントは全5470枚
・「ちょうど」の見極めが肝
・文章題や図形問題はあえてやらない
・『戦争と平和』まで読めるようにする
・「E-Pencil」導入で英語の受講者が急増
・ビッグデータ解析で教材を改定
・世界中の人のことを考えられる人になってほしい
・本部に支払うロイヤリティは75%から40%
第3章 1枚のルーズリーフから始まった
・高校の数学教師だった創始者・公文公
・小6で微積分を終えた息子・毅
・『公文式算数の秘密』がベストセラー
・アメリカ公立小学校「サミトンの奇跡」
・学習者数約427万人、売上900億4300万円
・スイスに作ったボーディングスクール
・初年度から東大合格者6名を出した公文国際学園
・人間の可能性を追求し続けた公文公
・創始者親子の死去と新生「KUMON」の誕生
・大学入試改革、人工知能、そして共働き
第4章 速く進む子と続かない子の差は何か?
・学習習慣を身に付け学力の貯金をするのが目的
・中学受験に活用、スポーツとの両立にも活用
・ひらがなを見るのも嫌いになってしまう子も
・進むかどうかは子供の能力、続くかどうかは保護者の姿勢
・神童の中にも公文式が合わない子供はいる
・名門校の生徒は早めに公文式をやめている!?
・公文式の算数・数学は劇薬のような勉強法
・3学年以上進んでいないと意味がない
第5章 つるかめ算は本当に不要なのか?
・「黒表紙教科書」と公文式の共通点
・学研教室と公文式は似て非なるもの
・公文式に対する明確なアンチテーゼ
・「幼児方程式」への社会的批判と方向転換
・公文式で身に付く、「計算力」より価値あるもの
・公文式の3つの弊害とは?
・大切なのは「やる・やらない」より「目的と理由」
◆著者紹介 おおたとしまさ
育児・教育ジャーナリスト。1973年東京生まれ。麻布中学・高校卒業。東京外国語大学英米語学科中退。上智大学英語学科卒業。リクルートから独立後、数々の育児・教育誌のデスクや監修を歴任。学校や塾、保護者の現状に詳しく、各種メディアへの寄稿、コメント掲載、出演も多数。心理カウンセラーの資格、中高の教員免許、小学校教員の経験もある。著書は『名門校とは何か?』(朝日新聞出版)、『ルポ塾歴社会』(幻冬舎)、『追いつめる親』(毎日新聞出版)、『中学受験という選択』(日本経済新聞出版社)など。