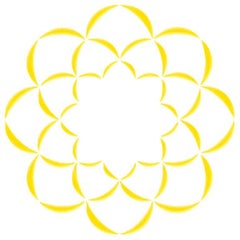『御書全集・・・・1117㌻18行目~1118㌻2行目
編年体御書・・・・・485㌻18行目~486㌻2行目
【本文】
法華経の信心を・とをし給へ・火をきるに・やす(休)みぬれば火をえず、強盛の大信力をいだして法華宗の四条金吾(しじょうきんご)・四条金吾と鎌倉中の上下万人(じょうげばんにん) 乃至(ないし) 日本国の一切衆生の口にうたはれ給へ
【通解】
法華経の信心を貫き通しなさい。火を起こすのに、途中で休んでしまえば、火を得ることができない。
強盛な大信力を出(いだ)して、法華宗の四条金吾、四条金吾と、鎌倉中の上下万人をはじめとして、日本国のすべての人の口に褒め称えられていきなさい。
【語句解説】
火をきる 火きり棒などの道具を使って、摩擦熱で火を起こすこと。
信力 仏法を信じる心の強さのこと。
【拝読御書の背景と大意】
本抄は、日蓮大聖人が佐渡流罪中に、鎌倉の門下の中心者である四条金吾に送られたお手紙で、別名を「煩悩即菩提御書(ぼんのうそくぼだいごしょ)」といいます。御執筆の時期は、文永9年(1272年)5月と伝えられてきましたが、翌文永10年5月とも考えられます。
大聖人が竜の口の法難、佐渡流罪という最大の難に遭われるなか、大聖人の門下も、さまざまな迫害を受け、その多くが退転しました。大聖人は文永9年2月、大難と戦う弟子たちの勝利を願い、末法の御本仏としての大境涯を認(したた)めた「開目抄(かいもくしょう)」を門下一同に与えられます。この大難の中、一歩も退くことなく戦い抜いたのが四条金吾でした。
本抄の冒頭で大聖人は、常に師を支え、守ってきた金吾の志に感謝され、「法華経の行者(ぎょうじゃ)」として大難に遭うことは喜ばしいことであり、これによって生死の苦悩の束縛を断ち切って、成仏の大境涯を得られるのであると述べられています。
そして大聖人が説かれる「南無妙法蓮華経」は、わずか七字(しちじ)であるが、天台・伝教の法門より一重(いちじゅう)立ち入った深い法門であるとされ、南無妙法蓮華経こそ、あらゆる仏を成仏させた究極の法であり、一切衆生の仏性を開く根源の法であると教えられています。最後に、どこまでも弛(たゆ)むことなく信心を貫き、「強盛な大信力」を奮い起こして、「法華宗の四条金吾・四条金吾」と国中から称えられる存在となっていくよう励まされています。
自分自身の「栄光の山」へ
この御文で日蓮大聖人は、「法華経の行者」の具体的な実践を示されています。
冒頭の〝法華経の信心をとおす〟とは「持続の信心」のことで、いかなる時も御本尊を信じ、祈りを貫き通すことです。大聖人はそのことを、道具を使い、摩擦によって火を起こす例えで教えられています。
火を起こそうとしても、手を休めてしまえばつかないように、途中で手を抜き、諦めてしまうことは人生の敗北に通じます。いかなる状況でも、粘り強く挑戦を続けていくなかで一生成仏の境涯を開き、勝利することができるのです。
続いて大聖人は、「強盛の大信力をいだして」と呼び掛けられています。強盛な信力・行力を奮い起こしていく時、偉大な仏力・法力が現れてきます。大聖人は、その強盛な信力をもって「法華宗の四条金吾・四条金吾」と、周囲から信頼される存在になっていきなさいと仰せです。
私たちで言えば、「創価学会の○○さん」と地域の人々から称賛される存在になっていくことです。仏法を実践する私たちが、現実の人生と生活に勝利し、周囲から信頼されてこそ、仏法の力が証明されます。事実、世界192カ国・地域に広がる創価の連帯も、各国・各地域の同志が、あらゆる非難や中傷にも負けず、粘り強い対話で友情と信頼を結び、築いてきたのです。
池田先生は語っています。
「どうせ生きるなら、大目的に向かって、大確信をもって、自分自身の『栄光の山』を、悠然と、楽しみながら登りきることだ。人生、弱くては、つまらない。『私は創価学会だ。だれが何と言おうが、偉大な創価学会の代表だ』。そのくらいの決心で、胸を張っていくべきだ」と。
私たち一人一人が栄光の人生を勝ち開くために、不退の信心を貫き、わが地域に友情と信頼の輪を広げていきましょう。
◆気になる?→なるほど! ザダンカイ質問タイム◆
Q
御本尊には、どんなことを祈ってもいいんですか?
A
何を祈っても大丈夫。
信心が強まるほどに、祈りも境涯も深まっていく。
登場人物
大木さん(地区部長)
白崎さん(地区婦人部長)
蓮田さん(男子部員)
華山さん(女子部員)
蓮田 今回の御書を学び、地道な信心の大切さがよく分かりました。
ただ……御本尊に何を祈ってもいいんでしょうか?
白崎 あらあら、蓮田さん、どうしたの。
大木 もしかして、何かあったのかい。
蓮田 実は、仏法対話している友人から「祈りが叶う信仰っていうのなら、俺も、〝楽してお金を稼げるように〟って、いのってみようかな」って言われちゃって……。
華山 あらら。信心に関心を持ってくれたのは良かったなと思うけど、ちょっと虫がよすぎるような気もしますね。
蓮田 もちろん、僕もそう思いました。だけど、本当にいいことなのか、ダメなのか、自分でも、なんかスッキリしなくて、モヤモヤしているんです。
華山 確かにそうですね。御祈念というと、「もうちょっと給料が増えますように」とか、「仕事が順調に進みますように」といった現実的な願いごとを掲げることも多いですしね。
白崎 その友人の場合は、〝楽して〟っていう姿勢が気になるけど、自分の都合のいいことを祈ってはいけないなんてことは、ないのよ。
蓮田 えっ、いいんですか?
白崎 そう、いいのよ。最初は、みんな自分の悩みや願いごとから始まるんだから。だけど祈ったことで、きちんと納得できる結果が出るから、確信につながるのよ。
大木 誰だって、入会したばかりの頃は、自分の仕事や健康のことなど、「自分の悩みや欲求が解決すること」を願って、御本尊に祈り、学会活動に励んでいるんじゃないだろうか。それが、信心を続けていくうちに、自分のことに加えて、だんだんと友人や周囲の人のことを祈れる自分へと変わっていったんじゃなかったかな?
華山 確かに。私にも経験があります。かつて職場に苦手な先輩がいて、初めは「早くその先輩に、違う部署に移ってほしい」って祈っていました。でも、学会活動に励むうちに「まず自分が変わろう」と思うようになり、今では「その先輩に出会ったおかげで、成長できた」と感謝の題目を唱えられるようになったんです。
大木 素晴らしい体験ですね。最初は、自分のことでいっぱいだったけど、偉大な妙法に縁することで、次第に、祈りも深まり、自分の境涯が大きいものになっていったんだね。池田先生は、〝自分のことだけでなく、家族のこと、社会のこと、人類のことまでも祈れる信心になっていけば、その分、大きな自分になっているのです〟と語られているんだよ。
蓮田 なるほどー、よく分かりました。
白崎 祈るきっかけは、些細なことでいいの。でも、広宣流布を目指して前進している創価学会の中で、日々、真剣に戦っていれば、気が付いたら、大きく境涯が広がり、栄光の人生が開かれることは間違いないのよ』
(『大白蓮華』 2018-2 聖教新聞社)より
SOKAnet 会員サポート 座談会御書e講義より https://www.sokanet.jp/index.html
講師 : 橋本教学部長書記長
【解説】
『仏法を実践する私たちに不可欠なのが、不退転の持続の信心と地域・社会での信頼の実証を築く実践であることを教えられています。
本抄は、四条金吾への励ましのお手紙ですが、そこには、ひとりでも多くの門下が大難を乗り越え、宿命を転換し、幸福を勝ちとってほしいとの、大聖人の御心情が迫ってきます。
大難の渦中にあっても、折伏・弘教に挑む四条金吾に、もう一重深く打ち込むように、大聖人は強調されます。
それが、冒頭の、【法華経の信心を・とをし給へ】との仰せです。
火を起こす作業と同じように、「法華経の信心を最後まで貫き通していきなさい」と述べられています。
当時、火は、道具を使い、摩擦による熱で起こしていました。
火が出るまで、間断なく勢い良く作業しなければならない。手を休めてしまえば、火は着かない。
それと同じように、「魔」につけ入れる隙を与えずに、地道に信心を貫き通していくことの大切さを教えられています。
いつ、いかなる時も、妙法を心から信じ、自行化他(じぎょうけた)にわたって弘めていく強き信心こそ、勇気と勝利の最大の原動力です。
ゆえに、【強盛の大信力をいだして】と、呼び掛けられています。
大変な時・大切な時に、「今こそ」「いよいよ」と、大信力を奮い起こし、広宣流布の誓願を胸に前進していくことが勝利への第一歩となるからです。
大聖人は、弟子に「勝利への指標」を示されます。
【法華宗の四条金吾(しじょうきんご)・四条金吾と鎌倉中の上下万人(じょうげばんにん) 乃至(ないし) 日本国の一切衆生の口にうたはれ給へ】。
大弾圧を受けていた当時、人々から「法華宗の誰々」と言われるのは、「あの、法華宗か!」と、後ろ指を指される。あるいは、ひた隠しにしたい呼ばれ方だったことでしょう。
それを、敢えて、大聖人は、「さすが、あれが、法華宗の四条金吾・四条金吾」と、鎌倉中、日本中の人々に讃嘆されるような、信頼と実証を勝ち取りなさい、と御指導されたのです。
私たちで言えば、周囲から、「創価学会の誰々さん」と称賛され、妙法の偉大さを示していくことに他なりません。
仏法を実践する私たちが、現実の人生と生活に勝利して、周囲から信頼されてこそ、初めて、その仏法の力が証明されます。
一人ひとりが掛けがえのない存在になることが、逆境を跳ね返していく原動力になり、広宣流布を開くことになる、と明記してまいりたいと思います。
【ポイント】
講義のポイントを2点申し上げます。
ポイントの1つ目は、勝利を開く原動力は、「不退転の持続の信心」であるということです。
池田先生は、小説『新・人間革命』第11巻の「躍進の章」で、「持続の信心」について述べられています。
『持続というのは、ただ、昨日と同じことをしていればよいのではありません。「日々挑戦」「日々発心」ということです。信心とは、間断なき魔との闘争であり、仏とは戦い続ける人のことです。その戦いのなかにこそ、自身の生命の輝きがあり、黄金の人生がある』(『新・人間革命』第11巻366ページ)
と。
また、池田先生は、スピーチで次のように指導されています。
『本当の幸福とは、崩れざる自分自身を築くことである。その源泉が妙法の信仰である。そのために学会の組織がある。 (中略)
一人だけでは、道をはずれる場合がある。絶対的幸福を目指して、たがいに励まし合い、支えあい、正しい軌道を進んでいく。
学会は、いわば「幸福と平和の学校」なのである』(『普及版 池田大作全集「スピーチ」2002年[2]』12ページ)
以上が、先生のスピーチです。
大事なのは、互いに励まし合う学会の同志の存在です。
その意味で、ひとりを大切に、全員を勝利者に、との思いで、訪問・激励、個人指導に徹する重要性を共々に明記してまいりたいと思います。
ポイントの2つ目は、勝利の指標は、信心で人間性を磨き、地域や職場でなくてはならない存在となっていく、ということです。
池田先生は、今回の御文をとおして、次のように講義されています。
『「信心即生活」です。「仏法即社会」です。社会の中で、信心根本に絶対勝利の実証を示し、人々から讃嘆されることこそ、仏法者のあるべき正しい姿です。
「法華宗の四条金吾」――この御指導は、永遠の指標です。
学会員は、この御金言を心肝に染め、現実の人生に妙法の果徳を厳然と現しながら生き抜いてきました。これ以上の尊き、素晴らしき人生はありません』(『勝利の経典「御書」に学ぶ 20』35ページ)
と。
本年11月には、広宣流布大誓堂完成5周年を迎えます。
創価学会常住御本尊が、本部に御安置されて初めての正月を迎えた1952年(昭和27年)、池田先生は、御本尊御前から、大法弘通慈折広宣流布へ出陣され、広布拡大の翼を東京蒲田より広げられました。
この2月闘争で、池田先生が具体的に取り組まれたのが、「祈りから出発」「近隣を大切に」「体験を語る」の3つです。
まさに、〝仏法者のあるべき姿をとおして広宣流布を前進させる〟という、拡大の模範の金字塔を打ち立てられました。
私たちは、「世界広布新時代」の2月闘争を痛快な挑戦と拡大で総仕上げし、「3・16」60周年の世界青年部総会の大勝利へ、青年と共に勢い良く前進してまいりましょう』