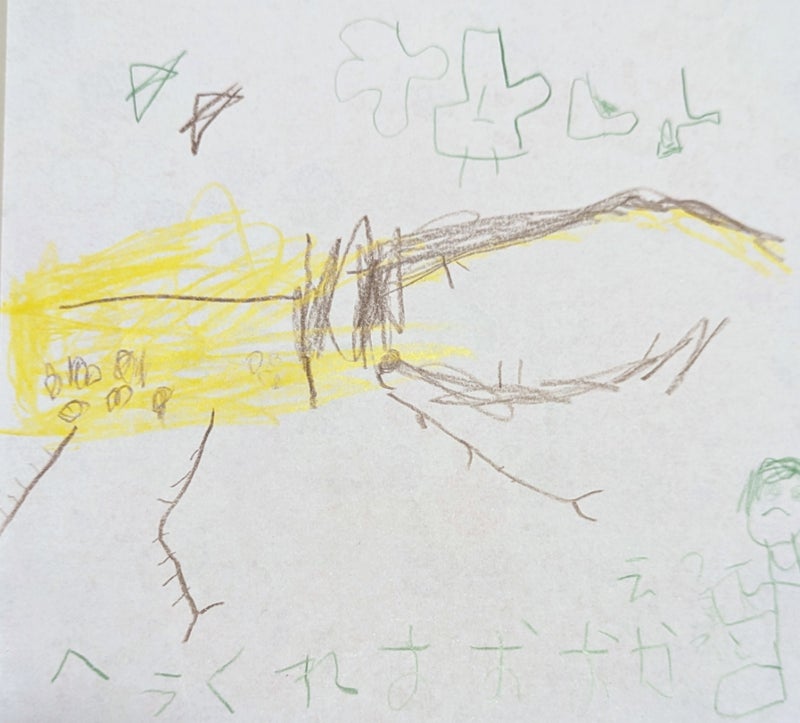★川崎区川崎大師の絵画教室
お問合せ:080-4195-4579
なないろアート アトリエセブンカラーズ ホームページ
2月も中旬になりました。三寒四温といいますが
雪が降ったり、温かくなったり・・・この季節を乗り越えたら桜の季節ですね。
今日は絵画教室の生徒さんの声をご紹介します。
I様
娘が習い始めて5年目になります。いろんな画材を使い、新しい事も取り入れてくださるので毎回レッスンをとても楽しみに通っています。
レッスンを通して「絵を描くのが好き!」という気持ちを大切に育ててくださっているように感じます。
いつも思うのですがただ絵のテクニックを教えてくださるだけではないというところが教室も魅力です。
娘のことを絵を通してすごく理解していただいて、親も知らない面を引き出してもらえるというか・・・。
娘は「いつも私の絵のいいところを見つけて褒めてくれるので自信がついた、楽しい。」と言っています。
アトリエセブンカラーズでは
「自分の絵が好きになる自己肯定感の高い子供を育てる」
という理念のもとに活動してきました。
アドラー心理学に基づいた「勇気づけ」や
右脳と五感を刺激する「臨床美術」も取り入れています。
私自身が自分の絵が大好きだったのが「大嫌い」に変わった経験があります。
自分の表現したいものを思い切り表現してほしいと思います。
H様
通っている本人は、絵を描くためのいろいろな技法を教えてくれるのが嬉しいそうです。
親としては、毎回違うテーマなので持ち帰った作品を見るのがとても楽しみなことと、何より子供が好きな事をしっかりした先生の下で学び、楽しめて通えているのがありがたいと思っています。
親も知らない画材の使い方もあったりして、自分が小さな頃も通いたかった、と思ったりしています。
M様
通いはじめてまだ2か月ですが娘は毎回レッスンを楽しみにしております。この短い間でも本当に多彩なレッスン内容で様々な作品を持ち帰って来ます。
何より先生の描かれる絵が大好きで憧れているようです。
絵画教室では新年度に向けて体験教室を実施いたします。
絵が好きな方、もっと描けるようになりたい方
絵画工作に興味のある方、新しい事を始めたい方
苦手意識を克服したい方・・・
いろんな思いをもった生徒様をお待ちしております。
一人でコツコツ描く時間も大切ですが
楽しいイベントや作品展、みんなで作る大きな共同作品など
教室だからできる経験があります。
一緒に楽しく制作しましょう!
★体感教室のお申込みはコチラ
↓ ↓
子育て論は
子どもを尊重する事が大切とか
いいところに注目するとか
学ぶほどいろいろありますが
そんな事してきたら
子供がわがままに育つのでは?と
心配になりませんか?
こどもを尊重することと
甘やかしを履き違えてしまう事が
あるのではないでしょうか?
何でも子どもの望みを
叶えるのは甘やかしですね。
例えば習い事に行く日に子供が
今日は行きなさたくないと
いってきたらどうしますか?
行きなさいと行っても
子供が泣くと根負けして
子どものいいなりになったりすると
子供は泣きさえすれば
親は自分の言うことを聞くと
学習します。
行かないなら習い事は辞めると
きちんとルールを決めておいて
その通りにしなくてはいけません。
子どもに結末を体験させるのです。
毅然とした親の態度が大切です。
この対応から子供は何を学ぶのか
という視点を持ちたいです。
実際の点数は明かすことなく
その後、子どもたちを
グループA「頭がいいね」
グループB「よく努力したね」
グループC コメントなし
さらにその後、子どもたちに
グループAの「頭か?いいね」
『頭がいいね』と褒めることが
褒める事自体が悪いことでは
ないですが褒めるタイミングを
間違えてはいけないということです。
私は似顔絵師として起業しました。
全国各地で子供の似顔絵を中心に描いてきました。
当時は、起業なんて意識はなくて
気づいたらこれ起業だったんだな・・・
と思うほど計画性なく
似顔絵イベントをしはじめて
現場描きはどんなに描いても
開催場所にとられる分もあり
大した収入にはなりませんでしたが
それでも描く仕事はとても楽しく
お金には代えられない
やりがいを感じるものでした。
あの頃から一度も会社員をやめた事を
後悔したことはありません。
私が起業したばかりの頃から
ずっと絵のオーダーをいただいている。
ワンちゃん好きのお客様がいます。
愛犬とファミリーをずっと描かせていただき
本当に幸せな事です。
新しい愛犬が来た時も
愛犬を亡くされた時も
描かせていただきました。