FANM MATNIK DOU
先週、21日に発売になりましたMAYAさんのニューアルバム「マルチニークの女」、じっくりと聴き込んでおります。
というわけで、恒例(と言うわけでもありませんが)のレビューをば・・・
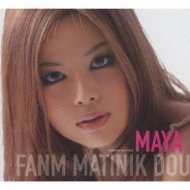

マルチニークの女 / MAYA
本作はジャズ&ラテンシンガーMAYAが、ラテンに特化して取り組んだ意欲作。
ベサメ・ムーチョやラ・クンパルシータなど、一般的にも有名な曲も多数収録されていますが、「こんな曲知らん!」というようなマニアックな曲も多数収録されており、選曲の妙も光っています。
そして、「ラテンって言うと、無駄に陽気なアレでしょう!?」と、その陽気なイメージを持っておられる方も多いかと思いますが、いやいや、このラテンアルバムは実にラテンの持つ「哀愁」をタップリと感じることが出来ます。
ラテンは何故、陽気なメロディーと激しい情熱を持ち合わせているのか。
裕福な社会には生まれなかったであろう、ラテンの哀愁あるメロディーがじっくりと心にしみてきます。
■1曲目 Inamura Jane
勘の良い方ならこのローマ字でピンと来るかも知れません。そうです、桑田佳祐さんの「稲村ジェーン」です。
正直、「稲村ジェーン」というと、映画の方が真っ先に思い浮かびますし、その映画の方も・・・。そんな感じなので、曲の方なんか全く覚えておりません。
しかし、この高橋康廣さんのアレンジ、このMAYAさんの歌声で聴く「稲村ジェーン」で開眼しました。
スゲェいい曲。
そして、なんと言ってもMAYAさんも初めて望んだというフラメンコ調のアレンジが秀逸で、関根彰良さんのギターも必聴。
■2曲目 Besame Mucho
MAYAさんとしてはメジャーデビュー前の2ndアルバムの時にも吹き込んだ事のある「Besame Mucho」。
個人的にはこの2ndの時のBesame Muchoはあまり好きではなかったのだけれど、ライブで聴くBesame Muchoは好きだったし、今回、本作に吹き込まれたBesame Muchoは素晴らしい。
スローテンポでしっとりと歌われるBesame Muchoは曲調はジャズを基調に、ほんの少しラテンのスパイスが香ってくるアレンジ。
そのゆったりと、しっとりとした曲調に、感情を静かに絞り出すようなMAYAさんの歌声は絶妙に絡み合い、Besame Muchoという世界を作り上げていきます。
■3曲目 Ser Y No Ser
先ほどのBesame Muchoよりはアップテンポで展開される「Ser Y No Ser」ですが、決して陽気な曲ではなく、この愁いを帯びたメロディーがなんとも秀逸です。
その愁いのあるメロディーを内田光昭さんのトロンボーンが奏で、MAYAさんの歌声に陰のある艶を添えています。
■4曲目 Abrazame
ホント、MAYAさんには申し訳ない!!
どうしても「Abrazame(アブラサメ)」が「油鮫」に聞こえてしまう・・・と言うか、勝手に連想してしまう!!
で、曲中「油鮫と言えば、深海鮫の油(肝油)はスクアランオイルという名称で、よく健康食品として売っているなぁ・・・。ん?このスクアランオイルの原料の深海鮫ってなんだ?まさか油鮫という名称の鮫じゃ無かろうな・・・」などと考えている間に曲が終わってしまうのです。
申し訳ない!
メロディーも何も良い曲なのに・・・
ちなみに、油鮫という鮫は居ませんでしたが、「エドアブラザメ」という鮫はいるそうです・・・
■5曲目 Sabor A Mi
アルゼンチンで「Sabor A Mi」というお料理番組があったらしい(今でも放送しているかは不明)。
それは兎も角、ラテンのスタンダードとして有名らしいこの曲。オイラは本作で初めて知りました。
Sabor A Mi・・・直訳すると「私の味」かな?
男と女の会話で「私の味」だから・・・「私色に染まったあなた」という感じか。いや、ラテンの曲なんだから、もっとエロい意味で捉えても良いのかも知れない・・・。
曲調も、内田さんのトロンボーンが甘く、ゆっくりとたゆたい、そこに甘く吐息が溢れるようにMAYAさんの歌声が絡んできます。
う~ん・・・マッタリしてきた・・・。
■6曲目 Maria Cervantes
ここでピアノトリオの演奏。ベースは嶌田憲二さん、ピアノが岡田げんさん、ドラムが松尾明さん。
ミドルテンポの軽快で、それでいてしっかりとした芯のある曲調が何とも言えません。
岡田げんさんのピアノ、トリオの演奏で初めて聴きましたが、この人、ラテンの血が流れてるんじゃないでしょうか?スペインのジャズアーティストの演奏を聴いているようです。
MAYAさんのアルバムに収録されているトリオ演奏曲は素晴らしいものが多いですが、これもまた秀逸。
■7曲目 La Cumparsita
聴けば誰もが「あ!この曲は!!」と気付くこの曲。誰もが知っているこの曲。へぇ・・・こういうタイトルだったか・・・と、今更知って恥ずかしかったり。
なんだかこの曲、聴くと反射的に社交ダンス(演目はタンゴ)のイメージが頭に浮かびますが、これ、私だけではないはず。
それもそのはずで、ウルグアイのヘラルド・マトス・ロドリゲスという作曲家がカーニバルに参加する仲間のために作曲したタンゴ曲とのこと。
しかしそうか、この曲を選曲したか、MAYAさん。
■8曲目 Meu Mundo Caiu
Meu Mundo Caiu、「崩れた世界」。
この曲はブラジルの歌手Maysaの曲。
「魔性の女」と呼ばれたMaysaのその生涯は、男に落ち、酒に落ち、最後はその酒によって交通事故を起こし、40歳の若さで亡くなるまで波乱に満ちていたそうです。
そんなMaysaの「崩れた世界」、MAYAさんは自分の物にしています。
オリジナルのMaysaの「崩れた世界」は、ストリングスが入っているため、崩れていく世界に華やかさが垣間見えるのですが、本作の「崩れた世界」は内田さんのトロンボーンが基調となっているため、更に直接的に崩れた世界の儚い世界観を感じることが出来ます。
ちなみに、Maysaが歌う「崩れた世界」はこちら↓
■9曲目 Princesa Caballero
なんだろう、急に世界が変わった。
直訳すると・・・「紳士王女??」いやいや、調べてみると、「騎乗のプリンセス」という意味らしい。
それにしても、なんだか砂漠とラクダが見えてくるのはオイラだけ??
なんだかとっても変わった雰囲気の曲。
でもなんだか気になる。
■10曲目 Historia De Un Amor
邦題は「ある恋の物語」。以前、MAYAさんのアルバム「Love Potion No.9 」でも収録されていた曲。
」でも収録されていた曲。
これを松尾明トリオ(ピアノは小林裕さん)と内田光昭さんのトロンボーンで演奏しています。
これまで甘く歌っていた内田さんのトロンボーンが、儚く哀愁を帯びた音色に変わっています。まさに歌うトロンボーン。
MAYAさんの歌声こそ入っていないものの、MAYAさんの世界を壊さず、むしろ次の「マルチニークの女」への序章として、しっとりと誘導していくかのようです。
■11曲目 Fanm Matinik Dou
タイトル曲、「マルチニークの女」。このアルバムに収録されるまでこの曲を知りませんでした。
これがまたノリの良いラテンナンバーで、曲の出だしで突如登場するオーバードライブのかかったギターの音色にキュン!となってしまいます。
この曲を聴くと、これまで押し殺してきたMAYAさんの「明」の部分が解放されたかのような、ようやく笑顔が見れたような・・・そんな印象を受けます。
体が自然と揺れてきます。
■12曲目 Tres Palabras
この曲はこれまでもライブなどで歌われてきた曲ですが、ようやくアルバムに収録された・・・という感じもします。
そして、アップテンポの、いわゆる「明るい」ラテン曲でアルバムの最後を締めないのもMAYAさんならではか?
この曲を歌うときのMAYAさんは、いつも目を瞑って左手を方の高さに掲げ、そしてサビでは少し膝を曲げて腰を落とし、眉間にしわを寄せながら切なそうに歌います。
CDを聴いていてもその姿が頭の中に浮かんできます。
プロデューサーの寺島靖国さんも「MAYA史上最高のCD!」と力強く拳を掲げておりました。
納得の1枚です。
このレビューを書きながらこのアルバムを聴いているわけですが、聴けば聴くほど新しい発見がある、聴けば聴くほど病み付きになってくるCD。
MAYAさん、恐るべし。
というわけで、恒例(と言うわけでもありませんが)のレビューをば・・・
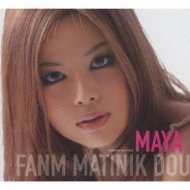
マルチニークの女 / MAYA
本作はジャズ&ラテンシンガーMAYAが、ラテンに特化して取り組んだ意欲作。
ベサメ・ムーチョやラ・クンパルシータなど、一般的にも有名な曲も多数収録されていますが、「こんな曲知らん!」というようなマニアックな曲も多数収録されており、選曲の妙も光っています。
そして、「ラテンって言うと、無駄に陽気なアレでしょう!?」と、その陽気なイメージを持っておられる方も多いかと思いますが、いやいや、このラテンアルバムは実にラテンの持つ「哀愁」をタップリと感じることが出来ます。
ラテンは何故、陽気なメロディーと激しい情熱を持ち合わせているのか。
裕福な社会には生まれなかったであろう、ラテンの哀愁あるメロディーがじっくりと心にしみてきます。
■1曲目 Inamura Jane
勘の良い方ならこのローマ字でピンと来るかも知れません。そうです、桑田佳祐さんの「稲村ジェーン」です。
正直、「稲村ジェーン」というと、映画の方が真っ先に思い浮かびますし、その映画の方も・・・。そんな感じなので、曲の方なんか全く覚えておりません。
しかし、この高橋康廣さんのアレンジ、このMAYAさんの歌声で聴く「稲村ジェーン」で開眼しました。
スゲェいい曲。
そして、なんと言ってもMAYAさんも初めて望んだというフラメンコ調のアレンジが秀逸で、関根彰良さんのギターも必聴。
■2曲目 Besame Mucho
MAYAさんとしてはメジャーデビュー前の2ndアルバムの時にも吹き込んだ事のある「Besame Mucho」。
個人的にはこの2ndの時のBesame Muchoはあまり好きではなかったのだけれど、ライブで聴くBesame Muchoは好きだったし、今回、本作に吹き込まれたBesame Muchoは素晴らしい。
スローテンポでしっとりと歌われるBesame Muchoは曲調はジャズを基調に、ほんの少しラテンのスパイスが香ってくるアレンジ。
そのゆったりと、しっとりとした曲調に、感情を静かに絞り出すようなMAYAさんの歌声は絶妙に絡み合い、Besame Muchoという世界を作り上げていきます。
■3曲目 Ser Y No Ser
先ほどのBesame Muchoよりはアップテンポで展開される「Ser Y No Ser」ですが、決して陽気な曲ではなく、この愁いを帯びたメロディーがなんとも秀逸です。
その愁いのあるメロディーを内田光昭さんのトロンボーンが奏で、MAYAさんの歌声に陰のある艶を添えています。
■4曲目 Abrazame
ホント、MAYAさんには申し訳ない!!
どうしても「Abrazame(アブラサメ)」が「油鮫」に聞こえてしまう・・・と言うか、勝手に連想してしまう!!
で、曲中「油鮫と言えば、深海鮫の油(肝油)はスクアランオイルという名称で、よく健康食品として売っているなぁ・・・。ん?このスクアランオイルの原料の深海鮫ってなんだ?まさか油鮫という名称の鮫じゃ無かろうな・・・」などと考えている間に曲が終わってしまうのです。
申し訳ない!
メロディーも何も良い曲なのに・・・
ちなみに、油鮫という鮫は居ませんでしたが、「エドアブラザメ」という鮫はいるそうです・・・
■5曲目 Sabor A Mi
アルゼンチンで「Sabor A Mi」というお料理番組があったらしい(今でも放送しているかは不明)。
それは兎も角、ラテンのスタンダードとして有名らしいこの曲。オイラは本作で初めて知りました。
Sabor A Mi・・・直訳すると「私の味」かな?
男と女の会話で「私の味」だから・・・「私色に染まったあなた」という感じか。いや、ラテンの曲なんだから、もっとエロい意味で捉えても良いのかも知れない・・・。
曲調も、内田さんのトロンボーンが甘く、ゆっくりとたゆたい、そこに甘く吐息が溢れるようにMAYAさんの歌声が絡んできます。
う~ん・・・マッタリしてきた・・・。
■6曲目 Maria Cervantes
ここでピアノトリオの演奏。ベースは嶌田憲二さん、ピアノが岡田げんさん、ドラムが松尾明さん。
ミドルテンポの軽快で、それでいてしっかりとした芯のある曲調が何とも言えません。
岡田げんさんのピアノ、トリオの演奏で初めて聴きましたが、この人、ラテンの血が流れてるんじゃないでしょうか?スペインのジャズアーティストの演奏を聴いているようです。
MAYAさんのアルバムに収録されているトリオ演奏曲は素晴らしいものが多いですが、これもまた秀逸。
■7曲目 La Cumparsita
聴けば誰もが「あ!この曲は!!」と気付くこの曲。誰もが知っているこの曲。へぇ・・・こういうタイトルだったか・・・と、今更知って恥ずかしかったり。
なんだかこの曲、聴くと反射的に社交ダンス(演目はタンゴ)のイメージが頭に浮かびますが、これ、私だけではないはず。
それもそのはずで、ウルグアイのヘラルド・マトス・ロドリゲスという作曲家がカーニバルに参加する仲間のために作曲したタンゴ曲とのこと。
しかしそうか、この曲を選曲したか、MAYAさん。
■8曲目 Meu Mundo Caiu
Meu Mundo Caiu、「崩れた世界」。
この曲はブラジルの歌手Maysaの曲。
「魔性の女」と呼ばれたMaysaのその生涯は、男に落ち、酒に落ち、最後はその酒によって交通事故を起こし、40歳の若さで亡くなるまで波乱に満ちていたそうです。
そんなMaysaの「崩れた世界」、MAYAさんは自分の物にしています。
オリジナルのMaysaの「崩れた世界」は、ストリングスが入っているため、崩れていく世界に華やかさが垣間見えるのですが、本作の「崩れた世界」は内田さんのトロンボーンが基調となっているため、更に直接的に崩れた世界の儚い世界観を感じることが出来ます。
ちなみに、Maysaが歌う「崩れた世界」はこちら↓
■9曲目 Princesa Caballero
なんだろう、急に世界が変わった。
直訳すると・・・「紳士王女??」いやいや、調べてみると、「騎乗のプリンセス」という意味らしい。
それにしても、なんだか砂漠とラクダが見えてくるのはオイラだけ??
なんだかとっても変わった雰囲気の曲。
でもなんだか気になる。
■10曲目 Historia De Un Amor
邦題は「ある恋の物語」。以前、MAYAさんのアルバム「Love Potion No.9
これを松尾明トリオ(ピアノは小林裕さん)と内田光昭さんのトロンボーンで演奏しています。
これまで甘く歌っていた内田さんのトロンボーンが、儚く哀愁を帯びた音色に変わっています。まさに歌うトロンボーン。
MAYAさんの歌声こそ入っていないものの、MAYAさんの世界を壊さず、むしろ次の「マルチニークの女」への序章として、しっとりと誘導していくかのようです。
■11曲目 Fanm Matinik Dou
タイトル曲、「マルチニークの女」。このアルバムに収録されるまでこの曲を知りませんでした。
これがまたノリの良いラテンナンバーで、曲の出だしで突如登場するオーバードライブのかかったギターの音色にキュン!となってしまいます。
この曲を聴くと、これまで押し殺してきたMAYAさんの「明」の部分が解放されたかのような、ようやく笑顔が見れたような・・・そんな印象を受けます。
体が自然と揺れてきます。
■12曲目 Tres Palabras
この曲はこれまでもライブなどで歌われてきた曲ですが、ようやくアルバムに収録された・・・という感じもします。
そして、アップテンポの、いわゆる「明るい」ラテン曲でアルバムの最後を締めないのもMAYAさんならではか?
この曲を歌うときのMAYAさんは、いつも目を瞑って左手を方の高さに掲げ、そしてサビでは少し膝を曲げて腰を落とし、眉間にしわを寄せながら切なそうに歌います。
CDを聴いていてもその姿が頭の中に浮かんできます。
プロデューサーの寺島靖国さんも「MAYA史上最高のCD!」と力強く拳を掲げておりました。
納得の1枚です。
このレビューを書きながらこのアルバムを聴いているわけですが、聴けば聴くほど新しい発見がある、聴けば聴くほど病み付きになってくるCD。
MAYAさん、恐るべし。