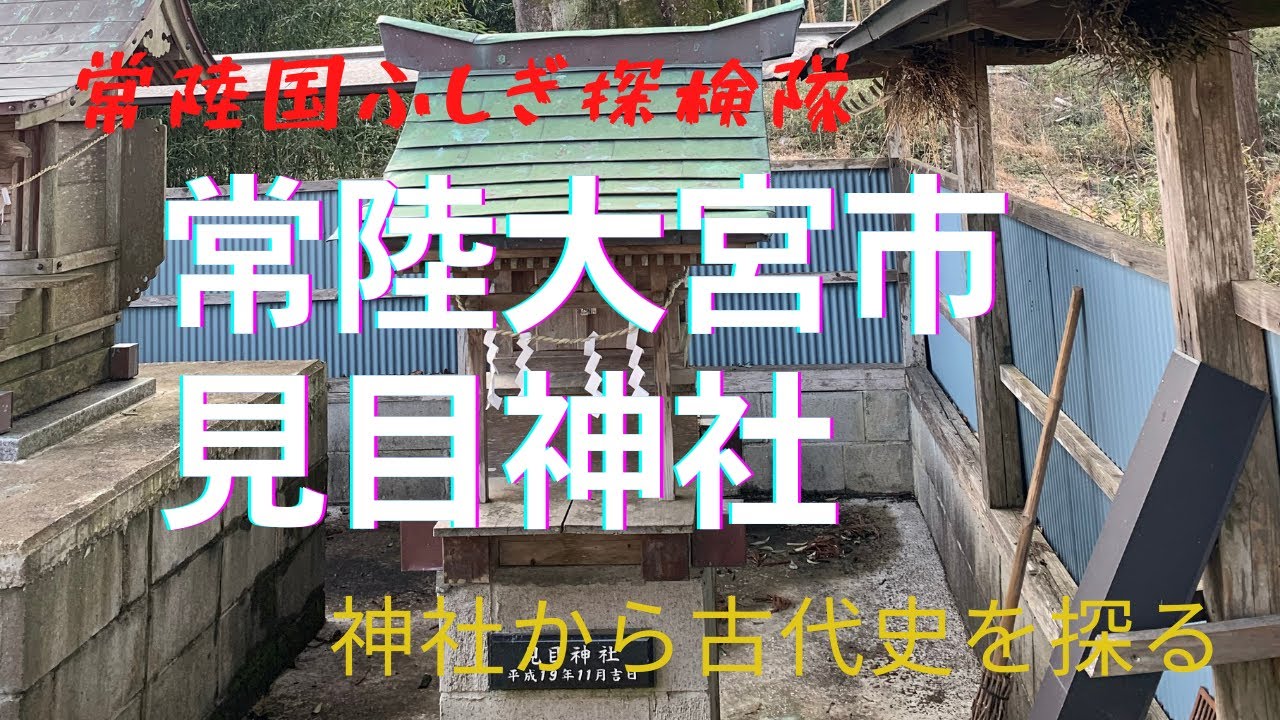常陸大宮市と常陸太田市に見目神社という神社がある。
少しも有名な神社ではない。😆
しかし、常陸国一宮鹿島神宮において、見目はとても重要な名前だったのだ。
Wikipediaの要石の項から引用
社伝によれば、見目浦とは、香々背男討伐のために武甕槌が天下った場所なのだ。
それが要石だということになっている。
要石は、鹿島神宮のほか、千葉の香取神宮、桜川市の磯部稲村神社にもある。
Wikipediaを見れば、三重県伊賀市の大村神社、宮城県加美町の鹿島神社にもあるようだ。
鹿島神宮の要石は、光圀が七日七晩掘らせたが、ついに石の全容は明らかにならなかったと、まことしやかな伝承が語り継がれている。
光圀や彰考館が絡むと、歴史や民俗は書き換えられていると考えるのが、科学的良心ある茨城県の歴史研究者の常識となりつつある。
文学的良心派の研究者のことは知らない。😆
YouTube動画に"ウノミちゃん"についての田舎道ドライブトークを投稿したが、既存の文献やネット記事、ニュース、新聞記事などを読んで、それが事実だと思ってしまう人を、われわれは"ウノミちゃん“と命名したのだ😆
だから、要石は地震を防いでいるのでしょ?とか、そんな話は311を経験したわたしたちには無意味だ😁
ものは言いようなので、要石のおかげであの程度で済んだんだ、なんて考え方をする、ウルトラスーパーポジティブ=おめでたい人間もいるが、わたしには近づかないで欲しい。
そういう人たちだけで徒党を組んでいて欲しい。🤣
神武即位がBC.660年と盲信している人たちも近寄らないで欲しい。
いわゆる天皇アゲの人たちのことだ。
わたしは、わたしなりの科学的思考で古代史を解明したいのである。😂
さてさて、見目神社だが、祭神は高倉下である。別名天香山。
Wikipediaより引用
天火明=饒速日の子とされる。
母親の天道日女は、天の川のお姫様という程度の意味であり、メソポタミア星座神話のアン、つまりイナンナ、ギリシャのアフロディーテ、ローマのヴィーナスと同義だと気づかなければならない。
日本神話で言えば、コノハナサクヤヒメ、オキツヨソタラシヒメ、イヨなどに相当するだろう。
上記のように饒速日の妻に該当するのは、コノハナサクヤヒメ=アメノウヅメ=豊受姫=加用姫になる。
いわば卑弥呼やアマテラスのひとりとも言って良いと思う。
われわれは饒速日は、武甕槌と長髄彦の性質を借用して、藤原不比等が創作したと踏んでいる。
百嶋系図においては、武甕槌がAニギハヤヒ、フツヌシ=猿田彦をBニギハヤヒとしている。
しかし、高倉下については、事代主と活玉依姫の子としているように見えるが、線が消えているので、明らかではない。
百嶋先生は、おそらく著名な神を無理やり系図に入れ込んだのかもしれない。
また、よくわからないところは、通説に準拠しているようにも感じる。
高倉下は、神武東征の時に武甕槌の名代として出現し、フツノミタマ=フツヌシでも良いだろう、を神武に下賜した。
武甕槌が大国主に国譲りを迫った時の刀である。
われわれ的には、大国主=長髄彦であるから、神武東征の熊野のくだりとの類似性を見て取ることができるのだ。
われわれは、さらに武甕槌も大国主のひとりと見做している。🤣
ふたりの大国主が安日長髄彦になる。
常陸国の見目神社は、常陸大宮市と常陸太田市にあるのだが、常陸太田市粟原のものは、宇野家の氏神として、文禄2年1594年に、おそらく常陸大宮市のものを勧請したようだから、古代史的意味は薄いだろう。しかも、高倉目と書いてある🤣
高倉下タカクラジのジを自と書いていたのを目と写し間違えたのか?
それとも、見目の目を意識していたのかは定かではない😆
常陸大宮市のものは、現在では若林の見目諏訪神社しか掲載がないが、石沢の見目平から勧請したとあるので、そちらが元宮になるはずだ。
しかも、石沢!
要石沢?
わたしはここで要石を探そう!😆
要石は、じつはカモメ石かもしれない。
カモメ石とは、もやい石だろう。
船を繋ぎ止めておく舫(もやい)だ。
中島みゆき「ニ隻の舟」より
敢えなくわたしが 波に砕ける日には
どこかでおまえの舟が かすかにきしむだろう
それだけのことで わたしは海をゆけるよ
たとえ舫い網は切れて 嵐に飲まれても
きこえてくるよ どんな時も
おまえの悲鳴が 胸にきこえてくるよ
越えてゆけ と叫ぶ声が ゆくてを照らすよ
直線距離で1kmくらいのものだ。
武甕槌が香々背男征伐に天下ったとされる見目浦は、鹿島神宮の要石のある場所だとされているが、武甕槌は建葉槌に香々背男退治の援軍を依頼したのだ。
建葉槌は静神社の祭神である。
鹿島神宮が常陸国一宮、静神社は二宮である。そして静神社は石沢の見目平から遠くはない那珂市静にあるのだ。
香々背男はどこに陣を張っていたかと言えば、日立市の大甕山(風神山)である。
鹿島神宮は、はるか南方にあるのだ。
だとしたら、見目浦とは、常陸大宮市の見目神社の場所がふさわしいのではないか?
武甕槌がタケカシマであるならば、鹿嶋神宮の元宮は、常陸大宮市門井の鹿島神社(旧大井神社)だと考えでも良い。
門井のすぐ北に那賀地名があり、タケカシマが居城とし皇都という字がある。
文学的推論をするならば、この那賀から今の緒川沿いに南下し、那珂川(往時は粟川と言ったらしい)に達して、合流地点で.皇都や光戸地名を残す。
さらに南下し、水戸市飯富町の大井神社に痕跡を残す。
さらに、聖方位の鹿島台地を南下し、大生神社を経由して、遂に鹿島神宮の場所に辿り着いたのではないか。
そしてその物語は、那賀氏が江戸氏になり、水戸城を作る話とダブってくるのだ。
だからこの神話は、中世時代以降に作られたのかもしれない。
香々背男が、武甕槌とフツヌシ、つまりニギハヤヒAとB、さらにタケハヅチに征伐されたというおとぎ話は、光圀=彰考館の創作かもしれない。
タケハヅチは、天日鷲の子だった。
見目は高倉下とされるが、有名な神社は、新潟の弥彦神社だ。常陸国から遠いのだ。
だからわたしは見目を目目姫だと考えてみた。すなわち遠津年魚目目妙姫(トオツアユメマグワシヒメ)である。いわゆる弟橘姫だ。われわれの系図では、タケハヅチの妹になるのだ。
ふたりの橘姫の祖父は鹿島のタケミカヅチになるのだ。父は、事代主=天日鷲である。
そして、ふたりの橘姫の夫はふたりのヤマトタケルになるのだが、彼らの祖父は、香々背男=長髄彦になるのであった🤣
中華(明国)系光圀が隠蔽したかったのは、これらのことではなかったか?
最近東国がヤマト王権以前の列島の中心地ったのではないか、という説が取り立たされているが、わたしたちもそれには同意する。
しかしながら、神武天皇即位をBC.660年とするのには賛同しない。
なぜなら神武とは五瀬命であり、スサノオでありながら、本来は女神だからである🤣🤣
追記:見目神社は伊豆にもあった。
三島大社の摂社になっている。
祭神は波布比売命(はふひめのみこと)波布といえば、都はるみのハブミナトだが、波、布と言ったら、常陸太田市の天志良波神社を思い出す。
祭神の天白羽鳥はヤマトタケルだった。
羽と波。つまり織物と波。
三島大社の祭神は大山祇と事代主だ。
大山祇の正体は、金山彦と妻の埴安姫=越智姫だと見抜いている🤣
事代主は彼らのひ孫である天日鷲=アジスキタカヒコネ=ウガヤフキアエズであり、ふたりのヤマトタケルの父親だった。そして彼らの妻は、姉弟橘姫、すなわちハブ姫。光圀がどんなことをしようが、真実はこぼれ落ちてくるのである。
記事の引用はフリーですが、引用元をきちんと表記してください。
見目神社の動画はこちら。