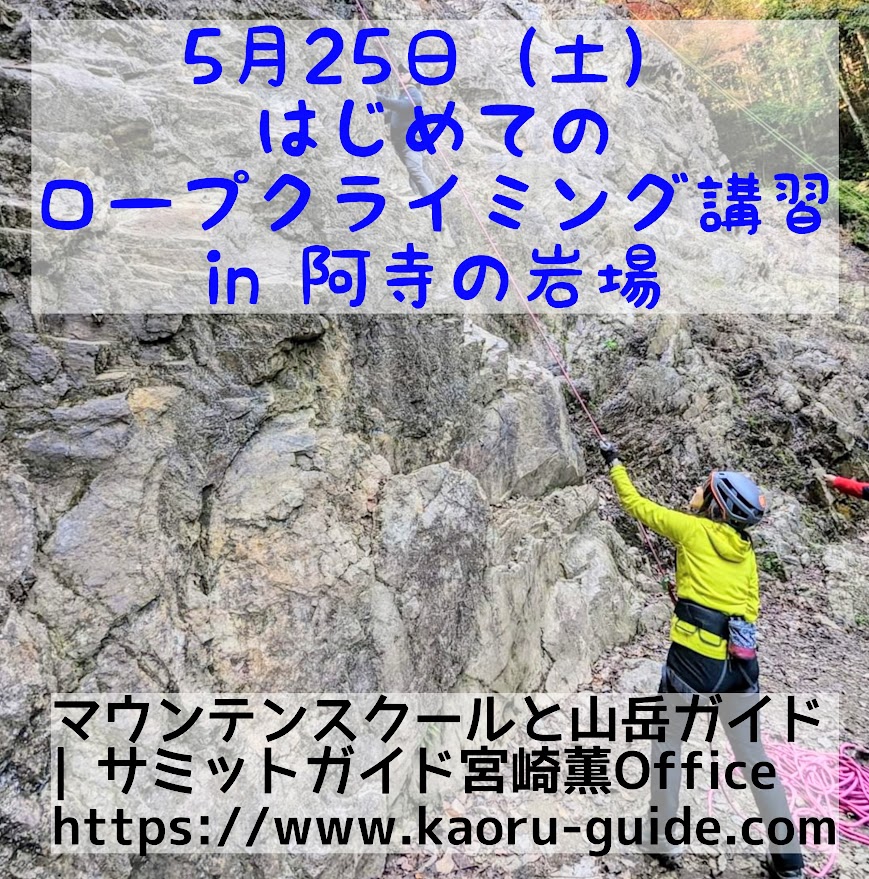また、山岳エリアにおいてはスマホは電波の圏外になることが避けられないけれど、無線機は電波状況を気にする必要がない。
そして複数の人とグループで同時に通信できるのが大きな利点。
かつて山で使う無線機と言えばアマチュア無線を使うのが一般的だったが、アマチュア無線技士の資格取得が必要なのと、「個人の趣味による、無線技術の追求」と言う様な前提があるため、ガイドなどの業務で使用することは法的に出来ない。
2008年にはじまった無線制度、デジタル簡易無線はアマチュア無線のように免許不要でありながら、アマチュア無線4級で使えるハンディ機と同じ最大5w出力。そして業務でも使用可。
僕もアマチュア無線技士4級の免許を持ってるが、山で使用する無線機はデジタル簡易無線に変えた。
複数台持って、仲間に貸して通話することも違法にならないから、僕も複数台持ってパーティで運用している。
アイコムのIC-DPR6を運用中。デジタル簡易無線登録局の大ヒット商品。
お互いの声が聞こえづらいマルチピッチや、パーティ間の連絡にも重宝。
開放呼び出しチャンネルにて第三者を呼び出すことも、秘話コードを使って混信することなく仲間内グループだけで使用することもできる。
運用に当たっては免許は不要だけど、総合通信局にデジタル簡易無線局の開設届をする必要はある。ネットで調べれば開設届作成は簡単。
デジタル簡易無線とは別に僕が持ってる無線機は、特定小電力トランシーバー。
アイコムIC-4350を運用中。防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さ。
特定小電力トランシーバーは免許も登録も不要で買ったその日から運用可能。
送信出力が0.01W以下で数100メートルの通話範囲に限られるが、そのぶん軽量コンパクトで安価なのがメリット。電波使用料も不要。
会の仲間内では、同じ機種の特定小電力トランシーバー同士で連絡取り合うこともある。
デジ簡(デジタル簡易無線)にせよ特小(特定小電力トランシーバー)にせよ、パーティで無線を運用するメリットはとても大きい。
コンテラの無線機用ハーネスは特殊部隊みたいでかっこいい。
胸部にピッタリ一体化するのでクライミングのとき視界が影響を受けずストレスない。