ご近所つきあいをさせていただいている東大名誉教授のT先生から先日「少し話したいことがあるんだけど」と電話をいただき自宅訪問。
T先生は御年86歳、少し足が不自由だが、敢然と一人くらしを続けてる。
実は同じくご近所つきあいをしている岐阜薬科大学元教授のK先生も88歳で一人暮らし。(ご近所つきあいと言っても車じゃないと大変だけど)
この先生は足が悪くて家の中でも車いす生活だ。
それでも一人くらしだからなぁ。
そんな事をものともせずに一人くらしを続けている二人を心から尊敬する。
凄いのは、二人ともまったくボケることなく一人暮らしを山中で続けていることだ。
膨大な読書量と文章書きがその秘密だと思う。
実は今、僕のカミサンが実妹とバルト三国ツアーに出かけていて、この間一人なのだが、どうにもつまらない。
食事も洗濯もその他諸々もみんな一人で処理しなければならない。
そのこと自体は大した事ではないけれど、自分の為だけに食事を作るというのはやはり少し煩わしい。
ついつい飲む量が増えるなぁ。
そんなことはともかく、T先生宅では千島列島問題でかなり盛り上がったのだが、その時先生が進めてくれたのが「ジニのパズル」。在日朝鮮人の「崔 実(チェ・シル)1985年生まれ、東京都在住。2016年、本作で第59回群像新人文学賞を受賞。」と言う若い女性の作品。
この本は、最初は少し饒舌過ぎて退屈だが、北朝鮮がテポドンを発射した描写あたりから一気呵成に物語が進み、民族とは何か、差別とは何か等々を激しく読者に突きつける。
その迫力たるや並たいていではない。
少女ジニが時代の流れの中で翻弄され、それでも必死に生き抜く姿は感動だ。
朝鮮学校の教室に飾られている金親子の肖像写真を教室から投げ捨てるシーンなどは、こんな事書いて作者は大丈夫なのかと思わせる。
差別といじめの中で生き抜く少女の姿に、深い共感を覚えた。
ヘイト差別が公然と横行する現代日本に突きつけた鋭い感性の刃かも知れない。
皆様もご一読下さい。
今日のおすすめ
全選考委員絶賛! 21世紀を代表する青春文学の誕生!
問題児のジニに、危なっかしいほどの生命力が宿っている。──青山七恵氏
一言でいうなら、これは「境界の物語」だ。──高橋源一郎氏
いつ暴力にさらされるか分からない者だけの知る緊張感に満ちている。──多和田葉子氏
素晴らしい才能がドラゴンのように出現した!──辻原 登氏
この小説との出会いに感謝せずにはいられない。──野崎 歓氏
受賞のことば

あまりにも呆然としていた。最終候補の連絡が来てからは生きた心地がしなかった。初めて担当者の方と会う約束の日は、前の晩から怖くてたまらなかった。顔をあげると、いつの間にか講談社に着いていた。慌てて降りると、Kodanshaではなく、Kudanshitaだった。ため息の中に、まぬけで力ない声がまざった。
この作品を書く前、何者かの悲鳴が聞こえていた。「ここから出して。お願い。息が出来ない」と、声の主はそう叫んでいた。しまいには叫ぶだけでなく、頭蓋骨をかち割ってやろうと、脳ミソの硬膜を叩き始めた。「食道を下って血管の中に侵入し、お前の心臓を食べてやる」と彼女は私を脅した。私は、書き出した。出してやるから、静かにしてくれ、と願いながら。書いている途中、以前、一次予選にも通らなかった群像新人文学賞を思い出した。私にとってのブラックホールだ。書いた物をしっかりと吸い込み、責任を持って消し去ってくれる。ブラックホールへ異物を投げるのは有料で、400円ほどかかったと思う。10月31日の午後4時頃、東京駅近くの郵便局で、うるさかった声の主にしっかり別れを告げ、帰りの電車の中で、ようやくうとうとと眠りについた。私は、彼女と決別した。何を書いたかなんて覚えていなかったし、それで良いはずだった。私とはもう関係のないことなのだから。わざわざ読み返すことも、誰かに読ませることもなかった。
それなのに、一本の電話と共に、彼女はブラックホールから舞い戻って来てしまった。それも、呑気に美味しそうな飴玉を持って。携帯画面に表示された03という市外局番を見た瞬間、レンタルDVDの延滞連絡だと思った。「最終選考だなんて嘘だ」と叫ぶと、電話の相手は優しい声色で少し笑いながら、嘘でもツタヤでもないですよ、と言った。私は、その日の晩から漠然とした不安を抱き続けてきた。
この人生、一体何がどうなっているのか。呪われているのか、恵まれているのか。呪われているのだとすれば、その呪いをかけたのは自分以外の誰でもない。そんなことを考えていると、車内で正面に座っていた男性の帽子に書かれた文が目に止まった。Fear is often greater than the danger. その言葉を背に、私は護国寺駅で降りた。どうせなら、与えられたこの今世、作家として生き抜いてやりたい。ビルの前に立った時には、そう思っていた。
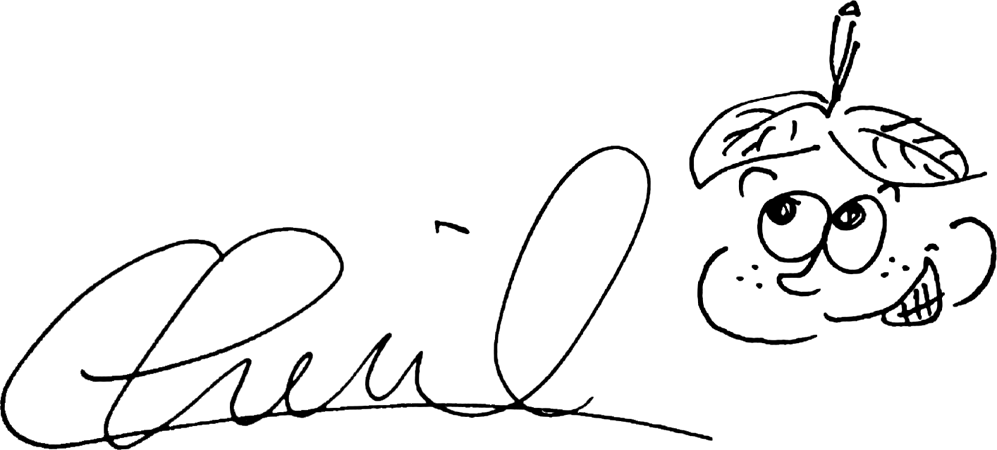
崔 実(チェ・シル)
1985年生まれ、東京都在住。
2016年、本作で第59回群像新人文学賞を受賞。
http://news.kodansha.co.jp/20160705_b01 より転載


