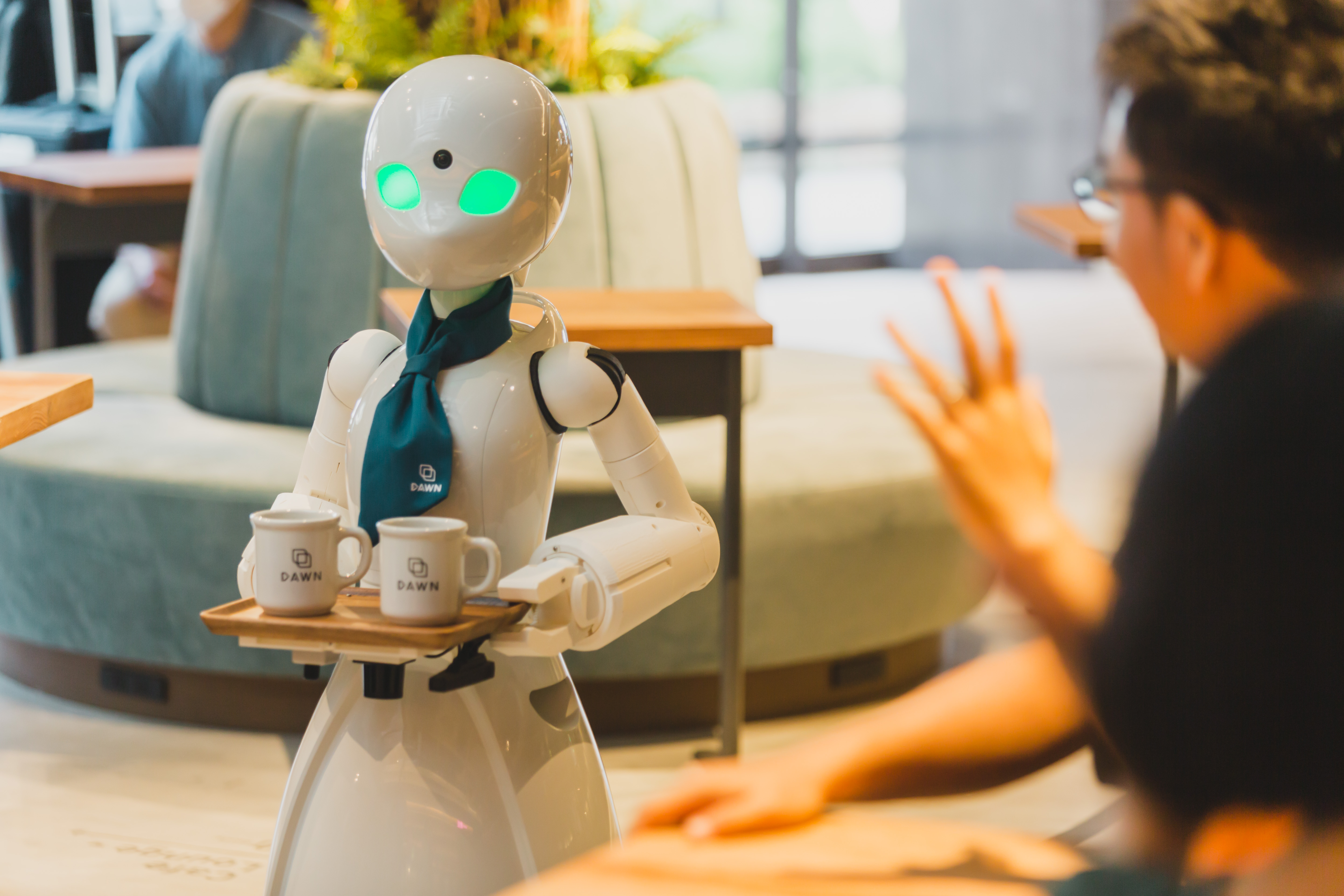***
人と違うことは悪いことじゃない。むしろ人と違う視点を持っていることは強みだ。「できないことがある」という点だって、自分の武器になることがある。
***
年始に読んだ、
田中美穂さんの
『わたしの小さな古本屋』。
この本の著者・田中美穂さんは、
企業勤めが向かないと思い、
20歳で古本屋を始めた人だ。
そんな彼女は人生経験を振り返って
「出来ることばかりが能ではない、
出来ないからこそ出来ることもある」
というふうに語っている。
なるほどなぁと感じ入った私は
この本が面白かったという感想を
会社で周りの人に話していた。
すると「自分が最近読んだ本にも
似たようなことが書いてあった」と、
吉藤オリィさんの『ミライの武器』を
他の方から貸していただく機会に恵まれた。
人と違うことは悪いことじゃない。むしろ人と違う視点を持っていることは強みだ。「できないことがある」という点だって、自分の武器になることがある。
読んでみると確かに、
まったくタイプの違う本なのに、
考え方にシンクロするところがあって
なるほどなぁと感じいった。
***
吉藤オリィさんは発明家で
ロボットの開発者である。
子供のころに折り紙が
得意だったことから
「オリィ」と名乗っている。
黒い白衣姿が目印。
彼は子供の頃に体が弱く、
入院をして休んでいるうちに
学校に戻りづらくなり、
不登校だった時期がある。
孤独の悪循環に陥っていたとき
唯一の楽しみは折り紙だった。
両親は彼にいろんなことを体験させたが
あるとき「虫型ロボット競技大会」に
出場したところ、偶然にも優勝する。
それがきっかけで
ロボット作りに没頭しはじめ
ほかの大会にも出場し、人と出会い、
もっとロボットの勉強をしたいと
進みたい道が見え始める。
***
印象的だったのは
【「なぜやっているの?」と考える。】の章。
高校2年生の時に
先輩たちの研究を引き継ぎ
車椅子の改良をしていた彼は、
JSECという自由研究コンテストに出場し
見事優勝、世界大会への切符を手にする。
しかしいざ世界大会に出場すると
同世代の16、17歳の子供たちが
「自分の研究を人生をかけてやりたい」と
堂々と胸を張って話すのを目の当たりのして
とてつもなくショックを受ける。
車椅子を作ることは自分が生涯をかけて
やりたいことなのかわからなくなり
「自分はなんのために生きているのだろう?」と
真剣に思い詰めた。
ヒントが見つかったのは、
日本に帰ってきて取材をひととおりうけて
「こんなことで困っています」
「こんな車椅子が作れませんか?」と
彼のところに問い合わせが届くようになってから。
彼は、視力の悪い人のために
メガネが当たり前になっているように
いま困っている人たちにとって
技術によって解決できる問題が
世の中にはまだまだあり、
自分がその一助を担えると気づく。
世の中は私が思っていたよりも全然完璧じゃない。世の中には、多かれ少なかれ私と同じく、社会に適応したいけれど、うまく適応できない人がいる。多くの人が、いろんな形の孤独に苦しんでいる。
(中略)
「私は孤独を解消するために生まれてきた」。そう言えるようになりたいと思い、残りの人生のすべてを「孤独の解消」に捧げようと決めた。
この考えは不安定な私の精神を安定させる上で、すごく価値のあることだった。「残りの命を使う目的」「まだ死ねない理由」を設定したことで、なにをするにもあまり迷わなくなった。
(中略)
「世の中は未完成で、生き方に正解はない。だから私にもできることがあるかもしれない」。なんの根拠もないただの勘違いだ。でも、そんな勘違いが、17歳の私を研究者の道へすすませた。
彼はその後も
高専に入って人工知能を研究したり
分身ロボットの「オリヒメ」を開発したり
相棒となる番田氏と出会って
もっとコミュニケーションをとるための
ツールに「オリヒメ」を改良していったりした。
さらに、オリヒメの開発をしていくうちに
寝たきりのALSの患者さんでも働ける
分身ロボットカフェの計画を実現した。
操作を覚えることができれば
遠隔でロボットを動かし
カフェの店員として働けるしくみだ。
最初は実証実験だった取り組みも
いまでは実店舗として日本橋にできている。
***
この本で著者は
あなたには「夢中になれること」が
あるだろうか?と問いかける。
これからの時代は
「人と同じこと」や
「我慢してやるべきこと」を
いくら上手にこなせても
生きていくのは難しい。
なぜならテクノロジーによって
世の中の課題はさまざまな形で
解決されていくようになるからだ。
一方で「夢中になれること」がある人は
この世界で見つかっていない
無数の価値や課題を見つけ、
人生に挑戦していける。
工夫によって、昨日よりも今日、「ひとりの人間ができることが増えた」なら、それは最先端のことだと誇ってもいいんじゃないか。
人の「能力」は、その人が持つ力そのものだと思われがちだが、実際は“喜ぶ人がどれくらいいるか”で計られている。
たった1人の人間では
「できないこと」がある。
これはどうしようもないことだ。
でも、1人が2人なら、2人が3人ならどうだろう?
たった1人の「好きなこと」が
つながってつながって、
誰かと誰かでなら
「できないこと」が
いずれ「できること」に変わる。
自分の「好きなこと」が
たくさんの人を喜ばす、
そんなきっかけになるかもしれないと
気づかせてくれる一冊だった。
***