湯浅譲二:箏とオーケストラのためのプロジェクション「花鳥風月」(1967)/ホワイト・ノイズに.../湯浅譲二
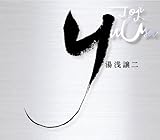
¥2,100
Amazon.co.jp
黛敏郎:七人の奏者によるミクロコスモス(1957 初演)/オーケストラのための「呪」(1967.../黛敏郎
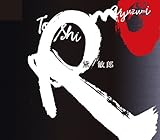
¥2,100
Amazon.co.jp
どちらも、
NHK「現代の音楽」アーカイブシリーズ
の最新版です。
このシリーズはとても貴重な録音がたくさん詰まっていて、
愛聴しています。
作曲者自身による談話も数分ずつ入っていて、
しかも今の談話ではなく、
作曲当時のものなので、
これもまた面白いです。
黛敏郎さんの談話で、いいなー!と思ったのは、この部分。
「いっさいの文学的ないしは、絵画的なイメージというものと、つながりを持たない」
そういう音楽を、音自身を組み立てて作っていきたいとおっしゃっているところ。
湯浅譲二さんの談話で、いいなー!と思ったのは、この部分。
能の影響を受けたという話の中で、
「音と、音のない休止。
休止というのは音を実態として把握させるためにあるのではなくて、
休止も音も同じウエイトでとりあつかわれている
という気が、私にはするのです」
私は無音が音と同じあつかいをされていることを
最初に、ヴェーベルンの音楽を聴いたときに感じて、
ものすごく衝撃的だったのですが、
たしかに、日本の音楽はそもそもそうかもしれません。
曲でとくによかったのは、
湯浅譲二さんでは「プロジェクション・エセムプラスティク」
ホワイトノイズでできている曲で、
昔、同じくホワイトノイズで作られた「イコン」という曲を聴いたときは、
その発想に驚いたものですが、
それに先行する作品のようです。
黛敏郎さんでは「カンパノロジー」は文句なしの名曲。
京都や奈良の寺院の鐘の音を使った曲です。
そして、今回、なんといっても感動したのが、
黛敏郎さんの「七人の奏者によるミクロコスモス 」(1957)(初演)
曲自体も、もちろんいいのですが、
感動したのは、そのいかにも前衛らしい前衛っぷりです。
前衛が前衛でいられた時代。
新しい試みはそれだけで価値を持ち、
「新しいことはいいことだ」と素直に思うことができた黄金の日々。
やってみたいこと、やるべきこと、
まだ誰もやっていないことが、山ほどあって、
もどかしいくらいの
黎明期の若々しい息吹を感じます。
映画で言えば、
メリエスとか、
そういうのを観たときに感じる感動です。
いい時代だったなーと、懐かしさを感じるのが不思議です。
1957年はまだ生まれてもいませんから。
ノスタルジーは、自分の知らない時代や場所にも感じる、
というのは本当ですね。