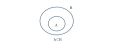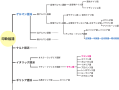↗️画像はウェブ検索からお借りしています
What do you call this in English?
🍞🍞🍞🍞🍞.
A what? A white bread?
Is that what you call them over here?
But that's what I mean.
In Japanese, we call them Shoku - pan.
(【ロンドンのベーカリーで目の前の1斤を指差して】これ英語でなんて言うん?
🍞🍞🍞🍞🍞て言うんやで。
なんやて? 白パンやて? へー、こっちではそう呼ぶねんな。
勉強させてもろたわ。
日本語ではこういうパンは食パンて言うねんけどね)
*単数形の「this」「that」が複数形の「them」で受けられている理由はなんでしょうか?
この記事全体がある意味その説明のためのもの、鴨♥️
イギリス英語の入門書紹介――役に立つのにお洒落で楽しい「イギリス英語」の招待状のようなもの
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/2387050ede4ca0a2947e1c5783157128
「食事」と「料理」で英語名詞の性質と役割分担を考える
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/56aaad6b64fecdd660ace8ae0904fda6
*本記事の「冠詞」の付け外しに関しては↗️この記事末尾の「おまけコラム」をご参照ください
>食パンは英語でなんと言う?
⤴️あるポータルサイトで見かけた記事のテーマです。
そこでの「解答」は「(a) white bread」になっていました。
面白いしこれも幾つかある「正解」の一つ。で、なにが問題なの?
英語研修屋さんから見てどこが「ちょびっと迷惑」なのですか?
まさか、①他の「正解」に触れていないから不正確とかの蘊蓄系の小言?
②実生活で見聞きする現物の指示対象を挟んで日本語と英語の単語に「一対一対応型の正解を想定するのは言語学的におかしい」とかは大人げない興ざめの揚げ足取りです❗️ ですよね。
その通り。もちろん、このタイプのクイズを作成する/楽しむ上で避けられない無理な難癖を
つけているのではありません。
英単語は2000語も覚えれば充分?⬅そんなわけないだろう❗ (*^o^)/\(^-^*)
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/58dcb4dfa601a3321646ab7d6bcf1029
「produce」の日本語の意味から見えてくる英単語増強のTips
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/bff0232cf99fd0edb87f7738e76a13b5
英単語を覚えるには諦観と気迫ですーー「短期記憶・長期記憶」談義のその先へ
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/71dfff5f7a1c019a7ab58ced83266b3b
この記事の要点は(上の↗️【ちょびっと迷惑とまでは言えない①②の】②の一斑あるいは延長線上ではありますが、そして、「食パン」は「a tin (bread)」とも言いますし、単に「(a loaf of) bread」が寧ろ普通、鴨。とかとか①をどれだけ丁寧に補足しようとも)、このタイプのクイズは英語のコミュニケーションスキルを開発する上で障害になりかねないーーしかも、そこに陥ったら冗談抜きに日本で生まれそだった日本語母語話者には修正が難しいーー思い込みに読者を誘導しかねないというもの。
それは、その【ちょびっと迷惑と言えること】とは、例えば、この「食パンは英語でなんと言う」クイズが、①日本語でも英語でも「食パン」なり「a white bread」が各々幾つかあるだろう他の同意語・類義語の存在をスルーしていること、②それらの同意語・類義語は各々日本語と英語の語彙の意味の平面で住み分けていること。すなわち、両者が意味論的な、つまり、辞書的に、ある単語が語義ルールの体系の中で占める位置と位相の問題とは、 まったく別に
まったく別に 、
、 ①②に加えて
①②に加えて 、
、
>「食パン」が日本語の単語の運用ルール体系の中で占める位置と位相と
>「a white bread」が英語の単語の運用ルール体系の中で占めるそれらは
>非対称的である。それらは縁もゆかりもありませんということなのです
もう眠くなりましたか? ということで急がば回れ、まずは、前者①②、ある自然言語の「語義ルールの体系の中である単語が占める位置と位相」の問題なるものの説明からはじめます。言い換えれば、はい、それは文字通り「辞書」の説明に関わること。
例えば、「bread」は「food made of flour, water, and yeast mixed together and baked. 小麦粉と水と酵母を一緒に混ぜたものを焼き上げてできた食べ物(Paperback Oxford English Dictionary)」,「a common food made of baked flour, 焼き上げた小麦粉でできた皆さんお馴染みの食べ物(Longman Dictionary of Contemporary English)」,「a food that is made with flour and baked in an oven,オーブンで焼き上げた小麦粉を使った食べ物 ↖️これは英国の小学生向けの「国語辞典」の説明ですけれど、関係代名詞の導く形容詞節によって限定修飾されているので通常は不可算名詞の「food」に冠詞が付いていることに注意してください (The Usborne First Illustrated English Dictionary and Thesaurus)」。そして、本邦の「ジーニアス英和辞典第5版」の「bread」の項目にはこうあります。
*bread 関連
(1) 食パン以外の【「クロワッサン:croissant/crescent」を含む】小型パンは roll, 「フランスパン」はFrench loaf, 「丸パン」はbun という. (2) パンの「皮, みみ」は crust, 中は crumb
ちなみに、「ベーグル」は bagel. 「菓子パン」と「惣菜パン」は各々 sweet(ened) bun/roll/bread と stuffed or savoury bun/roll/bread. また、英国では「柔らかい小型ロールパン」のことを bread roll(s) や bun(s) よりも寧ろ bap(s) と言います。
尚、われらが「あんパン」は「sweet bean bun(s), red bean bun(s)」ですが、これは遡れば説明的英語。つまり、アメリカ人やイギリス人の方が本国の街角でそう呼んでいるというのではなくて、逆に、例えば、知人のアメリカ人からあんパンを指差して「これなんてゆーねん?」と聞かれたときに日本語母語話者のあなたが説明する際の英単語なのです。だから、正式には「Japanese sweet red bean bun(s)」が正解なの、鴨。
而して、日本語の、よって、日本の実物の「食パン」(および、所謂「イギリスパン」や「サンドイッチパン」)は確かに a white bread あるいは a tin bread と呼ばれている。というか「roll, bun, bap, bagel, French loaf」や「菓子パン」とか「惣菜パン」ではないパンという意味で、繰り返しますが、「食パン」は単に bread と呼ばれるのがイギリスでは、そして、アメリカでも普通かもしれません。
大事なことなので確認しますが、最後の場合には「bread」と発話したその英語の母語話者さん、イギリス人の彼女さんやアメリカ人の彼氏さんの脳内では「bread」は日本語で言えば、所謂「パン類の総称」と「食パン類の名称なり総称」の広狭の一人二役を演じているのです。
このような「辞書的の意味」からも、蓋し、①②の点で、「食パンは英語でなんと言う?」➡️「正解は (a) white bread ですよ❗️」というのは些か舌足らずの説明だとは言える。
しかし、この不正確さ不十分さは冒頭に述べたようにそう大した問題ではない。この小言は、例えば、「potato は日本語でジャガイモと言うのですよ」という説明に対して「おいおい、馬鈴薯とか男爵/メークインあるいはポテトと言う人も希ではないですよ🐙」とか「soy sauce は醤油と言います」に対して「あんた田舎者かいな? soy sauce はムラサキに決まっとるがな❗️」とか難癖をつけるのと大差ないでしょう。いずれにせよ、このタイプの不正確さや不十分さに起因するコミュニケーションの停滞や齟齬は都度聞き返せばよいだけの話なのですから。違いますか?
定義の定義-戦後民主主義と国粋馬鹿右翼を葬る保守主義の定義論-
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/0fb85611be79e7a89d274a907c2c51ac
而して、クイズ「食パンは英語でなんと言う?」問題の問題点は「運用ルール体系の中である単語の占める位置と位相」を巡る事柄に収斂する。そうわたしは考えます。で、任意の自然言語を想定するとき、その「運用ルール体系の中である単語の占める位置と位相」の問題ってなんですか、ですと? それ美味しいのですか、ですと? はい、これまた急いては事を仕損じる。ここも①②の「語義ルールの体系の中である単語の占める位置と位相」の説明。具体的な事例を設定して説明しましょう。
同意語と類義語の存在。例えば、「襟巻き」と「マフラー」、「ズボン」と「パンツ」、「電子計算機」と「コンピューター」、「終点の停車場・駅一階構内」と「ターミナル・ピロティ」、「ミカン」と「オレンジ」、「果実」と「フルーツ」、「菓子舗」と「コンフェクショナリ」、「複合商業施設」と「モール」、「焼き飯」と「チャーハン」と「ピラフ」・・・。これらは時代とともに日本語の語彙の意味平面でその境界線を動かしながらーー指示対象の囲い込み奪い合いを繰り広げながらーー住み分けています。
而して、例えば、「restaurant:レストラン」と「restore:健康や権勢を回復する」はラテン語由来の「re:再び」+「store:元気にする」からできた親戚の単語ですとか。あるいは、「river:川」は大元のラテン語では「川の土手(bank)」の意味の単語で、なんと「rival」は「同じ土手(bank)の向こう側とこっち側で同じ川の水を使っていた(水争いを繰り広げてきた/関所の通行料金の配分を争ってきた)部族や村落の人々」の意味から現在の「ライバル」の語義を発展させたのですよ。
そもそも、「bread」はゲルマン語由来の古英語期に遡る由緒正しい英単語で「a bit=一口の食べ物≒命を明日につなぐありがたい一口の食べ物」が元来の意味だったのですよ。とかとか語源や地理学、人口統計学や貿易論の切り口などからの通時的の情報を加味しながらーー更には、加之、その当該の単語を含むセンテンスが置かれているコンテクストがフォーマルかカジュアルかそれらの中間か(whether formal, casual, or something in between)にも目配りしながらーーいろんな単語の現在の共時的な意味の由来と住み分けの状況(位置と位相)を調べるのも楽しいものです。
・英語史的文法論の要点覚書--異形の印欧語「現代英語」の形成、それは「格変化」の衰退から始まった
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/91718985f1a5d1b7df4c7485a966c123
・中尾俊夫『英語の歴史』⬅今でも最高の一般向け英語史、鴨。読みやすくはないけれど🐙
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/f64de3ba90ee36bde0927619de3a4cd0
他方、「a white bread」と「a tin bread」のイングランド内の地域的な使用頻度なり使用階層や使用年齢層ごとの使用選好を調査をする。あるいは、日本語の「パン」は安土桃山時代前後にラテン語経由のポルトガル語から借用された言葉であり(ラテン語由来の「panis:元気にするもの/餌をほどこす」が原意の「pao」を取り入れたもの。ちなみに、「カステラ」の語源は、岡山の「吉備団子」じゃなかった広島の「もみじ饅頭」でも太宰府天満宮の「梅ケ枝餅」でもない、同じくポルトガル語「pao de Castelra=【スペインの】カステラ公国地方名物のパン」らしいです)、な、な、ナポリじゃなかった、なんと、イタリア語ではこの「panis」は「pasta」=「🍝パスタ🍝」になって現在にいたってます・・・。
とかとかを文献を猟歩して/文字通り足を使って確かめる。これらの営みと企てが、単語の意味に関するこのようなタイプのアプローチが本記事で言う、ある自然言語の「語義ルールの体系の中である単語の占める位置と位相」の説明です。では、いよいよ、はい、ある自然言語の「運用ルール体系の中である単語の占める位置と位相」とはなにか?
The laws of grammar are like the laws of any other science, simply generalized statements about what does happen, not directions about what should ー and they are subject to change as soon as new evidence comes in.
(文法の法則は、他のすべての科学の法則がそうであるように、これから起きるはずのことについての指示・説明ではありません。それは実際に目の前で生起している事柄を一般的に説明するものなのです。而して、新しい証拠が現れれば、それらの法則は直ちに修正されなければならない類いのものでもあります)
(出典:中原道喜「英語長文問題精講」p.97, B. Foster「The Changing English Language」chap.5)
ある自然言語の「運用ルール体系の中である単語の占める位置と位相」。もちろんそれは、1️⃣英語で行われる実際のコミュニケーションの中で実証的に確認されるものであって/そのコミュニケーションの場面で使われたその英単語の意味を決める something であって、2️⃣浮世離れした神通力や傲岸不遜なリベラル派の教条とは無縁なもの。他方、3️⃣その単語を発話したご本人にしかわからない生いたちなり極私的な経験に専ら起因する類いの仕掛けでもありません。
結論の一部を先取りして言うと、それも結局は「語義ルールの体系の中である単語の占める位置と位相」を記述する「辞書に記載可能な情報」ではあるのです。ということで、実話三連投入の後、銀の竜の背に乗って結論に向かいます、多分。
The most important thing in communication is hearing what isn't said.
(コミュニケーションに際して最も大切なこと、それは語られないことに耳を澄ますこと)
(By Peter F. Drucker)
We had mutton stew and pie-plant for lunch ー hate 'em both; they taste like the asylum.
(昼食の献立はマトンのシチューとルバーブ、両方とも大嫌い。だって孤児院風味なんですもの)
(Jean Webster「Daddy - Long - Legs」Letter 13 (maybe, should be Letter 15), FR, after April 4th)
🐲A:味の素とカップヌードルの反乱🐲
大学時代の彼女さんに、味の素はもとより人工の調味料(artificial seasoning)、まして、インスタントラーメンなどは御法度なヘルシーで環境に優しい食生活をむねとするリベラル派のハイソなご家庭出身の方がおられました。そして、中学生の反抗期、彼女はおこづかいで「カップヌードル」を買ってきて、お母さまと3歳下の妹さんの見ている前で完食。カップヌードルの乱。さて、この反乱以降このご家庭における「カップ麺」という単語の意味(connotation)はどうなったでしょうか?
カップヌードルとナショナリズム
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/059bfa6bce2926c4e0d25cd62aa17807
🐲K:コッペパン1個に涙する会社社長🐲
KABUの趣味の契約農地仲間に地元の超優良中小企業のオーナーがおられる。この社長さん、お茶休憩の時によくコッペパン(Koppe - pan≒a bread roll↖️語源不明🥖)とか食パンを微笑みながら美味しそうに召し上がられる。ある夕刻、お孫さんの進学相談をしたお礼にと社長に誘われた。その入った寿司屋さんでついにその訳を聞きました。
はい、彼は秋田のかなり奥まったエリアのご出身。農家の三男坊で家には米は文字通り山ほどあるが、小学生になり給食で生まれてはじめてパンを食べてその美味しさに涙したとか。これが日本が戦争で負けたアメリカ人が毎日食べているというパンか❗️ そんなことより高校出たら東京に出て働いて働いて働いて腹一杯パンを食べてやる🔥 と、成績優秀だし家には金もあるから⛪️大学⛪️に行けと親兄姉に言われても初志貫徹。でもって、三十半ばには毎朝「社長❗️ 金借りてください💰️」とたのみに来る銀行員で玄関前は満員御礼状態になっていたとか。はて、このご家庭や会社の従業員さんの間で「コッペパン」や「食パン」の帯びる意味(connotation)はどんなものでしょうか?
福岡県大牟田市:松屋デパート「洋風かつ丼」復活が孕む思想的意味
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/9ffb70a94181ada4d3527ae2bc548d25
小さな<窓>からも空は見える-日本再生のケーススタディーとしての福岡県大牟田市の菓子舗だいふく物語
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/2dcd3dfb908582c9cd5581881d5a6187
🐲B:今ではネズミも跨ぐ? でも、憧れのバナナは永遠🐲
歳がばれる自分たちの話し。前の東京オリンピックもかすかに覚えているわたしにとって「バナナ」は憧れの高級果実でした。実は、これフイリッピンバナナ輸入大手商社の元担当者さん(👦教え子さん)に調べていただいたから間違いないと思いますが、間違いなく1960年代の半ばまではその家庭の可処分所得やら資産に関わらずそうだったはず。なぜならば、輸入🍌🍌の総量制限と渡航便数制限がまだあったから。
ということで、年に何度か母親が数房の🍌🍌🍌(two or three hands of bananas)を買ってきたとき、その夜、亡くなった祖母もまだ元気で家族でその幾房かのバナナをいただいた信じられないくらいの幸福感をくっきり覚えています。それが今では子供も喜ばないネズミも跨ぐバナナ😢 近所のスーパーでも、一房180円、閉店間近には一房80円👀‼️ けれど、わたしは借りている書斎兼書庫で時々🍌🍌をいただいています。そこそこの幸福感を覚えながら。どうでしょうか? こんなKABU家とこの話が耳タコのKABUの弟子のご家庭での「バナナ」の意味は? 🍌🍌🍌に憑依する意味(connotation)は?
[再掲]カレーライスの誕生★カレーの伝播普及が照射する国民国家・日本の形成
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/d7b5503b7aaa15c9c35d87c7a4cb7255
確認ですが、実話三連の中の「味の素」や「カップ麺」、「コッペパン」や「バナナ」のコノテーションはーー「オリーブの葉 or 鳩➡️平和」「ペンと剣➡️言論と武力」等々、表面的な語義に加えて常に同時にある単語に憑依する裏面の語義のことを「connotation」と呼びますーー、3️⃣「その単語を発話したご本人にしかわからない生いたちなり極私的な経験に専ら起因する類いのもの」に尽きるわけではありません。
それらは、🍜🍥第二次大戦後に西欧社会に吹き荒れたフェミニズムやらエコロジーやらに憧れた日本のハイソなリベラル派のニューファミリーが文字通りその足元からその義慢性を突きつけられていた70年代前半の(日本語母語話者の多数派ではないにせよ、それなりのポピュレーションの)日本語母語話者にとっては痛みをともなう公共的な語義だろうから。🍞🥖終戦後の地方出身者の少なからずにとっての「コッペパン」「食パン」の公共的な語義の一斑だろうから。🍌🍌わが家だけでなく「バナナ」に好ましい思い出を重ねる世代は現存しているだろうから。
畢竟、ならば、それらの語義は、辞書の説明の中では各々の単語においてかなり後ろの方に来るとしても間違いなくある単語の公共的な意味の一つではあるのです。蓋し、そして、「食パンは英語でなんと言う?」類いの記事の、英語でする異文化コミュニケーション能力開発においてちょびっと困る契機がこのことから生じる。どのように? はい、そのどれもが正しい「食パン」の語義のどれとして話者はさっき「食パン」と発話したのか? これどうやって判定しますか?
この判定には単純に二つの解決法が思い浮かぶ。どの単語についても論理的には無限に書きたされる語義の選択をどうするか? その二つの道は、【壱】ポータブルの🖥️スーパーコンピューター🖥️を持ち歩く、あるいは、【弐】鏡の国のアリスの白の👸女王👸さまの叡智に助けを求める(ask for 「the mental equipment of the White Queen in Alice」, Agatha Christie「N or M」, chap.2 )。
これ真面目な話しですよ。でも、真面目な話し、この両者とも現実的ではないだろうし、更に重要なことに論理的に採用が不可能なのです。
前者は説明するまでもないでしょう。それは学ぶにも運用するにも扱いにくいでしょうから(to be cumbrous and difficult to learn and apply) 。後者はもっと簡単な理由からそう言える。要は、スーパーコンピューターさんや白の女王さまの「回答」が「正解」であることを生身の人間である日本語母語話者にはーー実は、TOEIC 860点ゲットに必要だろう10000語を遥かに越える、約20000語を覚えているとされる英語の平均的なネーティブスピーカーにも、更には、25000語から30000語を使いこなすインテリのネイティブスピーカーさんでさえ❗️ーー判定できないからです。
*ちなみに、この「ワード数」はかなり曖昧です。実際、例えば、単純系の副詞(close, hard, high 等々、語尾に副詞を示す「- ly」などのない、派生元の形容詞と副詞が同じスペルの副詞)は日本の出版社の辞書では1語とカウントされないのに対して英米の辞書では分家が認められて都合2語とカウントされる傾向があるくらいですから。
ということで、ここからが問題です(Here's the thing.)。 ここに至って発想の転換が求められる。そう、諸々の同意語・類義語が縄張り争いを続けている語義の平面から飛びたたなければなりますまい。銀の竜の背に乗って。その「銀の竜」こそーー当該の単語が実際に運用された場面を注視するーー「運用ルールの体系」と本稿でわたしが呼んでいるものです。
而して、ウィトゲンシュタ、H.L.A ハート、ならびに、分析哲学日常言語学派の知見が教えるところによれば、究極的には、あるルールの存在はそのルールが破られた際の世間と社会の否定的な反応が生じるかどうか(≒そのルール破りがそれに対する批判非難を惹起するかどうか)でのみ確認できる。簡単な話です。要は、ある単語は運用の実際においてのみその当該のコミュニケーションに際しての語義を知りうる。例えば、
温厚なオーナー経営者にまずまず取り入っていた(と、ご本人は思い込んでいた)銀行のアカウント担当者(account representative)さんが、ある日突然、出入り禁止を通告された。その前日、昇給昇進を人事部から知らされた駒澤大学卒32才の平の営業マンさんと、地元の高校卒業以来勤務している(途中、全日制簿記学校に社命で2年間通い税理士免許取得した)44経理課主任さんが(特に、後者は二階級特進で執行取締役兼任の経理部長への栄進♥️)、そのお二人が社員食堂でしみじみ嬉しそうに「食パン」食べているのを見て、「お祝いが食パンですか? 業績絶好調の御社らしくない❗️ わたしが今度、銀座でも評判のコンフェクショナリかベーカリーでお二人になんか買うてきましょう。それにしても、オーナーさんケチなところもあるんですね」と言っただけなのに。
はい、実は、これ⤴️実話です。そして、普通なら「お寿司」でもとってお祝いしてもおかしくない場面で食パンでお互いに喜びを分かち合っている異様な光景を目にしたのならば、そこに耳を澄ますべき「語られていない何か」の存在をこの銀行員さんは感じなければならなかった。そして、あなたもこの現象を観察したならば、そこに「食パン」に憑依するなにか普通ではない語義を経験的に察知されるでしょう。そうではありますまいか。
おそまつさまでした。以上