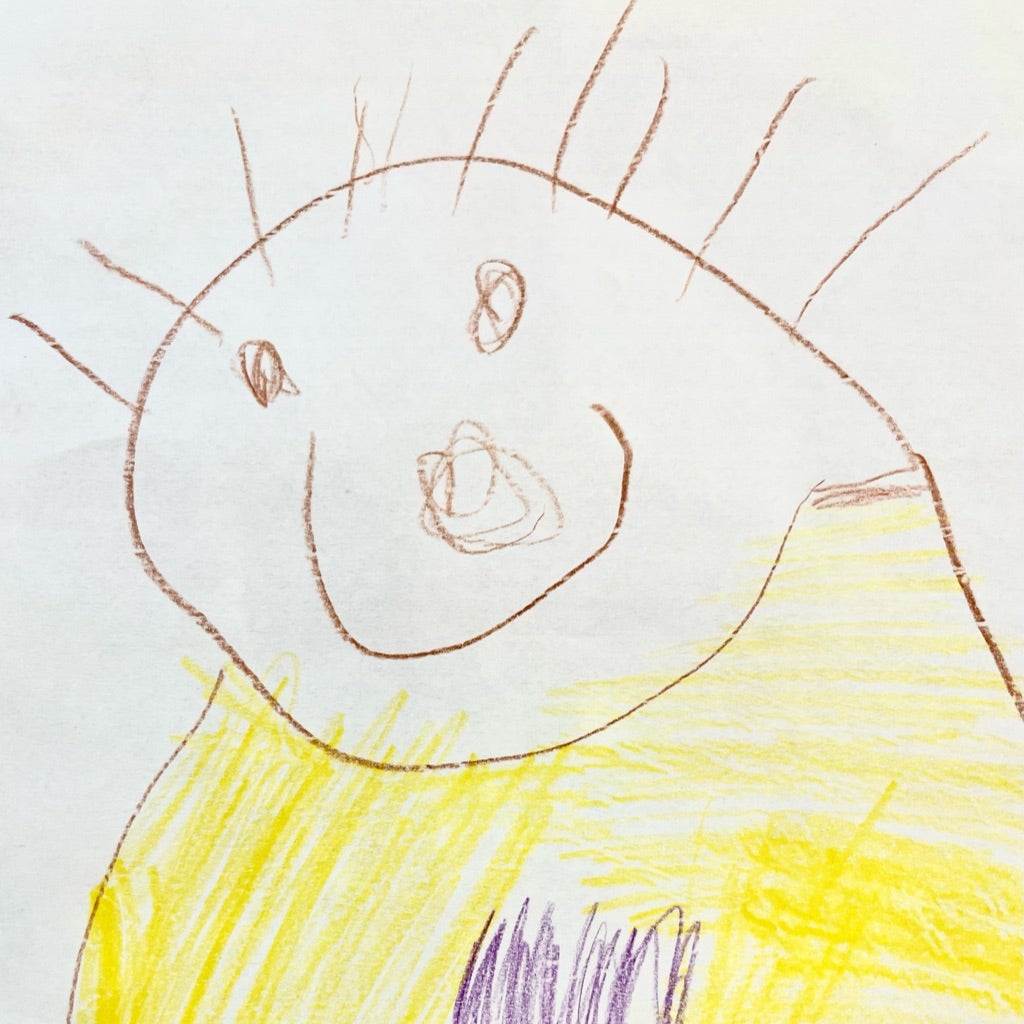(1)
の続きです
就学先の決め方
誰でも行きたいところに行けるわけではない
→法令などで基準が規定されている
困難の程度が各基準に該当する場合に特別支援学校や特別支援学級に通級したり、通級指導を受けたりすることができる
子どもの状態を把握し、基準に該当するかどうかを検討することが必要
検討→園・市町村・都道府県の就学支援委員会の役割(ただし就学時に決定した「学びの場」は固定したものではなく、そのぞれの児童生徒の発達の程度・適応の状況などを勘案しながら柔軟に転学できる)
就学先決定のための観点
知的障害の場合
①知的発達
- 知能検査や発達検査の数値
②他人との意思疎通
- 話の内容の理解の程度(一斉指示・個別指示)
- 意思の表出
- コミュニケーションの状態
③日常生活動作
- 食事、排泄、衣服の着脱、移動などの日常生活の基本動作に対する援助の頻度が「頻繁」なのか「一部」なのか判断(頻繁な場合、支援学校適)
※「頻繁」とは、一定の動作・行動の意味、目的、必要性を理解できず、その年齢の発達段階で標準的に要求される日常生活の行為に、ほとんどの場合または常に援助が必要である程度のこと
食事時頻繁な離席、極端な偏食、異食、食べ物で遊ぶ、手掴み食べ、排尿・排便の失敗あり(おむつ着用)、清潔意識なし、排泄しても伝えない、衣服の前後左右意識なし、声掛けしても自分で衣服の着脱ができない、移動時要手繋ぎ、飛び出しあり、目的地がわからないなど
④社会生活への適応
- 対人関係、行動特徴が「著しく困難」なのか「困難」なのかを検討する(著しく困難な場合、支援学校適)
※著しく困難な場合とは、
対人関係
視線が合わない、他人に興味がない、誘われても応じない、他害あり、不適切な関わり(抱きつくなど適切な距離が掴めない)など
行動特徴
過敏が強い、こだわりが強い、多動、自傷行為、異食、離席が多い、危険認知がない、パニック、ルール理解困難など
自閉症の場合
特別支援学級
- 自閉症またはそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの
- 自閉症またはそれに類するもので、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの
特別支援学校
- 上記知的障害の場合の①〜④に準ずる
園・市町村・都道府県側からみた
就学の流れ
①年少〜年中
園側は就学支援が必要な児童(普通学級で困難さが出る可能性がある児童)を把握
※親は、就学に関して心配がある場合、年少〜年中のうちに園の先生へ相談しておくとよい
②年長4月頃
教育委員会から各園などに「就学支援が必要と思われる子ども」についてアンケート調査を実施
①での園の先生への相談が教育委員会に引き継がれ、就学支援体制の基礎となる
※年中後半〜年長4月頃までに発達検査を受けておくと良い
親の中で就学先の意向を家族で話し合っておく
③年長5〜6月頃
就学支援員による園訪問の実施
相談支援員はその際に子どもの困難の状態を把握し、適切な学びの場を考えていくための情報収集をする
※親は、療育の記録や医療受診の記録は、その都度各園の先生に伝えておくと就学支援員の情報収集もスムーズになる
④市町村就学支援委員会の開催
就学支援委員会:医師・特別支援学校教諭・特別支援学級教諭・通級指導教室教諭・各園の先生・福祉関係者などにより、困難さのある子どもの教育に関して専門的な検討を行う場のこと
訪問した園児一人一人について、必要な支援や適切な学びの場について検討する
親と子と面談し、親側の意向確認も実施する
⑤特別支援学校に就学する場合、県専門調査
第1次・第2次と2回の機会がある
- 子ども:別室で発達検査実施(発達検査の結果は親は知ることができない)
- 保護者:聞き取り調査
⑤最終的に12月末までには就学先決定
市町村・県の検討内容と親の意向が合わない場合、市町村と何度か面談を繰り返すこともあるが最終的には12月末までに就学先を決定する