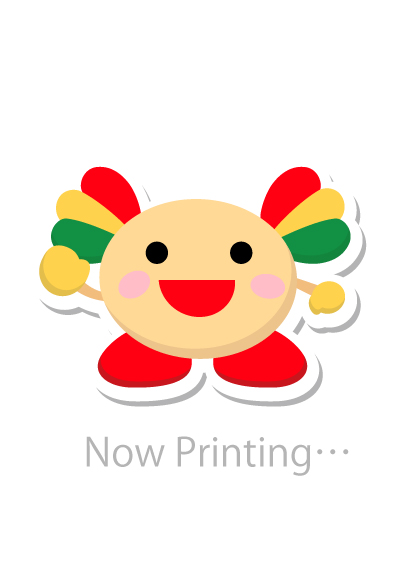◆伊藤貫『中国の「核」が世界を制す』を読み解く(その1)
★要旨
・本書は、
二十一世紀の日本が独立国としての地位を維持するためには自主的な核抑止力の構築が必要であることをはっきり指摘しているから、
反核感情の強い「反米左翼」や「リベラルな市民派」の立場をとる人たちとも、
外交視点が異なる。
・二十一世紀の日本は、自主防衛政策と日米同盟維持政策を両立させる戦略的必要性があることを説明する本書は、
いままでの日本の保守派・革新派双方の外交政策論とは明らかに異質なものである。
・戦後の日本の外務官僚・防衛官僚と国際政治学者は、
アメリカの政治家・官僚・軍人・学者等と、
「核の傘」の有効性や日本の自主的核抑止力の可能性に関して、
真剣な議論をしてこなかった。
・筆者は、一九八〇年代末から現在まで、
国務省・国防総省・CIAのキャリア官僚、
連邦議会の軍事委員会と外交委員会のメンバー、
そして米国の著名な国際政治学者たちと、
「核の傘」の有効性や日本の自主的核抑止力の必要性に関して議論をしてきた。
・本書は、中国の覇権主義の危険性を説明し、
日本国には自主的な核抑止力が必要であることを指摘する著作である。
・つまり本書は、
「日本の核武装」という、戦後の日本社会でタブーになってきた問題を真正面から議論する書物である。
・核兵器に対して感情的に反発する人が多い日本で、
「なぜ、二十一世紀の日本には自主的な核抑止力が必要なのか」という議論をするためには、
外交政策と軍事政策に関して論理的な思考パターンが存在することを
読者に理解してもらわなければならない。
・現在の日本は、重要な岐路に立っている。
一九九一年以降の国際政治構造は、表面的にはアメリカが世界覇権を握る一極構造になっているが、
現実には、EU、ロシア、中国、インド、イスラム教諸国が、
米国覇権に対する依存度を低める動きを続けている。
・国際関係を理解するために必要なパラダイムは二つである。
リアリスト・パラダイムとウィルソニアン(ウィルソン主義)パラダイム。
この二つの外交パラダイムのうち、
戦後の日本人に理解しやすいのはウィルソニアン・パラダイムである。
・日本の学校の歴史・政治経済の教科書で使われている
平和主義的な外交解説のパターンはウィルソニアンであるし、
外務省官僚や外務大臣が国民に日本外交を説明する際にも、ウィルソニアン的な解説をつけることが多いからである。
・ウィルソニアンというのは、
「国際法強化、国際組織の充実、経済の相互依存性の増大等が進めば、
世界の諸国はお互いに戦争しなくなる」と考えるパラダイムである。
・「理想主義的」なウィルソニアン・パラダイムと
対立する「現実主義的」なリアリスト・パラダイムというのは、
「強制執行能力を持つ世界政府や世界警察軍が存在しない現状において、国際法と国際組織に期待・依存するのは現実的ではないから、
バランス・オブ・パワー(勢力均衡、
とくに軍事力の均衡)を崩さないように国際関係を運営するのが、もっとも手堅く安全なやり方だ」
と主張する考え方である。
・第一次大戦後の国際連盟や不戦条約(一九二八)は、
米英仏独伊日ソ等の列強諸国の帝国主義的な軍事行動を阻止できなかったし、
第二次大戦後の国際連合も、安保理の常任理事国は拒否権を使用(濫用)することにより、
「自国の侵略行為と戦争犯罪行為は、安保理の議題に載せない」(常任理事国である米英仏中露五カ国は、何をやっても処罰されない)
という状態であるから、
現実の国際社会において国際法と国際組織が本当に戦争を防止する機能を持っていないことは歴史的な事実である。
・リアリスト派が、
「ウィルソニアン派の主張はとても立派な理想論だが、現実の世界で戦争を防止する機能を果たしているのは彼らの立派な理屈ではなく、
むしろ諸国間の軍事力の均衡、つまりバランス・オブ・パワーではないか」
と指摘する時、
リアリスト派の議論には説得力がある。
★コメント
腑におちる論文である。
学びたい。