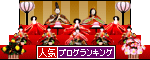法学の世界というのは,言い換えれば,この世を「権利と義務」で捉えるということでもあります(拙稿「法の『体系』」参照)。したがって,「自由」という言葉も,一度法学の世界に身を置いてしまえば,「権利」(もしくは「義務」)に関するものとして理解されなければなりません。
このことが何を意味しているのかといえば,「自由ですら制約され得る」ということです。つまり,完全無制約の「自由」というものは存在しません。自由の定義は,通常「義務のない状態」を指すのですが(拙稿「権利論の基礎」参照),この義務には,作為義務(○○をせよ)だけのみならず不作為義務(××をしてはならない)ということを含んでいます。昨今話題になりがちである「表現の自由」に関していえば,「○○と言え」と言われることはないだけでなく,「××と言ってはならない」ということもないということを含意せざるを得ません。
そうだとすると,ただちに,脅迫罪(刑法222条)や名誉毀損罪(刑法230条)の存在に突き当たってしまいます。つまり,従来より,他人の「生命,身体,自由,名誉,又は財産に対し害を加える旨を告知」すること(刑法222条1項)は脅迫罪とされ,「人の名誉を毀損」する者(刑法230条1項)は名誉毀損罪とされるとすれば,すでにこれらの「表現」は(刑罰を背景に)「禁止」されていることになる以上,「自由」の定義と衝突せざるを得ません。
法学が「権利・義務」を中心に構成するものだとすれば,表現の自由とは,「そのような表現をする『権利』があるか」,あるいは,「そのような表現を『禁ずる(不作為義務を課す)』理由があるか」ということです。これに対して「自由なのだから無制約だ」というのは,法学的には,問題を捉え損ねています。
焚書が1つの表現とみなされるとすれば,殺人すらも表現だと見得る契機があることになります。しかし,「わが殺人はアートである(故に無罪)」という抗弁を認めることはあり得ないでしょう。それは,「殺人はアートではない」から(だけ)ではなく,「人の生命に表現の自由は劣後する」からです。この時点で,「自由」それすらも他の価値と優先劣後関係を持っていることが明らかになります。それを,「自由」という言葉の形式的な意味にだけ拘泥し,「絶対無制約」のものと考えるのは,最低限の検討すらされていないとのそしりを受けざるを得ません。
「自由」すら,「社会契約」の文脈で捉えるとき,その意味内容は「社会契約」によって決せられています。「人々の『自然状態』での闘争を回避しようと国家(社会)を作る」という契約の中でのみ「自由」は意味を与えられており,この社会契約の趣旨に反する「自由」などありはしないのです。