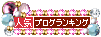そういえば冬季オリンピック中ですね。いろいろと半端に書くのも問題があろうかと思われますので、来週あるいは再来週にまとめて雑感を残す程度で足りるでしょう。
昨日の拙稿では、「法を離れた『善』のようなものは、およそ法の領分ではありません」と論じ、また「規範の内面化」においても「規範はまず必ず『外』から与えられるものである」と論じました(また、拙稿「法が生んだ『幸せ』の形」も参照)。そのような、「規範」や「法」を与えるものに、「文学」や「神話・伝説」もあるというべきでしょう。
『契約法』(有斐閣・1974年)で著名な来栖三郎博士(1912年~1998年)は、「文学における虚構と真実」(同『法とフィクション』(東京大学出版会・1999年)収載)の中で、「私は小説を殆ど読んでいないし、ごくわずか読んだ小説は十九世紀以前のものであり、いわゆる二〇世紀小説はさっぱり読んでいない。」という記述が見られます(前掲書155ページ)。
他方で、同書に「余白に」という小稿を寄せた木庭顕東京大学名誉教授は、自著で、占有を土台とする法という概念は究極には形態的感覚的概念であり、論理ではなくイメージによってよく感得されるという趣旨をあちらこちらに示されています(例えば、同『新版ローマ法案内』(勁草書房・2017年)9ページ参照)。実際に国内外の多くの説話や神話などに触れるにつけ、それは実感を伴います。
では、法学の分野としてそのようなものの分析はなされていないのかというと、近時「法と文学」という分野がやおら目を向けられ始めてきました(近時であれば、明治大学の小林史明講師がその旗手といえるでしょうか。氏の「法と文学」に関する紹介として、「法と文学」長谷部ほか編『現代法の動態』(岩波書店・2014年)197ページ以下)。もっとも、この「法と文学」という名の示すように、それはある程度のまとまりを持ちながらもいまだ雑然とした状況にあるのかもしれません(もし刑法と言わずに「法と犯罪」とか「法と刑罰」と言えば、そこでは刑法学のみならず、犯罪学や犯罪心理学、哲学などが入ってくることが予想されるのと同じです)。
法の根源を慣習法に求めるとき(例えば、石田喜久夫『民法学事始』(弘文堂・1985年)参照)、仮に当該の規範が法的確信にまで高められ、かつ法執行に適したものであれば、それは法規範としての通有性をもつこととなります。つまり、おとぎ話や神話の中で示された規範が人々の中に根強く息づくとき、それが裁判所をはじめとする国家権力によって強制することができる性質のものであれば、そのおとぎ話や神話は「法」を取り扱っているといえるのです。
法と倫理は区別されるべきですが、法をすべて「○法○条に記載されている」という意味での「成文法」のみであると理解することは、言わずもがな、これも誤りなのです。