エウレカの確率 経済学捜査員とナッシュ均衡の殺人/石川 智健
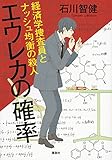
¥1,620
Amazon.co.jp
向山製薬に起きた「人体実験が行われている」と警告する怪文書の犯人を捜していたコンプライアンス課の玉木は、捜査対象の希少疾病第2部門で起きた課員の事故死に不信感を抱いて捜査にやってきた経済学捜査員という肩書の刑事の伏見に出会う。2人は、連れだって事件の捜査をすることになる・・・。
エウレカは、ギリシャ語のεὕρηκα(見つけたの意味)でアルキメデスがアルキメデスの原理に気付いた時に発した言葉とされる。昔『ユリイカ』という雑誌がありましたね~。ラテン語読みになるとユリイカですね。
これ面白いのかなあ。経済学の用語が多少出てきますけど、帯に書いてあるほど特徴にはなってない気がする。
それに普通の推理小説じゃないの?と言う気がします。可もなく不可もなく、歴史に残る傑作というのではないプロが書いた普通の推理小説。探偵にも主人公の玉木にもさほど人間的魅力はないし。こういう地味な小説読んでると、横溝文学とか、エラリー・クイーンとかが懐かしい。
こういう作品にあたると推理小説全般のことを考えてしまうのが私の性。
(このあとネタばれ。読んでない方は注意。)
この作品の場合、途中で登場する玉木の大学時代の友人岸本が本命ですね。誰が読んでもあからさまに怪しい人物。こういう場合こいつは、まず犯人じゃない。
では、だれが犯人かと言うと、あからさまに怪しい人物の対抗が誰になるのかをみればよい。対抗といえる人物はそれなりに書き込んでいなければなりません。悪人と言うのは魅力的なものですから、魅力が印象に残るような書き方をしてないといけない。それが犯人です。
この小説の場合は、構成から言って亜由美です。
登場人物が10人以内の小説の犯人は、それで大体犯人がわかります。たまに穴馬で物語の語り手役が「実は・・・」とか言って犯人だという掟破りがあります。アガサ・クリスティが「アクロイド殺し」でやりました。
そういう意味でも、「どんでん返し」もないし、普通の推理小説だよなあと思いました。
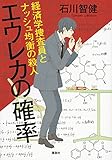
¥1,620
Amazon.co.jp
向山製薬に起きた「人体実験が行われている」と警告する怪文書の犯人を捜していたコンプライアンス課の玉木は、捜査対象の希少疾病第2部門で起きた課員の事故死に不信感を抱いて捜査にやってきた経済学捜査員という肩書の刑事の伏見に出会う。2人は、連れだって事件の捜査をすることになる・・・。
エウレカは、ギリシャ語のεὕρηκα(見つけたの意味)でアルキメデスがアルキメデスの原理に気付いた時に発した言葉とされる。昔『ユリイカ』という雑誌がありましたね~。ラテン語読みになるとユリイカですね。
これ面白いのかなあ。経済学の用語が多少出てきますけど、帯に書いてあるほど特徴にはなってない気がする。
それに普通の推理小説じゃないの?と言う気がします。可もなく不可もなく、歴史に残る傑作というのではないプロが書いた普通の推理小説。探偵にも主人公の玉木にもさほど人間的魅力はないし。こういう地味な小説読んでると、横溝文学とか、エラリー・クイーンとかが懐かしい。
こういう作品にあたると推理小説全般のことを考えてしまうのが私の性。
(このあとネタばれ。読んでない方は注意。)
この作品の場合、途中で登場する玉木の大学時代の友人岸本が本命ですね。誰が読んでもあからさまに怪しい人物。こういう場合こいつは、まず犯人じゃない。
では、だれが犯人かと言うと、あからさまに怪しい人物の対抗が誰になるのかをみればよい。対抗といえる人物はそれなりに書き込んでいなければなりません。悪人と言うのは魅力的なものですから、魅力が印象に残るような書き方をしてないといけない。それが犯人です。
この小説の場合は、構成から言って亜由美です。
登場人物が10人以内の小説の犯人は、それで大体犯人がわかります。たまに穴馬で物語の語り手役が「実は・・・」とか言って犯人だという掟破りがあります。アガサ・クリスティが「アクロイド殺し」でやりました。
そういう意味でも、「どんでん返し」もないし、普通の推理小説だよなあと思いました。
