蜘蛛の糸・杜子春 (新潮文庫)/芥川 龍之介
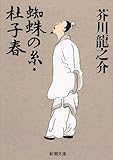
¥340
Amazon.co.jp
釈迦はある時、極楽の蓮池を通してはるか下の地獄を覗き見た。幾多の罪人どもが苦しみもがいていたが、その中にカンダタ(犍陀多)という男の姿を見つけた。カンダタは生前に様々な悪事を働いた泥棒であったが、一度だけ善行を成したことがあった。小さな蜘蛛を踏み殺そうとしたが思いとどまり、命を助けてやったのだ。それを思い出した釈迦は、地獄の底のカンダタを極楽へ導こうと、一本の蜘蛛の糸をカンダタめがけて下ろした。
極楽から下がる蜘蛛の糸を見たカンダタは「この糸をつたって登れば、地獄から脱出できるだろう。あわよくば極楽に行けるかもしれない」と考える。そこで蜘蛛の糸につかまって、地獄から何万里も離れた極楽目指して上へ上へと昇り始めた。ところが糸をつたって昇る途中、ふと下を見下ろすと、数限りない地獄の罪人達が自分の下から続いてくる。このままでは糸は重さに耐え切れず、切れてしまうだろう。それを恐れたカンダタは「この蜘蛛の糸は俺のものだ。お前達は一体誰に聞いて上ってきた。下りろ、下りろ」と喚いた。すると次の瞬間、蜘蛛の糸がカンダタのぶら下がっている所から切れ、カンダタは再び地獄に堕ちてしまった。
その一部始終を見ていた釈迦は、カンダタの自分だけ地獄から抜け出そうとする無慈悲な心と、相応の罰として地獄に逆落としになってしまった姿が浅ましく思われたのか、悲しそうな顔をして蓮池から立ち去った。
あまりに有名過ぎてあらすじ省略しようかと思いましたが、Wikiに適当なのがありましたのでコピペしました。
この『蜘蛛の糸』は、私が小学校5年か6年かのときの国語の教科書に載っていました。芥川は教科書に載せるのにほど良い長さの短編が多いので、高校の時も現国の教科書に『羅生門』と、ずい分学校で読まされてます。
この話を昔読んだ感想は、「お釈迦様って結構厳しいんだ~。」でした。でも、それ授業時間中には言えませんでしたけど。空気読むって大事ですもんね。
大学のころにドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読んだ時、「あら。」と思ったのは、この『蜘蛛の糸』にそっくりな話がサイド・ストーリーとして挿入されているのです。ねぎ女の話。「悪い事ばかりして死んだ女が煉獄に落ちた。彼女が生前、畑から出ていたねぎを畑にもどして根を土に埋めてやったのを神様が思い出し、天国からねぎを女に差し出してやった。女はねぎを上って行き、ふと下を振り返ると、後に罪人が続いている。彼女はカンダタ同様悪態をつくのですね。そして女の手の上でねぎがふっつりと切れる。」
長らく、芥川はこのドストエフスキーの小説から剽窃したんだと思っていました。なんか仏教的ではないような気がしますし。
今回Wikiを読むとイタリアやスペインに似た説話があるそうですし、日本の昔話にもよく似た筋があるそうです。しかし、話のまとまり具合からいっても「ねぎ女」の話は「蜘蛛の糸」にかなり酷似していました。
ともかくも明治の作家は外国語が堪能だったのは確かなようですね。
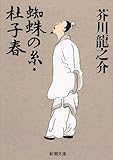
¥340
Amazon.co.jp
釈迦はある時、極楽の蓮池を通してはるか下の地獄を覗き見た。幾多の罪人どもが苦しみもがいていたが、その中にカンダタ(犍陀多)という男の姿を見つけた。カンダタは生前に様々な悪事を働いた泥棒であったが、一度だけ善行を成したことがあった。小さな蜘蛛を踏み殺そうとしたが思いとどまり、命を助けてやったのだ。それを思い出した釈迦は、地獄の底のカンダタを極楽へ導こうと、一本の蜘蛛の糸をカンダタめがけて下ろした。
極楽から下がる蜘蛛の糸を見たカンダタは「この糸をつたって登れば、地獄から脱出できるだろう。あわよくば極楽に行けるかもしれない」と考える。そこで蜘蛛の糸につかまって、地獄から何万里も離れた極楽目指して上へ上へと昇り始めた。ところが糸をつたって昇る途中、ふと下を見下ろすと、数限りない地獄の罪人達が自分の下から続いてくる。このままでは糸は重さに耐え切れず、切れてしまうだろう。それを恐れたカンダタは「この蜘蛛の糸は俺のものだ。お前達は一体誰に聞いて上ってきた。下りろ、下りろ」と喚いた。すると次の瞬間、蜘蛛の糸がカンダタのぶら下がっている所から切れ、カンダタは再び地獄に堕ちてしまった。
その一部始終を見ていた釈迦は、カンダタの自分だけ地獄から抜け出そうとする無慈悲な心と、相応の罰として地獄に逆落としになってしまった姿が浅ましく思われたのか、悲しそうな顔をして蓮池から立ち去った。
あまりに有名過ぎてあらすじ省略しようかと思いましたが、Wikiに適当なのがありましたのでコピペしました。
この『蜘蛛の糸』は、私が小学校5年か6年かのときの国語の教科書に載っていました。芥川は教科書に載せるのにほど良い長さの短編が多いので、高校の時も現国の教科書に『羅生門』と、ずい分学校で読まされてます。
この話を昔読んだ感想は、「お釈迦様って結構厳しいんだ~。」でした。でも、それ授業時間中には言えませんでしたけど。空気読むって大事ですもんね。
大学のころにドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読んだ時、「あら。」と思ったのは、この『蜘蛛の糸』にそっくりな話がサイド・ストーリーとして挿入されているのです。ねぎ女の話。「悪い事ばかりして死んだ女が煉獄に落ちた。彼女が生前、畑から出ていたねぎを畑にもどして根を土に埋めてやったのを神様が思い出し、天国からねぎを女に差し出してやった。女はねぎを上って行き、ふと下を振り返ると、後に罪人が続いている。彼女はカンダタ同様悪態をつくのですね。そして女の手の上でねぎがふっつりと切れる。」
長らく、芥川はこのドストエフスキーの小説から剽窃したんだと思っていました。なんか仏教的ではないような気がしますし。
今回Wikiを読むとイタリアやスペインに似た説話があるそうですし、日本の昔話にもよく似た筋があるそうです。しかし、話のまとまり具合からいっても「ねぎ女」の話は「蜘蛛の糸」にかなり酷似していました。
ともかくも明治の作家は外国語が堪能だったのは確かなようですね。
