ベルサイユのばら (1) (集英社文庫)/池田 理代子
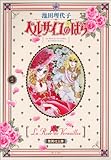
¥650
Amazon.co.jp
うわすごい表紙。少女マンガしてますね。1972年21号から1973年まで『週刊マーガレット』(集英社)に連載された。
フランス・ブルボン朝後期、ルイ15世末期からフランス革命でのアントワネット処刑までを描いている。前半はオスカルとアントワネットの2人を中心に描き、中盤以降はオスカルを主人公として、フランス革命に至る悲劇を描いた。
1755年12月25日、フランス王国の貴族であるジャルジェ家に1人の女児が生まれた。当主であるレニエ・ド・ジャルジェ将軍には5人の娘がいたが家督を相続すべき息子を持っておらず、その誕生を心待ちにしていた。しかし、生まれたのはまたもや女児であり、将軍は姉妹の中で一番美しく生まれた彼女に「オスカル・フランソワ」という男性名を付け、息子として育てて後継者にすることにした。オスカルは以後、男性として、また、軍人として厳しく育てられることとなる。
同年11月2日、後にフランス国王ルイ16世の王妃となるオーストリア皇女マリー・アントワネット・ジョセファ・ジャンヌ・ド・ロレーヌ・オートリッシュがオーストリア女帝マリア・テレジアとその夫神聖ローマ皇帝フランツ1世の11女としてウィーンに生まれる。アントワネットはウィーン・シェーンブルン宮殿において兄姉と共にのびのびとした子供時代を過ごした。
当時のオーストリア・ハプスブルク家は、伝統的な外交関係を転換してフランスとの同盟関係を深めようとしており、その一環として母マリア・テレジアは、アントワネットとフランス国王ルイ15世の孫ルイ・オーギュスト(のちのルイ16世)との政略結婚を画策していた。1770年5月16日、アントワネットと王太子ルイとの結婚式がヴェルサイユ宮殿にて挙行され、彼女はフランス王太子妃となった。このとき近衛連隊長付大尉となっていたオスカル・フランソワと出会う。オスカルの美貌と誠実さを好ましく思ったアントワネットは、以後オスカルを心を許した忠臣として寵愛する。
「東京教育大学文学部哲学科に入学。学者を志し勉強していたが、1年で父親からの金銭的援助が打ち切られてしまうために生活の糧として漫画を描き始める。」という経歴からもわかるように、これまでの少女漫画家にはない教養や歴史観みたいなものを備えた初めての少女漫画家だったのではないかと思います。
たしか愛読書はマルクスの『共産党宣言』だそうで、「べるばら」も主人公たちが貴族や王族なのに、物語は革命側の視点から描かれています。
この作者の嗜好の特徴としてあげられるのがオスカルに代表される「男装の麗人」。この次の長編『オルフェウスの窓』も主人公が男装して男子校にいる女性でした。
人の嗜好は理解を超えたものですが、竹宮恵子さんの「少年愛」のようには漫画の亜流は生まれませんでした。すでに既存の"宝塚歌劇"があったからなのか・・・。べるばらブームというものは宝塚での舞台化以降が本格的だったような気がします。
また、この漫画の主人公のマリー・アントワネットの描き方については、多少実像とかけはなれたものがあったのではないかという気がします。なんか悲劇の王妃という本人も深刻にフェルゼンへの愛に悩むみたいな女性像でした。
だが、実際にはあまり政治とか国家とか統治とはなんてことには興味のない趣味の良いお洒落な女学生的なイメージだったのではないかと思います。浮気にしたって少々は18世紀の貴族社会ではあたりまえだったのではないでしょうか。
そういうイメージで捉えた映画。
マリー・アントワネット (通常版) [DVD]/キルスティン・ダンスト,ジェイソン・シュワルツマン,アーシア・アルジェント
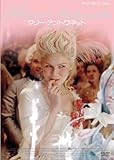
¥3,990
Amazon.co.jp
このソフィア・コッポラ監督の映画は思いのほか面白いですし、ベルサイユ宮殿で実際にロケをしたそうで映像もきれいです。またこのマリー・アントワネットの人物像はかなり本物にちかいのではないかと思います。
_____________________________________________
もう一度池田さんのことに戻りますが、池田理代子さんの功績という点で考えるなら、少女漫画の読者の年齢層を引き上げたことではないでしょうか。
数年前、女性週刊誌に『ベルサイユのばら』が連載の形で再掲載されたことがあった。美容院でなにげなく読んでいてその面白いのに感心したのを覚えています。私の好きなタイプの漫画でない事は明らかなのですが、傑作であることは疑いありません。
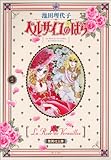
¥650
Amazon.co.jp
うわすごい表紙。少女マンガしてますね。1972年21号から1973年まで『週刊マーガレット』(集英社)に連載された。
フランス・ブルボン朝後期、ルイ15世末期からフランス革命でのアントワネット処刑までを描いている。前半はオスカルとアントワネットの2人を中心に描き、中盤以降はオスカルを主人公として、フランス革命に至る悲劇を描いた。
1755年12月25日、フランス王国の貴族であるジャルジェ家に1人の女児が生まれた。当主であるレニエ・ド・ジャルジェ将軍には5人の娘がいたが家督を相続すべき息子を持っておらず、その誕生を心待ちにしていた。しかし、生まれたのはまたもや女児であり、将軍は姉妹の中で一番美しく生まれた彼女に「オスカル・フランソワ」という男性名を付け、息子として育てて後継者にすることにした。オスカルは以後、男性として、また、軍人として厳しく育てられることとなる。
同年11月2日、後にフランス国王ルイ16世の王妃となるオーストリア皇女マリー・アントワネット・ジョセファ・ジャンヌ・ド・ロレーヌ・オートリッシュがオーストリア女帝マリア・テレジアとその夫神聖ローマ皇帝フランツ1世の11女としてウィーンに生まれる。アントワネットはウィーン・シェーンブルン宮殿において兄姉と共にのびのびとした子供時代を過ごした。
当時のオーストリア・ハプスブルク家は、伝統的な外交関係を転換してフランスとの同盟関係を深めようとしており、その一環として母マリア・テレジアは、アントワネットとフランス国王ルイ15世の孫ルイ・オーギュスト(のちのルイ16世)との政略結婚を画策していた。1770年5月16日、アントワネットと王太子ルイとの結婚式がヴェルサイユ宮殿にて挙行され、彼女はフランス王太子妃となった。このとき近衛連隊長付大尉となっていたオスカル・フランソワと出会う。オスカルの美貌と誠実さを好ましく思ったアントワネットは、以後オスカルを心を許した忠臣として寵愛する。
「東京教育大学文学部哲学科に入学。学者を志し勉強していたが、1年で父親からの金銭的援助が打ち切られてしまうために生活の糧として漫画を描き始める。」という経歴からもわかるように、これまでの少女漫画家にはない教養や歴史観みたいなものを備えた初めての少女漫画家だったのではないかと思います。
たしか愛読書はマルクスの『共産党宣言』だそうで、「べるばら」も主人公たちが貴族や王族なのに、物語は革命側の視点から描かれています。
この作者の嗜好の特徴としてあげられるのがオスカルに代表される「男装の麗人」。この次の長編『オルフェウスの窓』も主人公が男装して男子校にいる女性でした。
人の嗜好は理解を超えたものですが、竹宮恵子さんの「少年愛」のようには漫画の亜流は生まれませんでした。すでに既存の"宝塚歌劇"があったからなのか・・・。べるばらブームというものは宝塚での舞台化以降が本格的だったような気がします。
また、この漫画の主人公のマリー・アントワネットの描き方については、多少実像とかけはなれたものがあったのではないかという気がします。なんか悲劇の王妃という本人も深刻にフェルゼンへの愛に悩むみたいな女性像でした。
だが、実際にはあまり政治とか国家とか統治とはなんてことには興味のない趣味の良いお洒落な女学生的なイメージだったのではないかと思います。浮気にしたって少々は18世紀の貴族社会ではあたりまえだったのではないでしょうか。
そういうイメージで捉えた映画。
マリー・アントワネット (通常版) [DVD]/キルスティン・ダンスト,ジェイソン・シュワルツマン,アーシア・アルジェント
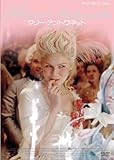
¥3,990
Amazon.co.jp
このソフィア・コッポラ監督の映画は思いのほか面白いですし、ベルサイユ宮殿で実際にロケをしたそうで映像もきれいです。またこのマリー・アントワネットの人物像はかなり本物にちかいのではないかと思います。
_____________________________________________
もう一度池田さんのことに戻りますが、池田理代子さんの功績という点で考えるなら、少女漫画の読者の年齢層を引き上げたことではないでしょうか。
数年前、女性週刊誌に『ベルサイユのばら』が連載の形で再掲載されたことがあった。美容院でなにげなく読んでいてその面白いのに感心したのを覚えています。私の好きなタイプの漫画でない事は明らかなのですが、傑作であることは疑いありません。
