竹宮恵子の漫画は水準が高い。これを最初に言っとかないと、この後決してほめ言葉が出て来そうになくてなんでわざわざブログ書いてるんだという話になるので、最初に書いときます。
萩尾望都と同い年でほぼ同時期から現在にいたるまで同様に活躍をつづけられています。
この人にについて何かを言うとき、「少年愛」を少女漫画に紹介したということを抜きには語れないと思うのです。
現在、"やおいもの"として本屋の一角を平積みで埋める漫画群がありますが、これらの大元になったのがこの人の作品です。私がまだ小学生時分には少年が主人公の少女漫画などというものは存在しておりませんでした。少女マンガの題材と言えば、継子いじめだったり、バレエだったりという一定の年齢に達した女性は卒業するものという前提がありました。池田理代子さんが出てきたあたりから変わってきましたが。
竹宮恵子が少年を主人公にして、かつその少年の恋愛の相手役がまた少年という少女漫画を世に出した最初の人なのだと思います。例外的には、『ファイヤー』(水野英子作)などありましたが、これは発表がセブンティーンだったと思います。
特に有名な『風と木の詩』に関して言えば、少女コミックで連載が始まった時、巻頭カラーで「構想○○年」みたいな字が踊っていて、こういうものを日の当る所に出すぞという雑誌の決断と意気込みに驚いたのを覚えています。
『風と木の詩』の関して言えば、その時購読していた少女コミックも他の漫画家の連載が終わった時点で購読を止めてしまったので、結末がどうなったのか思い出せないぐらいなんですけど、これって少年愛どころか児童虐待の話じゃないのかと思ってたぐらいで、わたしはつくづく"腐女子"の才能がないなと思います。この人の作品でちゃんと雑誌で読んでいたのは『ファラオの墓』ぐらいだなと思います。
少年愛は少女たちの「男になりたい。でも男に愛されたい。」という願望を具現化したものだというまことしやかな説を聞いたことがありますが、現在のように読者の年齢が上がり多分に現実生活(結婚もし、子供もいるような女性が読んでいると聞く。)が安定している人たちにおいてもそうなのかと考えると、自分の女性性をどこかで否定的に考えている人たちに受けるのかなと、私は感じております。また、そういう人たちの癒しになるところがあるようです。
たしかに日本の社会では女性はつまらない。学校卒業して会社に入っても出世はできないとか、結婚、出産、育児で家庭に縛りつけられるみたいな感じは誰もが時代をさかのぼるほど、持っていたのかもしれません。
ただ、現在ではどうなのか。これこそ、社会状況が変わってもジャンルが生き残るの例ではないでしょうか。その世界が出来てしまったので、その世界の心地よさに酔いしれて依存症状態にはまった人たちが読者になっていて、この人たちは忠実なのでそこそこの市場性が確保されているみたいな。"韓流","ハードボイルド"他にも私が知らないだけでそういう「ジャンル」はたくさんあるのでしょうね。大体こういう「ジャンル」が出来るきっかけが水準の高い傑作群なのですが、それで一大ブームが起こり真似する人がたくさん出てきて亜流が大量にでき市場を確保し、「ジャンル」になるという構図でしょうか。
「少年愛」漫画の水準の高い傑作群を描いた人が、竹宮恵子、萩尾望都あたりになるのでしょうね。
漫画を紹介するときは表紙の絵をなにか貼りたいのでどれか作品を選ぶということになるのですが、ま、芸術家が主人公ならそんな世界が描かれても当然かということで『変奏曲』。まだこの時代は上品です。
変奏曲 vol.1 (1)/竹宮 惠子; 増山 法恵
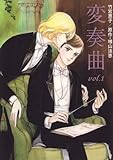
¥1,260
Amazon.co.jp
Wikiで腐女子を見てみたけど、知らない言葉がいっぱいで、現象としての捉え方しかしてなくて中身を全然知らないので当然ですが、とても私ではついていけません。
社会学者の宮台真司が"オタク"の定義を「二次元で抜けることだ。」と言っていたのですが、じゃあ女性のオタクの定義は?ということで、ことほど左様に人口の半分を占めている女性がまるでいない物と扱われるこの状況をみると「女ってつまらない。」と感じる人が多くてもしょうがないかなと感じます。
私は,"オタク"の定義など出来ませんが、その要素として社会からの疎外感があるとすれば女性は全て"オタク"の予備軍。"腐女子"は、立派な"オタク"でしょうね。
萩尾望都と同い年でほぼ同時期から現在にいたるまで同様に活躍をつづけられています。
この人にについて何かを言うとき、「少年愛」を少女漫画に紹介したということを抜きには語れないと思うのです。
現在、"やおいもの"として本屋の一角を平積みで埋める漫画群がありますが、これらの大元になったのがこの人の作品です。私がまだ小学生時分には少年が主人公の少女漫画などというものは存在しておりませんでした。少女マンガの題材と言えば、継子いじめだったり、バレエだったりという一定の年齢に達した女性は卒業するものという前提がありました。池田理代子さんが出てきたあたりから変わってきましたが。
竹宮恵子が少年を主人公にして、かつその少年の恋愛の相手役がまた少年という少女漫画を世に出した最初の人なのだと思います。例外的には、『ファイヤー』(水野英子作)などありましたが、これは発表がセブンティーンだったと思います。
特に有名な『風と木の詩』に関して言えば、少女コミックで連載が始まった時、巻頭カラーで「構想○○年」みたいな字が踊っていて、こういうものを日の当る所に出すぞという雑誌の決断と意気込みに驚いたのを覚えています。
『風と木の詩』の関して言えば、その時購読していた少女コミックも他の漫画家の連載が終わった時点で購読を止めてしまったので、結末がどうなったのか思い出せないぐらいなんですけど、これって少年愛どころか児童虐待の話じゃないのかと思ってたぐらいで、わたしはつくづく"腐女子"の才能がないなと思います。この人の作品でちゃんと雑誌で読んでいたのは『ファラオの墓』ぐらいだなと思います。
少年愛は少女たちの「男になりたい。でも男に愛されたい。」という願望を具現化したものだというまことしやかな説を聞いたことがありますが、現在のように読者の年齢が上がり多分に現実生活(結婚もし、子供もいるような女性が読んでいると聞く。)が安定している人たちにおいてもそうなのかと考えると、自分の女性性をどこかで否定的に考えている人たちに受けるのかなと、私は感じております。また、そういう人たちの癒しになるところがあるようです。
たしかに日本の社会では女性はつまらない。学校卒業して会社に入っても出世はできないとか、結婚、出産、育児で家庭に縛りつけられるみたいな感じは誰もが時代をさかのぼるほど、持っていたのかもしれません。
ただ、現在ではどうなのか。これこそ、社会状況が変わってもジャンルが生き残るの例ではないでしょうか。その世界が出来てしまったので、その世界の心地よさに酔いしれて依存症状態にはまった人たちが読者になっていて、この人たちは忠実なのでそこそこの市場性が確保されているみたいな。"韓流","ハードボイルド"他にも私が知らないだけでそういう「ジャンル」はたくさんあるのでしょうね。大体こういう「ジャンル」が出来るきっかけが水準の高い傑作群なのですが、それで一大ブームが起こり真似する人がたくさん出てきて亜流が大量にでき市場を確保し、「ジャンル」になるという構図でしょうか。
「少年愛」漫画の水準の高い傑作群を描いた人が、竹宮恵子、萩尾望都あたりになるのでしょうね。
漫画を紹介するときは表紙の絵をなにか貼りたいのでどれか作品を選ぶということになるのですが、ま、芸術家が主人公ならそんな世界が描かれても当然かということで『変奏曲』。まだこの時代は上品です。
変奏曲 vol.1 (1)/竹宮 惠子; 増山 法恵
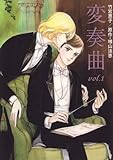
¥1,260
Amazon.co.jp
Wikiで腐女子を見てみたけど、知らない言葉がいっぱいで、現象としての捉え方しかしてなくて中身を全然知らないので当然ですが、とても私ではついていけません。
社会学者の宮台真司が"オタク"の定義を「二次元で抜けることだ。」と言っていたのですが、じゃあ女性のオタクの定義は?ということで、ことほど左様に人口の半分を占めている女性がまるでいない物と扱われるこの状況をみると「女ってつまらない。」と感じる人が多くてもしょうがないかなと感じます。
私は,"オタク"の定義など出来ませんが、その要素として社会からの疎外感があるとすれば女性は全て"オタク"の予備軍。"腐女子"は、立派な"オタク"でしょうね。
