スカイ・クロラ [DVD]
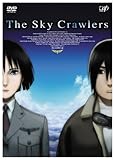
¥2,600
Amazon.co.jp
森博嗣の小説『スカイ・クロラ』を読んでないしこの後読む気もないので、先入観を持たずに観ました。
私は好きです。でもこの映画にお客が入ったら不思議ですよね。
最初「また草薙さんなの?」と思ったんですが、偶然原作の登場人物が「草薙」さんだったようです。素子さんじゃなくてちょっと安心しました。
パイロットたちは、成長しないクローンのようなものらしい。「函南」のあとに来る人も前にいた人もどうも「函南」と同じ顔、声、姿をしていたらしいと仄めかされている。
また、「草薙」の娘の父親は"ティーチャー"と言っているように聞こえる。
戦闘機の空中戦闘シーンは非常に美しい凝った作りで、これがやりたかったんじゃないのと思います。
ラスト近く、次のセリフに全てが現わされている。
「いつも通る道でも
違う所を踏んで歩くことができる。
いつも通る道だからって
景色は同じじゃない。
それだけではいけないのか。
それだけのことだから・・・・いけないのか。」
「"ティーチャー"を撃墜する」という字幕がでるが、音声では"I kill my father."と聞こえる。
"親殺し"はルールの破壊を意味し、親を殺した人間は大人になる。
子供のままで生きていくことは出来る。しかし、変わろうとすること大人になろうとすることは「死」を意味する。
と、私には読めるのですけど・・・。
--------------------------------------------------
押井語録:
「若い人に、生きることの意味を伝えたい」
・・・・?。
「この映画は生まれ変わったつもりで作りました。この作品が成功しなかったら、今度こそ辞めます。」
「ダメだったら辞めようと、ダメだったら元の自分に戻って、相変わらずペダントリーとうんちくと、シニカルに偏った戦争映画しか作らない監督になろうとか、意固地に考えてもいます(笑)。」
・・・?・・・?・・・?。
この映画を観て若い人が理解すべき「生きることの意味」とは?
特に、監督は・・・生まれ変わっていないと感じるけど・・・どうでしょうか。
この人のテーマって、変わらぬ日常の退屈と鬱屈の破壊だと私は思います。「相変わらず」。
でもその「ペダントリーとうんちくと、シニカルに偏った」ところが好きなんですけど。
--------------------------------------------------
全ての戦争は戦争請負会社が請け負う空中戦のみになり、才能あるキルドレだけが兵士となる世界。永遠の命をもった存在が生きる実感を得るために常に死を意識しなければならない戦争に参加する。普通の人間を戦争の犠牲にすることはもはやできないが、戦争のない世の中はありえないという世界観らしい。単に作者の趣味的な戦争好きから作りだされたものなのかもしれない・・・が。
「本作はヴェネチア国際映画祭で反響があり多くの海内メディアから取材を受けたが、主な質問は物語そのものではなく、「現実に少年少女が兵士として徴用され、命を散らしているのに、「生を実感するため」などという空虚な理由のために戦うなどという作品は、フィクションであるとしてもどうか」など世界観についてであった。」(出典wiki)
世界はまだまだ日本の「平和ボケ」に追いつけないのですよ。
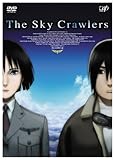
¥2,600
Amazon.co.jp
森博嗣の小説『スカイ・クロラ』を読んでないしこの後読む気もないので、先入観を持たずに観ました。
私は好きです。でもこの映画にお客が入ったら不思議ですよね。
最初「また草薙さんなの?」と思ったんですが、偶然原作の登場人物が「草薙」さんだったようです。素子さんじゃなくてちょっと安心しました。
パイロットたちは、成長しないクローンのようなものらしい。「函南」のあとに来る人も前にいた人もどうも「函南」と同じ顔、声、姿をしていたらしいと仄めかされている。
また、「草薙」の娘の父親は"ティーチャー"と言っているように聞こえる。
戦闘機の空中戦闘シーンは非常に美しい凝った作りで、これがやりたかったんじゃないのと思います。
ラスト近く、次のセリフに全てが現わされている。
「いつも通る道でも
違う所を踏んで歩くことができる。
いつも通る道だからって
景色は同じじゃない。
それだけではいけないのか。
それだけのことだから・・・・いけないのか。」
「"ティーチャー"を撃墜する」という字幕がでるが、音声では"I kill my father."と聞こえる。
"親殺し"はルールの破壊を意味し、親を殺した人間は大人になる。
子供のままで生きていくことは出来る。しかし、変わろうとすること大人になろうとすることは「死」を意味する。
と、私には読めるのですけど・・・。
--------------------------------------------------
押井語録:
「若い人に、生きることの意味を伝えたい」
・・・・?。
「この映画は生まれ変わったつもりで作りました。この作品が成功しなかったら、今度こそ辞めます。」
「ダメだったら辞めようと、ダメだったら元の自分に戻って、相変わらずペダントリーとうんちくと、シニカルに偏った戦争映画しか作らない監督になろうとか、意固地に考えてもいます(笑)。」
・・・?・・・?・・・?。
この映画を観て若い人が理解すべき「生きることの意味」とは?
特に、監督は・・・生まれ変わっていないと感じるけど・・・どうでしょうか。
この人のテーマって、変わらぬ日常の退屈と鬱屈の破壊だと私は思います。「相変わらず」。
でもその「ペダントリーとうんちくと、シニカルに偏った」ところが好きなんですけど。
--------------------------------------------------
全ての戦争は戦争請負会社が請け負う空中戦のみになり、才能あるキルドレだけが兵士となる世界。永遠の命をもった存在が生きる実感を得るために常に死を意識しなければならない戦争に参加する。普通の人間を戦争の犠牲にすることはもはやできないが、戦争のない世の中はありえないという世界観らしい。単に作者の趣味的な戦争好きから作りだされたものなのかもしれない・・・が。
「本作はヴェネチア国際映画祭で反響があり多くの海内メディアから取材を受けたが、主な質問は物語そのものではなく、「現実に少年少女が兵士として徴用され、命を散らしているのに、「生を実感するため」などという空虚な理由のために戦うなどという作品は、フィクションであるとしてもどうか」など世界観についてであった。」(出典wiki)
世界はまだまだ日本の「平和ボケ」に追いつけないのですよ。
