サイボーグ009 (第1巻) (Sunday comics―大長編SFコミックス)/石ノ森 章太郎
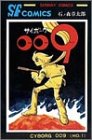
¥490
Amazon.co.jp
わたしがこれまでに読んだ中で最高にクール(かっこいい)な漫画だと考えている。
まず主人公がサイボーグという人間を改造した存在であるということ:
サイボーグは、Cybanetic Organismの略称なのだが、この漫画の発表の1964年当時の日本で一般的な名称ではありえず、この漫画によってサイボーグという名称が広まったと言われている。
サイボーグは、"人間のボディを改造した"存在であるわけで、感情の問題を考える必要がない。彼らは、所与の条件として感情の問題をクリアしているわけだ。これはロボットが感情をもてるのかどうかという電子頭脳の発達によるくだらない(かつ現実には不可能)オカルト話と無縁でいられる。リアリティに無理がないわけだ。
超人的な能力を持ちながら自然な感情を持ち人間としての悩みを抱える魅力あふれるキャラクターを生み出したのだ。
このような「自分たちは人間なのだろうか。自分とはなんだろうか。」という悩みは最近「サイボーグ哲学」と呼ばれているようだ。人間の体の一部を医療の一環として人造のものに置き換えたときに現実の人間に発生する悩みで、漫画の登場人物たちと同じものだ。この漫画はすぐれて未来を予測していたのだ。
悪役の設定:
00ナンバーサイボーグ達が戦うブラックゴーストの正体は、武器商人の国際秘密カルテルというものなのだが、東西冷戦どころかベトナム戦争まっさかりのときにこういう設定をしていた普遍性に感心する。
東西冷戦が終わったとたんに多くのジェームス・ボンドもどきのスパイ小説が陳腐化してしまったのにそういう影響を受けることもなかった。
9.11以降のアメリカのブッシュ大統領の背後に国際武器商人のカルテルがいると言ったら現実的な話をしているように聞こえないだろうか。
戦争というものの本質を捉えた設定なのだと思う。
コマの運び:
1964年頃の漫画のコマといえばまだまだ、3段で8コマぐらいの分け方が一般的で、コマに番号が振られることがなくなった程度がふつうだったようなのだ。なのに、石森章太郎の漫画だけは、縦にぶち抜きとか、見開き2頁横ぶち抜きとか、もうやりたい放題。いま、単行本を読み返してみてもコマの運び方が非常に垢ぬけている。またコマのなかの空間の取り方が特徴的でものの大きさを表すために大きな空間をとるような絵の配置がおこなわれている。
全体的に「音楽的」という言葉を思い出す。石森がモーツァルト型の天才であると言われる所以だと思う。
アカデミズムに陥っていない:
石森章太郎は大学に行くための資金を稼ぐために漫画を描いていたと言われているが、実際には大金を稼いだあとも大学に入学しなかった。これは結果的に良かったと私は思う。作品後期の『天使編』などに現れる「神」とは何かというテーマで、大学で宗教学の講義を聞いて、神のアカデミックな定義など開陳されても、漫画が面白いわけがない。
この作品のなかで石森は途中で一度執筆を中断し、再開した後もセリフのない世界の風景を描くことによってページを埋めていっている。これが何を表していいるのか私には言うことができない。
ただ言えることは現在作品となって残っている石森の『サイボーグ009』は彼の頭で考えたものだということなのだ。これは漫画というサブカルチャーの表現形式において最もふさわしい事ではないだろうか。
私が最初に従姉の家で『サイボーグ009』に接したのはわずか4歳という年齢で、字もひらがなカタカナ以外読めなかった筈なのに、「なんて面白い漫画なんだろう」と思ったことをいまも鮮明に覚えている。そしてその理解においても今と特に変わらないような気がするのだ。もちろんその面白さを言葉に書いて説明するような事は出来なかったけれど。
子供の理解力というものを馬鹿にしてはいけないし、子供に何を与えるかという問題のむつかしさを暗示していると思う。
私にとって、『サイボーグ009』は人生の最初に出会った最高にクールな作品だった。その後たくさんの漫画を読んで素晴らしい作品にも多く出会ったのだけれど、これを凌ぐクールさにはいまだに出遇っていない。
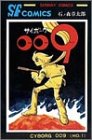
¥490
Amazon.co.jp
わたしがこれまでに読んだ中で最高にクール(かっこいい)な漫画だと考えている。
まず主人公がサイボーグという人間を改造した存在であるということ:
サイボーグは、Cybanetic Organismの略称なのだが、この漫画の発表の1964年当時の日本で一般的な名称ではありえず、この漫画によってサイボーグという名称が広まったと言われている。
サイボーグは、"人間のボディを改造した"存在であるわけで、感情の問題を考える必要がない。彼らは、所与の条件として感情の問題をクリアしているわけだ。これはロボットが感情をもてるのかどうかという電子頭脳の発達によるくだらない(かつ現実には不可能)オカルト話と無縁でいられる。リアリティに無理がないわけだ。
超人的な能力を持ちながら自然な感情を持ち人間としての悩みを抱える魅力あふれるキャラクターを生み出したのだ。
このような「自分たちは人間なのだろうか。自分とはなんだろうか。」という悩みは最近「サイボーグ哲学」と呼ばれているようだ。人間の体の一部を医療の一環として人造のものに置き換えたときに現実の人間に発生する悩みで、漫画の登場人物たちと同じものだ。この漫画はすぐれて未来を予測していたのだ。
悪役の設定:
00ナンバーサイボーグ達が戦うブラックゴーストの正体は、武器商人の国際秘密カルテルというものなのだが、東西冷戦どころかベトナム戦争まっさかりのときにこういう設定をしていた普遍性に感心する。
東西冷戦が終わったとたんに多くのジェームス・ボンドもどきのスパイ小説が陳腐化してしまったのにそういう影響を受けることもなかった。
9.11以降のアメリカのブッシュ大統領の背後に国際武器商人のカルテルがいると言ったら現実的な話をしているように聞こえないだろうか。
戦争というものの本質を捉えた設定なのだと思う。
コマの運び:
1964年頃の漫画のコマといえばまだまだ、3段で8コマぐらいの分け方が一般的で、コマに番号が振られることがなくなった程度がふつうだったようなのだ。なのに、石森章太郎の漫画だけは、縦にぶち抜きとか、見開き2頁横ぶち抜きとか、もうやりたい放題。いま、単行本を読み返してみてもコマの運び方が非常に垢ぬけている。またコマのなかの空間の取り方が特徴的でものの大きさを表すために大きな空間をとるような絵の配置がおこなわれている。
全体的に「音楽的」という言葉を思い出す。石森がモーツァルト型の天才であると言われる所以だと思う。
アカデミズムに陥っていない:
石森章太郎は大学に行くための資金を稼ぐために漫画を描いていたと言われているが、実際には大金を稼いだあとも大学に入学しなかった。これは結果的に良かったと私は思う。作品後期の『天使編』などに現れる「神」とは何かというテーマで、大学で宗教学の講義を聞いて、神のアカデミックな定義など開陳されても、漫画が面白いわけがない。
この作品のなかで石森は途中で一度執筆を中断し、再開した後もセリフのない世界の風景を描くことによってページを埋めていっている。これが何を表していいるのか私には言うことができない。
ただ言えることは現在作品となって残っている石森の『サイボーグ009』は彼の頭で考えたものだということなのだ。これは漫画というサブカルチャーの表現形式において最もふさわしい事ではないだろうか。
私が最初に従姉の家で『サイボーグ009』に接したのはわずか4歳という年齢で、字もひらがなカタカナ以外読めなかった筈なのに、「なんて面白い漫画なんだろう」と思ったことをいまも鮮明に覚えている。そしてその理解においても今と特に変わらないような気がするのだ。もちろんその面白さを言葉に書いて説明するような事は出来なかったけれど。
子供の理解力というものを馬鹿にしてはいけないし、子供に何を与えるかという問題のむつかしさを暗示していると思う。
私にとって、『サイボーグ009』は人生の最初に出会った最高にクールな作品だった。その後たくさんの漫画を読んで素晴らしい作品にも多く出会ったのだけれど、これを凌ぐクールさにはいまだに出遇っていない。
