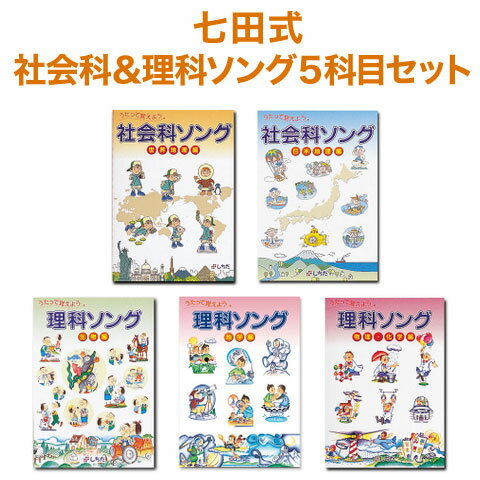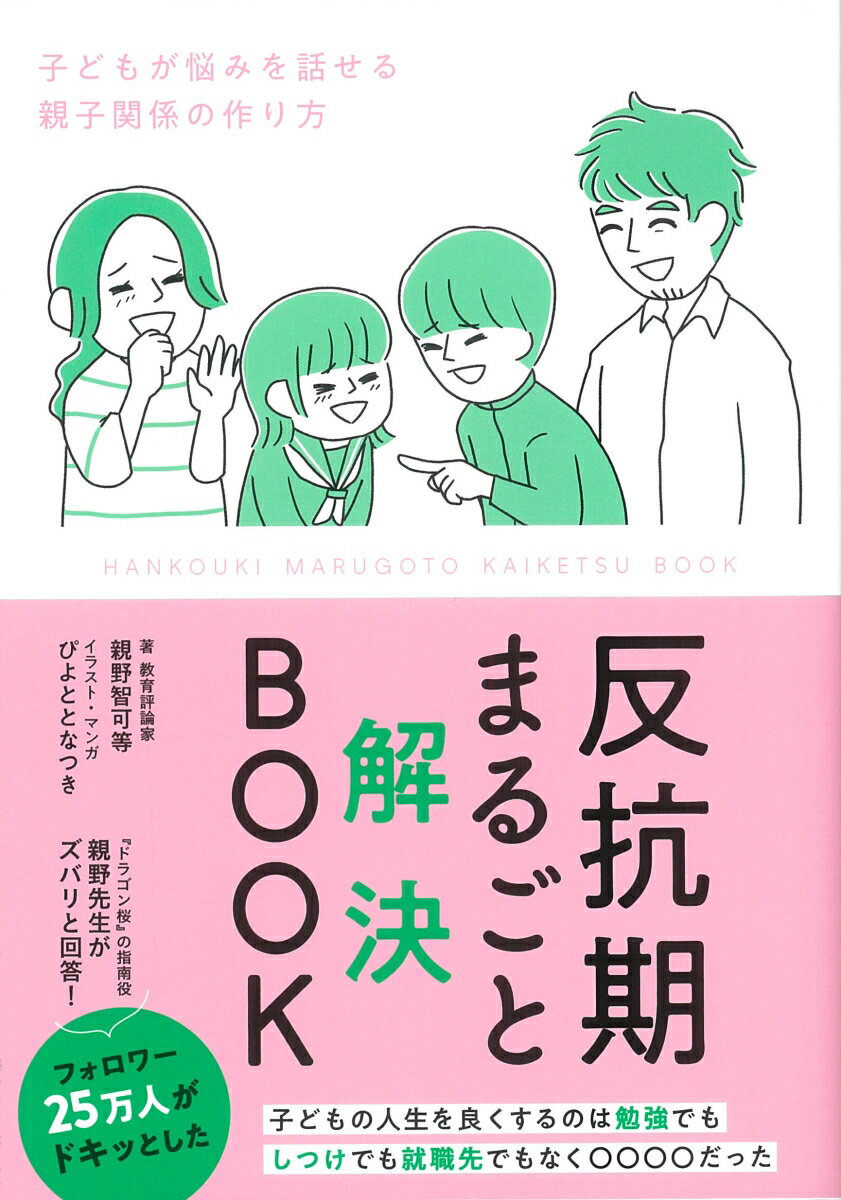2023年に我が家の三兄弟の長男が中学受験をしました。
年長さんの時に田中ビネー知能検査VでIQ136、2年生の時にWISC-Ⅳで同じくIQ136の高IQ児。
無対策で受けたSAPIX入室テストで
超絶ギリギリ合格、新4年生最下位アルファベットクラスからのスタート。
親として伴走した当時の記憶を呼び起こしつつ、中学受験の体験を書いています。
(一部、仮称などを用いています)
私自身、皆様のブログ情報でとても助けられました。
ですので、今度はどなたかのお役に立てればとの思いで、学校説明会に参加した際の内容や、受験お役立ち情報なども織り交ぜていければと思います。
立体切断の攻略の為にSAPIXの先生からオススメされた教材。
高いなのと思いましたが沢山使えたので買って正解でした。
理社の基本的な暗記物は低学年から始めよう。
歌を聞いて覚える教材。
低学年から使える、空間認知の教材
立体切断が苦手なお子さんに。

どうもこんにちは。
我が家の長男が通う学校は
ゴリッゴリの男子校。
学校がどんな様子なのかについては
何度か記事にしております通り。
先生方は
思春期のややこしい時期の男子たちを教育するプロなので
こちらとしても安心してお任せしております。
入学して1年が過ぎ
慣れてきたせいなのか
徐々にやらかす子も出てきたようで。
保護者会などでは
それについてのお話が毎回必ずあります。
具体的には
スマホの使い方、
SNSとの付き合い方、
ゲームの扱い方
というお話が多いかと思うのですが
これも時代の流れなのでしょう。
スマホやSNSって
ハマる子はハマる。
どハマりして
中毒みたいになってしまうことがあるんですよね。
睡眠を削ってゲームしちゃったり
そのせいで授業中に眠くなってしまったり
生活リズムなんて簡単に崩れてしまう。
だから長男の学校では
スマホやタブレットについては
それぞれの家庭でルールを決めて
例えば一日何時間まで、とか
使えるのは何時から何時まで、とか
それを書面にまとめて
提出することになっている。
そして学校としても
学校の最寄り駅でスマホの電源を切ること
学校に着いたらまとめて預けること
帰りは最寄り駅に着いたら電源を入れても良い
などの細かいルールを決めています。
なかなか良い方法だな、と思うんです。
でも。
ここまで対策していても
男子って、やらかすんですよね。
だって男子だから。
電源切ってなくて、預けるのも忘れちゃった、とか
意図的に預けなかった、とか。
それで授業中にLINEの着信音が鳴ってしまう、とかね。
そういう時、
先生の反応ってどんなんだろう??
ちょっと気になるところではあるのですけれども
ブチギレる
という先生は皆無なのだそうです。
うっかり預け忘れて授業中に着信音が鳴ってしまった子は
マズイ叱られる、と思って顔面蒼白。
でも先生は
着信音の真似をして
「ピンポーン」
と言ってクラスの笑いを誘い
スッ……とスマホを預かって
授業の終わりに
「◯◯くんは私に素敵な話があるようだから後で控室に来なさいね〜」
といった具合……。
ルールをうっかり破ってしまった、
例えば宿題忘れた、みたいな
些細なことであっても
私が子供の頃(いにしえの頃)なんて
体罰は当たり前、
水の入ったバケツ持たせて廊下に立たせるとか
1時間正座させるとか
フツーにあったんですよ。
私の兄が小学生の頃は
ビンタする先生も居たと。
でも時代は変わった。
今それやっちゃうと
大変なことになるのでね。
教育現場からは体罰は消えました。
とは言え
男子って、ちょちょっと言ったくらいでは
そう簡単に言うこと聞かないし
反抗期ともなるとなおさら。
そこに、スマホだなんだの中毒性のあるものが加わると
彼ら、ルールなんて簡単に破っちゃうんですよね…。
だから
男子を育てるプロである先生方は
どうやって言うことを聞けるようにしているのか。
ガミガミ叱って
カミナリ落としまくり。
……ではありません。
反抗的にならないように
でもルールはきちんと守れるように
時には笑いも交えながら
上手〜〜く誘導するんですよね…。
この辺りのさじ加減が
本当に絶妙で。
さすがはプロ。
結局、先生方は分かってらっしゃるんですよね。
力で押さえつけたところで
彼らは言うことを聞かない、
ということを。
それどころか
今度はバレないように
隠れてコソコソとやり始めてしまう。
そうすると
ますます厄介なことになるかもしれない。
なので
その子その子のキャラクターや反応を見ながら
その子に合わせた叱り方、注意の仕方をするんですな。
「叱る」って
本当に難しいんですよね。
「怒る」は怒りの感情を相手にぶつけること。
でも「叱る」は自分の感情を入れない。
私なんてついつい
「叱る」と「怒る」を混同しがちなもので
だから長男は反抗的になってしまうのですけれども。
男子を育てるプロは
そのあたりもやはりプロなんですよね。
親に言われても素直に聞けないようなことも
先生に言われれば素直に聞ける。
「親だから」という甘えもあるのでしょうけれど
やはり、プロはプロならではの
絶妙な操縦の方法がある。
反抗期の男子に
言うことをきかせる、って
並大抵ではない。
長男を育てて、反抗期を経験して
初めてそれを知りました。
上手に叱るスキル、
我が家でも学ばないといけませんね……。
それではまた。