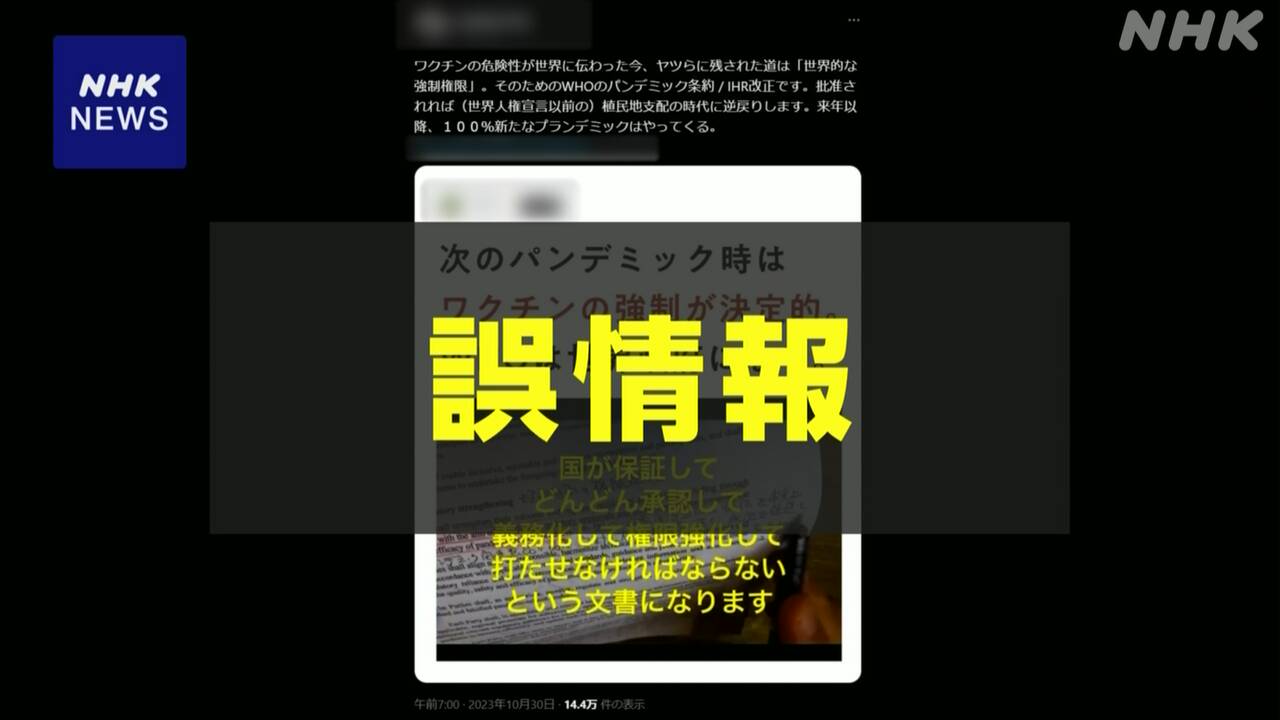前回の記事で出てきた詫摩佳代氏ですが、経歴調べると、ん?なんかおかしいとなったので記事にします。
少々マニアックな内容となりますので、あまり知る必要もないかもしれませんが、物好きな暇人の検索の成果をご覧あれ。
詫摩佳代(たくま かよ、1981年- )は、国際政治学者、東京都立大学法学部教授。専門は国際政治学、国際機構論。
広島県呉市生まれ、京都府京都市出身[1][2]。旧姓・安田。
2010年同大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程単位取得退学。
2011年、「国際連盟保健機関から世界保健機関、ユニセフへ:新しい安全保障としての『ポジティブ・ヘルス』の形成」で博士(学術)。
東京大学東洋文化研究所助教、関西外国語大学専任講師などを経て、
2020年東京都立大学法学部教授[3]。
2018年(37歳)のときに准教授になっているのですが、そのわずか2年後、2020年(39歳)に教授に昇進しているんですよね。
ちなみにwikipediaには書かれていませんが2023年からはフランスで教職となり、2024年からは慶應義塾大学の教授となっている模様。
普通こんなに早く、この若さで教授になれないはずですよ。異例の昇進じゃないかな。
そして同じ年に↓の著作を発表して、箔付のように賞を受賞していると。
これ以外に目立った著作はなし。しかも新書レベル。
うーん、なんか作り物の臭いがプンプンするんですが。
ちなみに私事ですが、僕の卒論担当教官はその道ではかなり高名な学者で、著作もいくつもある人でした。
それでも40代後半でまだ助教授だったんですけどね。
この人が教授になった2020年に、何が始まったかはみんなご存じですよね。
詫摩佳代氏の名前は2020年以降、頻繁にいろんなメディアで目にするようになってきます。
以上の作業はWHOに任せておけば良いものではない。WHOは国際機構であり、自ら主体的に何かができるわけではないからだ。
権限を決めるのも加盟国であるし、改革のための具体的なロードマップを作成し、実行に移していくのも加盟国である。
また改定に必要な賛成票を集めるべく外交を展開するのも加盟国である。とりわけWHOの権限を強化するという改定案には、国家主権への侵害を憂慮する多くの国が反対することも予測されるため、関係国の合意形成に向けた外交的努力が不可欠である。
従来、そのような動きをリードしてきたアメリカが保健協力に背を向け、中国には公正な改革をリードすることは期待できない。となるとヨーロッパやオーストラリア、日本などWHOに継続的に連携してきた国々の積極的な関与が不可欠となる。
この記事はコロナ禍初期の2020年のものですが、すでに現在問題になっているパンデミック条約の国家主権侵害の懸念について書かれていますね。
記事を全文読めば分かりますが、詫摩佳代氏はWHO主導でパンデミック対応できるようにするというWHO権限強化派であり、2020年の段階でそれは国家主権とぶつかるという認識を持っています。
その彼女が、
保健分野での国際協力に詳しい慶応大学の詫摩佳代 教授は「WHOが強い権限を持つとか、誰かに対して何かを強制するということはそもそもあり得ないことで、条文のどこにも書かれてない。国際法は基本的に、国と国が合意して初めて成立するものであって、それをどのように運用するのかは国家の裁量にかかっている。国際機関が国家に対して何かを命令したり強制したりすることは、パンデミック条約に限らず、国際法の基本としてあり得ないことだ」と指摘しました。
このように発言することを、はたして信用できますかという話ですね。
東京都立大の人事についても調べてみました。
この中に以下のような記述があります。
2015 年までの任期制教員は国立大学等の標準的な昇給を続
けてきたものに過ぎず、任期を選択しなかった教員は、標準の
昇給を受けていなかったのであるから、その較差を是正すべき
であるというのが、組合の主張です。言い換えれば、時の首長の
意向に沿わない教員に対して、不当に安い給与を押し付けてき
たことについて、均等待遇を求めているのです。
時の首長とは、東京都知事のことですよね。
石原慎太郎東京都知事の掲げた「まったく新しい大学をつくる」という公約のもと、東京都大学管理本部が2003年に発表した「都立の新しい大学の構想について」という新大学構想に基づき設立された。管理本部による強引な新大学への移行方針に抗議して、反対する複数の教員の退職や新大学への就任拒否などの事態も生じた。母体となった大学は、東京都立大学、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学、東京都立短期大学である。以前の大学名である「首都大学東京」は日本で唯一「大学」の語が末尾に付かない大学であった[注釈 1]。
東京都立大学は一時期「首都大学東京」と名前が改称されましたが、単に名前が変わっただけではなくて体制が変わって、いったんはほぼ別の大学として生まれまわったんですね。
その時に東京都知事の政治による介入があって、それに反発した教員が複数辞めたと。
2020年からまた名前がもとの「東京都立大学」に戻りましたが、名前は戻れど中身は別物ということらしいですね。
ようはこの詫摩佳代氏のわずか二年での教授昇進に、政治の介入があったのではないか?という疑義について、これだけでは証明にはなりませんが、少なくとも補強はできるのではないでしょうか。
東京都立大学のグローバル教養講座とやらに小池百合子と詫摩佳代が並んで登場していますね。
動画の中身では同時に登場してはいないのですが、東京都立大学に対して直接の権限を持っている小池百合子がこのように政治色の強い問題について東京都立大学とコラボするというのは、大学自治という観点から見て、ザワザワするものを感じます。
しかも、全国の知事の中でもことさらにコロナ対策にご執心だった小池百合子ですからね。
大学が政治に屈するというのは、あくまで政治に対して中立で公平であるべき学者の立場を脅かすことですから、由々しき事態なのですよ。
真理の追究が目的のはずの学問の府が政治の介入を許したら、学者の言うことに信頼性を担保することなどできないでしょうに。
そしてそのような東京都立大学でわずか二年で、コロナ禍に合わせるように教授に昇進した詫摩佳代。
やはりこの人は胡散臭いです。