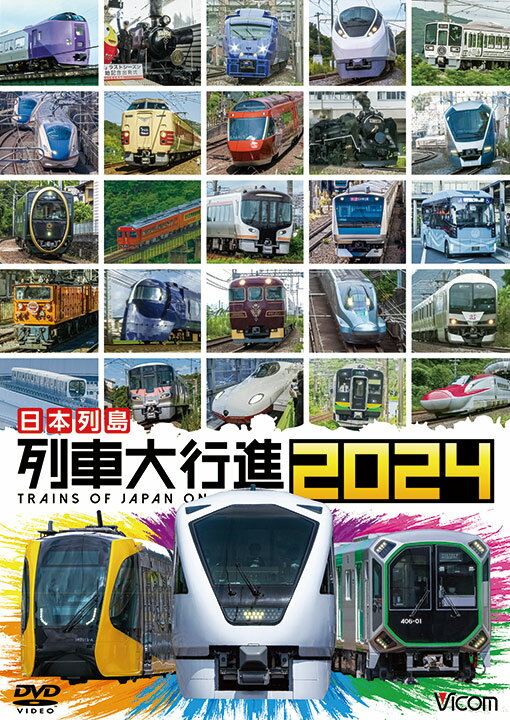皆さん、俺のブログを閲覧してくれてありがとうございやす!
今回も、文学フリマ東京ついでの旅の記事をお届けします。
第三弾は、東京都の小都市・青梅の街中を逍遥(しょうよう)した際のルポとなります。
時期は、やはりJR青梅線と奥多摩町を巡った2024/05/18(土)。
この日青梅市を出歩いたのは、奥多摩町を散策した午後の時間帯でした。
天気も良かったので少々蒸し暑さもありましたが、雨に降られるよりは幾分マシでしょう。
ともあれ、23区とは全く異なる長閑な田舎町の風情を十分に満喫できました。
...それでは、ここでWikipedia先生をカンニングして、青梅市について予習しましょう↓!
青梅の町の名称は、平将門が現在の市域に所在する天ケ瀬の金剛寺という寺を訪れた際、愛馬に使っていた梅の枝の鞭を地面に挿したことに因んでいます。
「新皇」として自身が天皇に対抗し得る権威となるための願掛けですが、その梅の枝は花が咲き結実はしたものの、実は熟さずに青いままでいたそうです。
この故事が「青梅」の地名の由来だとか。
その後の歴史はWikipedia先生も詳細を教えてくれませんでしたが、1894(明治27)年に青梅鉄道が開通し、青梅市が発足したのが1951(昭和26)年という記述がありました。
有名な「青梅マラソン」は、1967(昭和42)年に始まり、2024(令和6)年には56回目を数えています。
また、青梅の商店街は「昭和レトロ」を掲げてまちおこしを行っていましたが、看板等を手掛ける職人さんが亡くなり新たなレトロ看板を制作出来なくなったそうなので、現在はネコを活かしたまちおこしに舵を切り替えています(猫の街)。
それでは、青梅の概略を予習されましたところで、早速写真をご覧になられてみましょう↓!
先にもご紹介しましたが、スタート地点のJR青梅駅。
ここを起点として、狭い範囲ながらも街歩きを実行しました。
お社。
簡素な鳥居が特徴的ですね。
多摩ミシン商会。
地元で永年愛されてきた店舗でしょう。
「摩」の字の中身がカタカナの「マ」となっている点、印象的ですね。
...しかしこの略字、新漢字を制定する際に、どうして採用されなかったのだろう...?
昭和のレトロ建築と、明治・大正期の築と思われる商家が仲良く並んでいます。
こういう光景が当たり前に観られる点が、青梅の良いところですね。
「理容 山口」
これは見事な看板建築です。
時代としては、おそらくこの店舗建築は戦前からこの地に佇み続けていたのでしょう。
ポケットパークの入り口に佇むオブジェ。
この町には、通行人が歩き疲れたなら何時でも無料で休憩できるスペースや、腰を落ち着けられるベンチが其処彼処に設置されています。
いわば「人にやさしい町」。
消防団の建物。
「看板建築」とは定義が少し外れますが、これまた青梅の歴史と住民の方々を永い間見守り続けた建物です。
カフェでお茶にしよう...と、思っていたところが生憎のCLOSED。
しかし、このオブジェが撮影できただけでも大きな「収獲」となりました。
廃部品を組み合わせて、ロボットや謎の機械が紡ぎ出されているオブジェ、なかなかユーモラスです。
看板建築の並ぶ通り。
眺めていて飽きが来ないですね。
これまたポケットパークのオブジェ。
「排除アート」とは異なり、休む人の憩いを妨害しません。
なかなか見事ですが、同時に計算し尽くされて設置してあるみたいです。
ヘアサロン。
何気なく佇む店舗ですが、この通りのそれぞれの建物が「歴史」「街の移り変わり」「道往く人々」を、もう何十年と見守ってきたのでしょう。
青梅の良いところは、このような「昭和の庶民的な住宅」にもリフォームが施され、瀟洒なカフェに改築してあるのに出くわすことかと。
このようなカフェ、市民の憩いの場であり観光客の一服の場でもあります。
コチラから商店街に入りますが、その入り口にも看板建築が佇んでいました。
商店街を歩いていると、何やら歴史ありげな料亭が。
看板から見るに、うなぎと天ぷらで有名な老舗らしい。
「雪守横丁」という商店街の脇道を歩いていると、こんな小石を見つけました。
これは「傍示石」と呼ばれるもので、かつては屋敷と通りの境目を示す目印とされていたそうです。
そしてこの隘路が「雪守横丁」。
風情のあふれる通りですね。
いよいよ街歩きの終盤。
こちらは商業ビル。
ごく最近建てられたビルですが、それでも細やかなデザインが目を惹きますね。
この日は一挙に3カ所(青梅線・奥多摩町・青梅市)を巡りましたので、私もすっかり疲れてきました。
最後の気力を振り絞って、再度大通りの看板建築を撮影。
そしてゴール。
「まちの駅 青梅」
看板をよくよく注視しますと...???
「創業 平成二十八年」
なんて表記が。
新しいレトロ看板、なかなか心憎くなりますね。
以上、2024/05/19(土)に巡った多摩地区探訪を、全てお届けしました。
この日、青梅の市街地を歩いて思いました。
「この町は何処までも人にやさしい町なのだ」
と。
翻って、東京23区はどうなのでしょうか?
自分は新橋以外の「23区」はほとんど知らないのですが、その新橋の駅前広場を眺めても、ベンチなんて全く見当たりませんでした。
どうやら、自分の座る場所にホームレスが寝られては堪らない!という行政と市民双方の判断ゆえに、休憩できるスペースを徹底的に無くした模様です。
そしてそれで23区もんのサラリーマン連中は、歩き疲れたなら平気で地べたに座ってコンビニで買った缶チューハイを呑み、ツマミを齧るという風習が根付いているらしい。
実に「非文明的」です。
23区こそが、23区もん共が内心見下して止まない「奥多摩の民」「青梅の民」を遥かに下回るほどの未開・野蛮な地としか言いようがありません。
ホームレスであろうが高齢者であろうが障碍者であろうが外国人であろうが妊婦であろうが児童であろうが、誰であろうと優しく受け容れるベンチやポケットパークを至る所に設けている青梅市こそが、東京23区が忘れて久しい「人が人を排除しない町」なのです。
自分たちを「日本の何処よりも先進的である」と自惚れる23区もん共は、今一度青梅のあちこちに設えられたポケットパークから「人が人を排除しない意味」を学ぶべきでしょう。
次回のブログ更新は、文学フリマ東京開催日の翌々日早朝に、新橋をそぞろ歩いた際の記事をお届けします。
皆さん、楽しみに待っておくんなんし!
(罵詈雑言・個人攻撃・誹謗中傷大歓迎!)